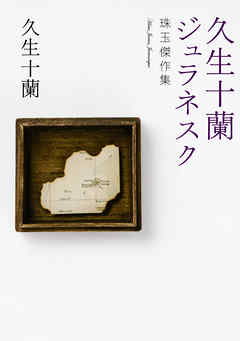感情タグBEST3
Posted by ブクログ
最後の「死亡通知」のオチがわからない。再読すべし。
それはともかく、岩波文庫とまったく重複がないのがよい。また小説ジャンルも多岐にわたっていて
力量を感じさせる。
Posted by ブクログ
堪能しました!明治35年生まれの著者の短編、あらゆる味わいの十編、「絢爛豪華な傑作群」というに相応しい。(著者について詳しいことはこの文庫の年譜などご参照ください)。昔、教養文庫か何かのを読んだだけと記憶していた(それでも「久生十蘭」という名を忘れられなかったのだ)けれど、どれも懐かしい(最初の『生霊』は鏡花的)。『葡萄蔓の束』(アナトール・フランスをも思い出す……)や『藤九郎の島』(芝居の俊寛などを想起)を強烈に記憶しているように感じられるからには、そもそもいったい何を読んだのだったか、そのへんの記憶さえ曖昧。既視感ならぬ鮮明な既読感……まさか。国書刊行会の全集は手に入れられそうにないから(欲しい・読みたいからといってすべてを手元に置くわけにはいかないもん、ね)、気になって積んどいた岩波文庫もちゃんと読もう。「出版不況」ではあるけれど出版点数は増えているとのこと。部数は少なくても、こういうのが文庫で新しく出るのは嬉しいことです。読者・購買者がどういう態度をとれば「本の味方」でいられるのかよくわかりませんが、私は本の味方でいたいなぁ、と、つくづく思います。
Posted by ブクログ
収録作品の初出は1940(昭和15)年から1956(昭和31)年。
実に巧緻な久生十蘭の短編小説集。一作一作が異なる方向を向きながら、完成度が高い。語彙が豊かなので分かりにくい熟語も出てくるけれども、物語色の強い短編小説を究めたい人なら読んでみるべき作家である。
しばしばガルシア・マルケスみたいに物語が奔走する感じで、本書中では「美国横断鉄路」が、残虐なリンチの場面が淡々と描かれていて強烈だった。
久生十蘭を読むことは物語を読むことの大きな楽しみをもたらす。ただしそこはどこか閉鎖的な空間のようでもある。あまりにも技巧的でカメレオン的であるので、個々の作品は「閉じて」いて、外部を寄せ付けないような何かがあるように感じられた。あまりにも精緻な工芸作品、という感じもある。一部のマニアを惹き付けるような文学世界である。
Posted by ブクログ
冒頭の「生霊」のドメスティックな物語からは想像もできないオチがまるでコルタサルでいきなり度肝を抜かれる。精緻で端正な文体と小説という表現スタイルだけが引き起こしてくれるめくるめく感覚。
Posted by ブクログ
素晴らしい。
収録されているどの短編も、驚くほどに生々しく、それでいて技巧に富んでいる。
なのに全く作為のようなものが感じられない。あまりに自然で、しかし緻密で、澄み切っているのにずっしり重たい。
最初の数編を読んで、そのあまりの出来栄えに私は舞い上がってしまった。これは凄い、これは素晴らしい、思わぬ掘り出し物だ、と。
しかし、読み進んでいくうちに、なんだかその判断も疑わしくなってきた。残酷で悲惨な話も収録されていたり、漢字や言葉が難しくてよくわからない話もあったりしたせいも、もちろんあるだろう。
けれど、それだけではないような気もする。読み終わった今でも、よくわからない。
作為が感じられない、作者の匂いがしない。それは「物語」にとっては、プラスにはなっても、マイナスになることはないものだ、と私は思っていた。
しかし、この本を読み終えてふと、私は首をかしげたのである。こんなに素敵な短編集だったのに、こんなに精巧で緻密な作品群を読めたのに、なんだかいまいち自分が「くたびれて」ないなぁ、と。
おかしな話だけれど、こんなに濃くて良質な短編集を読んだのに、さっぱり「付き合った」感じがしないのである。
なんだか変な感じだ。その「変な感じ」を、澁澤龍彦は解説にてこう現している。
「作者は作品の影に完全に隠れてしまって、ついに最後まで、ちらりとも姿を現さず、私たちの目を奪うのは、凝りに凝った、あまりにも凝りに凝った作者の超絶技巧のみなのだ」
とても納得できる表現である。しかし、その「ちらりとも姿を現さない」ところが、どうも私には少し、さびしく思われてしまったのかもしれない。
Posted by ブクログ
「フィクションとしての小説というものが、無から有を生ぜしめる一種の手品だとすれば、まさに久生十蘭の短編こそ、それだという気がする」と、解説で澁澤龍彦が指摘しているが、その通り。
私は作者が現れてくるような作品の方が好きな場合が多いけれど、久生十蘭のプロ技は素直に凄いと思う。
『無残やな』『死亡通知』『藤九郎の島』あたりがなかなか気に行った。奇妙なほどあっさりした描写が面白い。
でも結局一番好きなのは『生霊』で、久生十蘭の味というよりは、田舎の因習やそれに類するものの土着的な不思議な雰囲気の描写が好きなだけなのかも知れない、という気もする。
Posted by ブクログ
どれもおもしろかったが
「葡萄蔓の束」「その後」「死亡通知」
の三篇が特に素晴らしい.
十蘭の作品は全集でなければ読めないものも多いのでこの手の文庫化は嬉しい.
Posted by ブクログ
現代物、時代物、幻想譚、ルポルタージュ風など、さまざまな作風の短編が10作。
読み慣れない漢語が多いが、読んでいるうちに引き込まれ、意外とスラスラ読める。