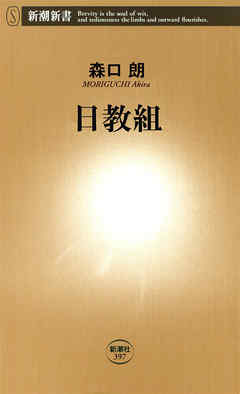感情タグBEST3
Posted by ブクログ
面白い。
謎の悪の組織「日教組」は物心ついたころに知った。この組織が戦後日本をおかしくしたとか、国旗や国歌を踏みにじる教員がいるとか。
ただ、本当に日教組に所属する教員がみんな共産主義者なのかというとさにあらず。実態に切り込んだ上で、現在もある程度の力を持つ日教組に対する処方箋を提示する。
Posted by ブクログ
常に批判の矢面に立たされる印象の強い「日教組」ですが,私自身はその実態をあまりよく知らないので,大変参考になりました.日教組ばかりではないのですが,現在の日本の教育に,極めて深刻な問題が残されているのは事実だと思います.とは言え,この書が出されたのは民主党政権時代であり,現在は自民党政権に逆戻りしているため,冷静な目で見守っていけばよいと考えられます.
Posted by ブクログ
わかりやすかった。
何も知らない一般人に伝わるように書こうという心意気を感じた。
前半の構成が特によい。
まず「教師の倫理綱領」を紹介し、次に共産主義について詳しく説明した後で再度「倫理綱領」を提示すると、
「なんということでしょう?!」となる部分は単純に面白い。
国旗国歌のことでなぜあんなに大騒ぎしてニュースになるのか全然理解していなかったが、
共産主義者にとって資本主義国家は打倒すべき存在なので、
国家の象徴である国旗や国歌も当然憎悪の対象となる、ということだそうだ。
軍国主義を思い出させるからかなーとなんとなく思っていたけれど、これって常識だったら恥ずかしい…
しかし、日教組の人が全員共産主義者なわけはなく、一部の人が熱心に活動し、権力を握っているだけらしい。(顕教と密教)
地域によっては100パーセント近い加入率の所もまだあるが、ほとんどの地域では組織率は
低下し弱体化しているとのこと。
民主党は日教組の言いなりらしいが、その理由が献金ではなく「選挙運動を手伝ってくれるから」というのは驚いた。
選挙運動員にバイト代を出すことは公職選挙法で禁じられているので、
運動員のボランティアをどう集めるかは大変な問題らしい。
だいたいからして選挙運動に意味があると思えない。
ビラを配っていても受け取らないし読まない。
ホームページで政策を分かりやすく説明し、演説したければYouTubeにUPすれば、見たい人は見るでしょう。
私の知らないところには選挙カーで連呼されていた名前についつい投票する人が沢山いるのか?
むしろうるさくて頭にきて、絶対に投票せん!という人の方が多いと思うのに。
組合費は先生達のお給料から天引きされているので、それを禁止すれば弱体化は容易だそうだ。
それを放置した自民党も悪い、というお話でした。
Posted by ブクログ
この日教組研究入門書、やや保守っぽい気がしないでもないけど、間違いなく読む価値がある。教育に少しでも関心のある人は読むべきだね。僕も日教組については具体的な内容をあまり知らなかったけど、この一冊でそこそこ知識を吸収出来た。難しい言葉も使ってないし、とっても分かりやすい。新潮新書では、創価学会研究入門書である島田裕巳の『創価学会』が良かったけど、この本も同じくらいに良いね。新潮新書は入門書系に強いな。
Posted by ブクログ
日教組というイデオロギーを知ろう!アンチ寄りな本です。ただ内容はちゃんと広く浅くだと思う。無理に中性的よりもこのくらい偏見を素直に出している方が読みやすいです。
ただ流されやすい人は読むのに注意は必要。右に流れる。
_____
p3 学力テスト
1964年に日教組が潰した。階級意識を生み出す学テは社会主義の敵を生み出すしくみ。
p53 日教組はGHQの出した法に従っていただけ
戦後の文部省は戦前の日本を完全否定する教育をする姿勢を見せなければいけなかった。「新教育指針」に則って日教組は教育活動をしただけ。
聖職者である教師を労働者と考えるのは間違っているというのも、文部省が労働協約を結んで労働者としたんだから。
政治活動をする日教組は政教分離を知らない。というのも当初政治活動は許されていた、それを文部省が後だしジャンケンで封じた。
色々ある。悪いのは日教組だけではない。当然教育の柱を決める文部省と政権に一番の責任があるはずだ。
p60 日教組の組織率減少
1958年から減少し始めた。勤務評定の闘争でストライキを起こしたりして、世間からの見られ方も変わった。子供をないがしろにして自分たちの賃金闘争を繰り広げる教員への不信が広がった。
p62 学力テスト②
詳しく書いてある節
p76 教育の神性
教師が聖職者だったのは天皇が神様扱いされていたから。天皇の勅令(教育勅語)という神のお言葉を臣民に伝道する聖職者ということだったのだろう。戦後手のひら返しをします。
丸山眞男は教師という疑似インテリゲンチャが日本にファシズム(全体主義)を蔓延させたという。
p79 敗戦
聖職者である教師にとって、敗戦は神の死であった。一億総手のひらを返しです。教師には新たに「民主主義」という唯物史観的絶対原理が与えられ、日教組という「教団」の代わりを作ることを認められたのである。
新たなる…光!
p80 平和教育
教員は戦後平和教育に熱心だった。というのも、戦時中、若者を戦地に後押ししたのは教師たちであった。p84のデータでは青少年の義勇軍訓練所への入所動機は教員の勧めが一番だったとある。
その罪滅ぼしである。反省しているのだから良いじゃない。もう二度と子供たちを戦地に送ってはいけない。
…自衛隊も??
p91 ピューリタンの体罰
アメリカにおける体罰容認の根拠はピューリタンの宗教観である。「人は本来的に弱く、罪を背負っており、真の道徳的・自律的行為は成しえない」だから愚かな人間を成長させるには人格者である教師の愛のむちがあるくらいでないとダメなのである。という理論。
p92 日本の体罰
明治時代1879年の教育令の時代から体罰は禁止と法律にある。昔は体罰なんて当たり前だったというのは、「昔は法律なんかあってないようなものだった、それがよかった」というようなものである。おさるさんだね。
日教組のせいで体罰がなくなったというのも微妙らしい。時期的に1970年代から減少するが、日教組の組織率が下がり始める時期と呼応する。単に戦前の体罰教師がやめていったからである。
p98 人権は神なくしてはありえない
人々に人権があるのはなぜか。それは神が与える絶対的な権利だからである。だから何人たりともこれを冒せない。というのが天賦人権論である。
社会主義者が人権を言うが、唯物史観で言えば神なんてないのだから神家という用語を使うのは変だよね。
1952年に日教組が作った「教師の倫理綱領」には人権について書かれていない。代わりに科学という言葉が多用されている。
p112 八分の一理論
田中角栄の権力理論。国政選挙で過半数をとる、自分の党で主流派(政権に近い派)が過半数をとる、主流派で自分の派閥が過半数をとる。つまり国会議員の八分の一が自分の派閥の人間なら首相になれるのである。
p161 明日から使えるいじめ対処法
①いじめの認知は被害者、親、友人、加害者、誰からの報告でも「この事態を心配する人からの報告」で統一する。
②教員は複数人のチームで対応する。
③複数の加害者と複数の教員が一対一で別室で話す。(加害者の話の矛盾を見つける)
④15分後に加害者を一人で残し教師で集まり、情報共有・矛盾点の分析を行う。
⑤ ③④を繰り返し加害者にいじめの事実を認めさせる。
⑥加害者に対し泣かせるまで対処する。
⑦すぐには謝らせず、罪の意識を覚えさせる期間を作る。(すぐに謝ると加害者はスッキリして反省が足りなくなる)
⑧一週間後に加害者に謝ることを「許す」。(そう簡単に罪の清算ができないということを意識づける効果かな)
これは日教組の先生が実践しているいじめ対応である。日教組の先生に偏見を持つ人は二元論でしか物を見れない視野の狭い人間である。日教組に加盟するくらいまじめな先生がダメなわけがない。ダメなやつもいるというだけ。
p176 かんがえるろう
管賀江留郎『戦前の少年犯罪』という本が面白そう。戦前の子供たちはさぞ優れた倫理的人物ばかりのように思えるが、凶悪犯罪もあったという事実をまとめている。作者名からしてふざけているが、一見の価値はあるかも。
「戦前教育は戦後教育より良かった」という印象はデータでは確かにそう読み取れるかもしれない。殺人・強盗など凶悪事件が最も多いのは1960年台の子供たちである。それから減少するが、反比例して窃盗・横領など経済犯罪が増加し続ける。戦後教育では正義というものを教えられないのだろうか。
まぁ昔の統計がどこまで現代と同水準なのかは怪しいが…。
p185 法の穴
地方公務員法には政治活動の禁止が乗っているが、罰則規定はない。公務員法は倫理的に縛っても罰則で封じるという手段は講じない片手落ちなのである。だから日教組の先生はやったもん勝ちでガンガン政治活動する人がいる。この状態を見て見ぬ振りしたのが自民党55年体制である。
p192 国旗国歌問題の本質(慣習と法制の愚)
この問題が噴火したのはなぜか。1989年の竹下政権下で学習指導要領が変えられ、「国民の祝日などに儀式をなど行う場合には、児童に対してこれたの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し国歌を斉唱させることが望ましい」とあったのを「入学式や卒業式にはその意義を踏まえ、国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導するものとする」となった。
法律で国旗・国歌を規定した場合、例えば共産党なんかが政権を握れば速攻でそれらを変える法律を作るだろう。それが国民の慣習で決まっているものなら、法律で権力者に縛ることはできなくなる。
法律の落とし穴。無理に決めようとするから反発が噴出したし、君が代・日章旗を失う危険性も生まれた。
p196 反共=軍国主義というロジック
日本において共産党は戦時中ファシズムと闘った唯一の勢力だった。だから戦後共産党は奮った。そのせいで反共=軍国主義への回帰を求めるものというロジックができてしまい、反共アレルギーができてしまった。
p198 日教組を維持した方が票を稼げる
自民党がなぜ日教組を本気で潰そうとしないのか。
①反共アレルギーがでて、軍国主義への回帰だと誤解を騒がれるから
②日教組という嫌われ者がいたほうが、選挙相手のネガティヴキャンペーンに利用できて、浮動票確保につながる。
特に②が納得。いいこと聞いた。
p205 選挙とバイト
選挙活動でバイトを雇ってはいけない。公職選挙法違犯になるのであくまでボランティアになる。このボランティアをどこから捻出するか、教団の会員か、後援企業の社員か、後援組合の組合員か、のどれかだろう。こういう選挙に必要だから日教組も政党との繋がりから免れない。
p219 ハードルを下げると優秀な人材は集まらない?
民主党の政策では「教員免許更新制の撤廃」「教員資格に大学院卒を加える」というものがあった。これは明らかな既得権益者保護政策。大学院卒の資格は風前の灯になっている教員養成系大学の延命政策である。
ハードルを下げると教師の質は落ちるのか。参入障壁の撤廃は競争により質の向上が見られるのは経済現象の基礎である。教育に経済理論をあてるのはタブーみたいな考えがあるけれど、これは経済どうのではなく、単純な意見である。大学院卒業したからって優秀とは到底思えない。それどころか、まさか教員になるのに経済格差を発生させるとか、それこそ悪である。
p234 検非違使の放免・目明し
どちらも平安時代と江戸時代の、警察機構が犯罪者を釈放する代わりに働かせるというしくみ。悪い奴というのは言い換えれば能力のあるやつであることが多い。これを生かす方法である。
筆者は日教組もこのようにうまく使えばいいと考えている。毒を以て毒を制す。
組合にいる保守派層の人々を決起させ組織の正常化を図るということか。
____
やはり組織が大きくなると運営に多大な労力が生まれ、自己矛盾や腐敗が生まれてしまう。日教組も全部が悪いなんてことはない。しかし、社会主義的イデオロギーの押し付けになっているところはいけない。教育は中立でなければいけないのだから。
なにが中立なのかという答えのない議論を吹っかけられるかもしれないが、答えは「あんたと私の意見の中間だ」である。
2014年、第二次安倍内閣がきっと大きく教育を変えるだろう。自民党が長年なぁなぁにやってきたツケを今こそ清算する時なのでしょう。
日本はぶっ壊れてしまうだろう。まぁ、今が必ずしもいいわけではない。新しく作っていく、その心が大事なんだ。
Posted by ブクログ
概略をさらうのには良書。現場にいた過去がありながら極力客観的に努めていることには好感が持てる。
戦後の教育行政はある種の敗戦からの反動で、過去の全否定。
それを現代に至るまで愚直にまで追及しているのがこの組織。
過程において完全に手段が目的化してしまっているのには笑える。
Posted by ブクログ
公立学校の教職員の労働組合である日本教職員組合、略して日教組について一般向けに解説した入門書的な本。
日教組というと、反日的な歴史教育、組合員たる教員の政治活動の参加、子供への過保護(体罰禁止など)といった事柄で悪名高いが、思えば自分は日教組について詳しいことは知らないので、参考のために読んでみることに。
著者は多くの日教組批判はデタラメであると述べた上で、日教組に関係する事件を取り上げつつ「戦後民主主義の申し子」と形容する。どういうことかと言えば、反日的教育=自虐史観は1947年5月15日、文部省(現・文部科学省)発表の「新教育方針」に従ったカリキュラムに基づくものに過ぎないし、政治活動についても文部省との労働協約で保障されたものだし、体罰禁止も既に1879年の「学校令」で定められていたもので、戦後になって初めて決まった方針ではない、といったことである。
日教組と文部省(+自民党)は文教政策を巡って対立関係にあることが認知されているが、それはプロレスショーに過ぎず、共犯関係にあったのだと言う。そうすることで日教組と文部省はそれぞれ自分に向けられた批判の矛先を相手に逸らすことができるし、自民党は日教組を叩くことで保守票を取り込める。
著者は日教組を一種の宗教組織に準える。戦後民主主義を布教するムラ社会的な組織だと。日教組が基本的人権の尊重を掲げる戦後民主主義と、人権を認めない共産主義という、相容れない思想を同時に標榜していたのは、インテリ層を取り込むためだったそうな。そう言えば日本のリベラル派はどこか共産主義的なイメージがある。
私も日教組に所属する教員の中に、「尊敬する人は金日成主席」と言う人や、自衛隊員を父に持つ小学生に対して「○○くんのお父さんの仕事は人殺しです」と言う人のような極端な思想の持ち主がいることを聞いたことから、悪い意味で左翼的な組織だとは思っていた。
だが、「日教組が日本を堕落させた元凶」といったような感情的、短絡的批判にも賛同できなかった。有力とはいえ、たかが一労働組合が1億人以上の人口を抱える国全体を左右すると考えるのは、過大評価が甚だしいと思っていたから。著者の主張に従えば、教育現場の現状や、文教政策について日教組だけを批判するのは片手落ちである。日教組を生かしてきた文部省(文科省)も視野に入れて批判するべきだと言う。
戦後の政治や社会にも密接に関わる話なので、結構勉強になった。
Posted by ブクログ
日教組が悪い。
そう思っていたが、実は日教組だけではないということには目から鱗。
でも日教組はとんでもないことには変わりない。
じっくりと日教組の動向を伺うのに、一つの資料となる好著。
Posted by ブクログ
あまりにもストレートな題名だったので買うのが怖かった。
でも、読んでみると面白かった。
中立的な立場から日教組をみている。
疑問に感じていたことがこの本を読んで解決した。民主党政権になり、滅びかけていた日教組が蘇ろうとしている。
Posted by ブクログ
悪名高い日教組。
元々は、GHQ、文部省肝入りでできたもんなんだな。共産党とのいろんな押し引きもあって、むしろ過激になってきたかと。
このところは流石に人員不足らしい。
うちの息子が学校の先生なんでちょっと心配。
Posted by ブクログ
自分自身の先入観を確認する上でも、手軽に概要を掴むには手頃な本だと思った。
新書なのにもう一度読み返して理解を深めてみたいと思った珍しい一冊。著者の偏見がほとんど見えてこないからなのかもしれない。
これで全容が理解できるわけでは無いし、真実がどこまでなのかも判断はつかないけど、とりあえず一度読んでから今の日本についてもう一度考えてみるのも良いかなと。
そして、自分自身がどこまでステレオタイプに汚染されているかも、一度確認してみる必要があるかも。
Posted by ブクログ
私には難しい本でした。思想背景や政党との関係を歴史を追って知ることはとても骨が折れます…一回読んだだけではよく分からなかったので、いつかまた読み返したいです。
いくつか気になった点を羅列。
・幹部は密教信者
・保守政党である自民が日教組を非難しないのは、政治の道具だから。選挙前、両者はプロレスの関係に。また、日本型リベラリズムは共産主義に寛容だから。
Posted by ブクログ
部落差別をはじめとするあらゆる差別問題に真正面から向き合った経験のない保守の学者が書いた本を、日教組組合員である私がひととおり一読したということを前提に感想を述べると、納得できる部分、納得できない部分、自分の認識と異なる部分が出てきて、私にとっては波の激しい展開で構成されているなというのが率直な感想である。
この著者が部落差別問題や在日朝鮮人差別問題に真正面から向き合ったときに、自分自身が綴ったこの文章をどうふり返るのかが非常に興味深い。
もし自身が「教育評論家」と称するならば、ぜひとも上記の差別問題に真正面から向き合っていただきたい。
そしてまたもう一度、日教組について論を展開してほしい。
それが、日教組組合員である私からの提言である。
Posted by ブクログ
積読している間に政権が自民党に戻ってきてしまった。
この間、結局教員免許更新制は継続しているし、全国学力調査は悉皆に戻ったし、あまり大きな変化はなかった(ようだ)。「心のノート」は復活しそう。
Posted by ブクログ
以前読んだ『創価学会』と同じように、なるべく中立的なスタンスからこの本は書かれています。
日教組とはどのような組織なのか。
ステレオタイプ化されている日教組の印象を分析しながら、誤りは誤りとして反証を示し、正しきは正しきとして実証をしていきます。
また、民主党がなぜ日教組の言いなりなのか、日教組の現在はどうなのか、日教組をここまで存続させてきた存在は何なのか、という点もしっかり分析しています。
それに、誤植も少ないです。
悪印象を与えがちなのが、(僕の読解力の低さもあるでしょうが)ところどころ出てくる引用です。
引用はふつう論議の裏付けに使うと思うのですが、この作者はちょっと違うようです。
「このような主張をしている人たちがいます。 (引用を連ねる) しかし・・・」
という風に、長々とした引用を読ませたうえで、それを逆接でつなげてくるので、少し混乱しました。
ただ、日教組について、精通できる点はよかったですし、作者個人の意見は小さい字で書いてくれているので、整理はついていました。
”飲み屋的論法”で批判するだけでは何も変わらない。
しっかりと実態を見つめて、事実をきちんと把握した上での批判が重要ですね。
★★★☆☆
Posted by ブクログ
お勉強に本棚に眠っていた本を再読。
うーん。社会主義とか共産主義のしっかりとした
勉強が必要だなー。。
と実感。個別の本よむとこれらの主義って
納得しちゃうから怖いけど。w
Posted by ブクログ
本書は、日本教職員組合-略称「日教組」-の設立から今日に至るまでの歴史と思想を追ったものである。ただし、巷のいわゆる「飲み屋論壇」とは異なり、長年批判されてきたにも関わらず、なぜ組織は存続できたのか、あるいは、なぜ今なお三〇万人近くの教員が所属し続けているのかといった「謎」を史料に基づいて分析している。
例えば、文部省(文科省)と日教組は長年対立関係にあったと思われがちである。だが、元をたどれば、日教組は「文部省から手渡された「新教育指針」という手引書によって誕生し、その手引書の教えを愚直に守ってきた」(p.52)だけであり、むしろ協力関係にあったと指摘する。また、最近では自民党が民主党批判のネタとして日教組を取り上げることが多い。しかし、これについても、両者(日教組と文部省)の対立が表面化した後、五五年体制で政権を握ってきた自民党は「自社なれあい構造」(p.186)を文教部門にも持ち込み、日教組を(弱体化は図りつつも)存続させてきた過去を明らかにし、今日まで選挙時の「浮動票獲得のネタ」(p.199)に利用してきたに過ぎないとして、自民党の責任を追及している。
著者は、教育正常化のためには日教組の弱体化が不可欠であると述べているように、日教組には批判的な立場を採る。しかし、巷の「何でも日教組が悪い」という議論には与しない。むしろ、本書が最も批判の対象としているのは、そうした無責任な日教組批判-例えば、自称“保守”政治家による批判など-であると言えよう。批判する以上は、まずは敵の正体を正しく理解してから・・・という著者の姿勢には見習うべきものがある。
Posted by ブクログ
日教組というと、現代教育の諸悪の根元のような言われ方をしている先生の組合というようにしか知識がなく、本当のところ一体何なんだろうと思い、本書を手にした。
私の認識それ自体はまさにその通りだったのだが、果たして実態は必ずしもそうではないらしい。ということはわかったが、どうもなんとなくピンとこない…。
著者いわく、本来はたいした力もない弱体団体だったのが、民主党政権になったことで俄然権力を手にし、今後の政治的動きに要注意、ということなのだが…。
こんな旧態然とした団体が幅を利かせていることに、限りなく違和感を覚えたことだけは確か。
Posted by ブクログ
日教組の歴史が要領よくまとめてある。社会党,共産党との関係や,新左翼による加入戦術なども。
昔通っていた小学校に,ギターで「戦争を知らない子供たち」を弾き語る先生がいた。他にも学校って色々と不思議な違和感あったけど,戦後教育とはこんなものだったのかーというのは大人になってから本を読んで知った。
成人してから膝ポンすることって他にもいろいろある。成長するって過去を体系づけていくこと。脳の記憶容量は人生でそんな変わんない。情報は,大人になるほど効率よく圧縮されてしまってある。
Posted by ブクログ
日教組に関する文献を読んだ。免許更新制度の廃止問題、全国学力テストの無意味化、教員免許のための大学院必修化などの背景を、日教組という組織の成り立ちから再考するきっかけに。完全な中立はあり得ないが、なるべく中立に判断するためには組織への正しい理解は必要だと思う。
組織というものは大なり小なり成り立ちや歴史に引きずられるものだから、組織を知ることで、その組織人の行動が理解しやすくなるものらしい。それを知った上で、どう付き合うかを考える必要がある。組織はその存続のために行動しがちなので、第三視点の導入や、ワクチン摂取などの前知識の共有が必要など。