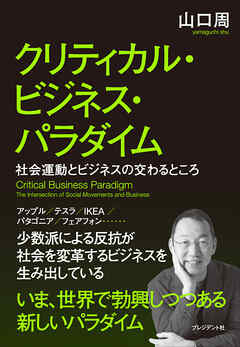感情タグBEST3
Posted by ブクログ
利潤追求優先のビジネスという活動自体を食わず嫌いし、ビジネスと社会貢献の交差点を探っていた自分にまさにクリティカルヒット。
それにしても黒カバーに緑色の字体の本には良作が多いような、、笑
Posted by ブクログ
人類は、明日を生きるための基本的な物質的条件の充足を達成した。これからのビジネスは営利よりもパーパスなどを重視していくべきだ。そのためのコンセプトが『クリティカルビジネス』であると。明快で興味深い内容である。
Posted by ブクログ
著者の山口さんは視点がユニークで、本書も読んでいて非常に刺激を受けるものとなりました。
今まで社会運動がなぜビジネスになるのか?という点について私自身は無理解でしたが、なるほど、今までの延長線上にはすでに成長要素は存在しないとか、今後は共感性が必要になるなど言われると、確かに、とは思います。
また、この本の良いところは、問題を問題としてのみで終わらせず「どうしたら自分の確信している課題が共感され大きな社会変革が生まれるか」といった手法論にも言及しているところでしょう。
「小さな問題も、啓蒙と共感により大きな問題となり、解決へのスピード感が上がる」といった考え方や、「小さな問題もグローバルでとらえることによって大きな市場が形成できる問題となる」といったスケール論などについても、多く参考とできるところがありました。
上記のほかに覚えておきたい内容がありましたので、簡単にメモしておきます。
--------------------------------
現状のAS-isはTo-beが思い描けようが描けまいが同じである。To-beを思い描くことで初めてAs-isとのギャップが生まれ、問題を認識できるようになる。
顧客の言うことを聞かない、むしろ顧客が正しい要求ができるよう、教育や啓蒙を進めて正しいフィードバックを得られるようにすることが、本当の意味での顧客志向である。
小さな問題も「啓発」と「共感」の拡散により大きな問題となり、解決へのスピードが上がる。
物的な要求が満たされている現在、「より環境に適応した消費生活を送りたい」「他者の問題を解決したい」といった新しい欲求や快楽が生じている。
とりあえず手元にあるものではじめる。失敗しても失うものはその手元にあるものだけ。
ローカルでは対象となる人数が少なく、普遍性の低い問題であったとしても、とも、グローバルにあまねく存在する問題としてとらえれば普遍性が高まる。
アクティビストに必要なのは「今は認められていないが、このアジェンダは必ず多くの人の共感を得るものになる」という確信。
Posted by ブクログ
本書で提唱される「クリティカル・ビジネス・パラダイム」とは、顧客や投資家の価値観や要望・利得の最大化を通じて自社の企業価値の最大化を目指す「アファーマティブ・ビジネス・パラダイム」(≒ 従来型のビジネス)とは対照的に、顧客や投資家の価値観や要望を批判的に考察して従来とは異なるオルタナティブを提案することを通じて社会にアップデートを起こすことを目指すものだ。前著『ビジネスの未来』で語られていた「高原社会」において我々はどのようなビジネスを展開すべきなのかという問いに対し、本書ではクリティカル・ビジネス・パラダイムを解としてその背景や具体例を論じている。
「クリティカル・ビジネス・パラダイム」そのものの議論・主張の切れ味もさることながら、その論の展開に援用された理論や引用も非常に示唆深く、普段の仕事観に影響を与えるであろうものも多い。例えば、前著から議論されてきた「問題の普遍性 ✕ 難易度」のマトリクスによる「経済合理性限界曲線」の乗り越え方はまさに本書の中核的論点だが、これを「少数派が多数派に影響を与えることで社会がアップデートされていく」というモスコヴィッシの「少数派影響理論」を応用することで解を提示したことには膝を打った。その実現のためには「小さな個人的問題」を「大きな社会的問題」へと自分ごと化するための社会的アクティビズムが鍵となるが、短絡的に自己利益の最大化を志向する従来型のビジネスを「アファーマティブ・ビジネス・パラダイム」と名付け、この対概念として「クリティカル・ビジネス・パラダイム」を位置づけることにより従来型のビジネスを「ダサいもの」として相対化するリポジショニングはマーケティングとポピュリズムをポジティブに応用した著者ならではの芸当に感じた。
また、「顧客の要望に対してクリティカルであるのが本当の顧客志向」という言葉や、人々の価値観を形成してきた/していくメディアや広告の責任と影響力にはハッとさせられるものがあった。また、ビジネスに関わっている人間であれば誰しも「課題・問題」に常に向き合いながら日々を過ごしているが、クリティカル・ビジネス・パラダイムへの理解を深めていくほどに「課題・問題」とは「あるべき姿」と「現状」の対比があって初めて「私たちが認知的に新たに生成するもの」だということが再認識・腹落ちさせられた。他にも、「ゼロサム・ゲームからプラスサム・ゲームへ」「情報は運動にとってプラスのエネルギーを生み出す」「システムは常に表の目的にではなく、裏の目的に最適化される」など、巻末の参考書籍をシェルパとしてもっと深く考えていきたいと思わされるサブテーマも多数あった。
著者は終盤、これまで論じてきたクリティカル・ビジネス・パラダイムの実現に対する日本社会の遅れ・逸脱に対する不寛容性に対して警鐘を鳴らしているが、トレードオフの論点へと矮小化させない姿勢にも感銘を受けた。(以下引用)
ーー「安定していて秩序が保たれているけれども、なんの逸脱も認められず、変化が起きない社会」と「不安定で秩序が乱れているけれども、逸脱が認められ、次々と変化が起きる社会」のどちらが良いか?と問われれれば、私の答えは一つしかありません。「どっちも嫌だ」です。
Posted by ブクログ
これからの生き方を考える。長いものにまかれる、人の言われる通りにする、みんながいいと言うものを忠実になす、という自分の基本スタイルがあるが、そうではなくても良い、と教えてもらえた。ひっくり返すのではなく、選択肢はたくさんある。
Posted by ブクログ
クリティカルビジネスパラダイム→→
社会運動・社会批判としての側面を強く持つビジネス。
昨今、日本でも会社のパーパス、社会貢献などが
持て囃されているが本書はその一歩先をいっている内容に感じられた。
読んでいて、こういう事って日本は苦手だなぁと
思っていたら、案の定、逸脱が許容できない日本社会にはクリティカルビジネスは育ちにくい土壌と書かれている>_<
だからこそ、今の日本を脱するためには最大のチャレンジだと述べているのには共感する。
Posted by ブクログ
◾️目的
山口周さんファンとして、新著だから。
◾️本質
社会運動・批判としての側面を持つクリティカル・ビジネスを通じて、経済、社会、環境問題を解決できる
◾️感想
過去の作品から同様の主張で一貫している。
パタゴニアなどをはじめてとする、「利潤追求目的型の企業ではない企業」がむしろ、市場において独自のポジションを得て、利益追求できている事実などはクリティカルビジネスの可能性を感じさせる事例として非常に納得感が高かった。著者もクリティカルビジネスを推進する立場から後半から、クリティカルビジネスに関わる方法論的な記載をしてくれている。ただし、今の日本の現状を踏まえるとすでに非常に高い視座を持ち一定のレベルに至っていない民衆にはいささか高すぎる要求に思えた。だからこそ、著者も指摘する美的センスを鍛えることが今後も求められて、著者のような啓蒙家が必要だと痛感した。
◾️ポイント
・ソーシャルビジネスとの違いは、コンセンサスが社会的に取れているかいなか。
・少数派から始まるのがクリティカルビジネス
・問題は存在しないが、あるべきを掲示することで新しい問題が生成される。
・センスの悪い客に向けてマーケティングすると、センスの悪い商品が生まれる。
・資本主義では、大きな解決しやすい問題から着手される
・システムで考えることの重要性。目の前に対処するとその解決策がまた次の問題の原因になることも。
・ヘイマエイ島の噴火の事例について。噴火で家を失ったがそれで離島した人が結果的に収入が増えている。過去はどう生きるかによって、解釈は変えることができる。→だからこそ、新しい機会に身をなげよ。
Posted by ブクログ
物質的な豊かさを追求する資本主義は終了した。脱成長を前提に、反抗の力と共感の力が社会課題を解決していくということが、山口さんらしく、数々のデータや事例をもとに主張されている。特に、なぜグレタ・トゥーンベリ氏のように「今どきの若い人」が、あえて現在・未来の社会課題に目を向けるのかの考察が面白かった。世界の趨勢とその力学、考察力や論理展開など勉強になることが多かった。
Posted by ブクログ
ビジネスの未来で言われていた高原社会でどんなビジネスが起こってくるのか、そんな内容を期待していたがそこまでは行かず。社会課題の解決とビジネスの良いとこどりはどう成立するのか知りたかった。