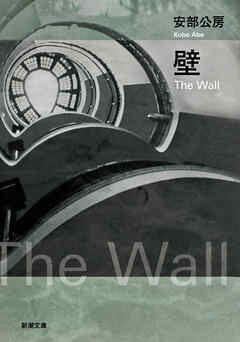感情タグBEST3
Posted by ブクログ
この本は、三部で構成されていた。第一部の「S・カルマ氏の犯罪」が第25回芥川賞を受賞したとのこと。
『壁 第ー部 S・カルマ氏の犯罪』
ある日、自分の名前が想出す(原文ママ)ことができなくなった主人公に次々と起こる非現実的な出来事。よくわからなくて何度も読み返すうちに、こにシュールレアリスムの世界観がクセになってしまった。
『壁 第二部 バベルの塔の狸』
第一部とは全くつながりのない物語だった。貧しい詩人が、公園で狸に影を食われるところから非現実な物語が始まる。最後までわけがわからない展開だった。だが、わけがわからないからこそ、読むのをやめられない魅力があり面白かった。
『壁 第三部 赤い繭』
第一部や第二部よりも前に発表されたショートショートや短編などの4作品。どれもシュールだが、長くないため比較的読みやすかった。第三部のタイトルになっている「赤い繭」は、世にも奇妙な物語を彷彿とさせるようなショートショートでとても読みやすかった。
Posted by ブクログ
第一部「S・カマル氏の犯罪」と第二部「バベルの塔の狸」を読んだとき、まるでピカソの絵のようだと思った。どこまでもどこまでも突き進む想像力が紡ぐ奇々怪々な世界。その「なんじゃこりゃ」と叫びたくなるような世界は、ピカソの絵がそうであったように、演繹という論理的な思考の展開によって極めて理性的に導出されているものだ。ただ、論理の出発点となる公理が、我々の常識の及ばぬ破天荒なものであるから、演繹の帰結としてとんでもないものが導き出される。あるいは出口のない堂々巡りを続ける。特に両作品の登場人物たち(「S・カマル氏の犯罪」で言えば裁判官を務める経済学者や数学者、「バベルの塔の狸」なら狸など)の会話は、本人たちが尤もらしい口調と論理展開でハチャメチャなことを言っているだけに思わず笑みがこぼれる。とても面白い。
第三部「赤い繭」には「赤い繭」「洪水」「魔法のチョーク」「事業」の短編が収録されている。こちらは直接話法で語られる部分が少ない分、前二部に比べてソフトな感じがする。
Posted by ブクログ
私には安部公房さんは難しいです
解説してる人も少なく、解説すら難しくて
少し残念でした。
しかし、設定はすごく面白くて
意味わからないはずなのに飽きずに読める本です。
設定は全く現実味がないはずなのに
現実に起きたかのように主人公や私の心情を
繊細に動かしてくれます。
バベルの塔の狸という章で
本当の無は無表情じゃなくて微笑だ。
だからモナリザは何考えてるかわからない。
微笑の方程式を作って10000匹の動物が一斉に
微笑するシーンが印象的でした。
飛鳥ちゃんへ
砂の女も壁も難しくて、
スマホを片手に漢字の読み方とか意味を
調べながら時間をかけて読みました。
読み終えてからも
ネットで解説を沢山探し、全部読んで、
なんとなく理解を深めていきました。
飛鳥ちゃんはすごいなぁと
思いながら読んでいます!
飛鳥ちゃんのメッセージアプリの開発中の
記事が自分の誕生日に出たので、
誕生日プレゼントみたいで嬉しかったです!
本当にありがとうございます!
最高の誕生日です✨
Posted by ブクログ
登場する主人公はどれも、日常から非日常に放り出される。
次から次へと変化するめまぐるしい展開を漫然と楽しむのもおもしろいし、作者の展開する非日常の論理を考察するのもおもしろい。
ぼく→彼→ぼくの変化はどうにも難解だった。
Posted by ブクログ
魔法のチョークが好きです。
あと人間がみんな水になる話も好き。
不思議な文章ですね、世代がものすごく違うのに、描かれている物語は現代にも通じるような、不条理で不思議で、自然の摂理に反しており、概念がそのまま文章化されているような…主人公が壁になる理由はなんだったんだろう…とか、ある名前が消失してしまい、なんか自分の存在が危うくなる…あと物が喋る。
おもしろーい。
読んだ後に知恵熱みたいのが出た。
非常に美しい文章であり、難解であり、考察に意味などあるのだろうかっていう。
現代の技術で映像化したら面白そうだなーって思いながら読んでいました。
Posted by ブクログ
ノーベル文学賞候補とも噂された安部公房の芥川賞受賞作品である。
中編と短編の計6編で構成されている。
どの作品もカフカの影響を強く受けており、『S•カルマ氏の犯罪』では主人公が名前を失い、『バベルの塔の狸』では目を除く身体を失うなど、不条理との腐心が描かれる。
しかし、カフカと違う点は、解説者が述べるように、主人公が事態を深刻に受け止めず、楽観ぎみなところだ。それが安部公房を貫徹する実存主義の在り方なのでしょう。
筒井康隆のようなブラックユーモアを効かせた怒涛のシュルレアリスムで、こんなにもニヤニヤさせられるとは思わなかった。
私の予想を超える面白さだったので、次は代表作である『砂の女』に触れようと思う。
Posted by ブクログ
きっと、これはこれを意味しているんだろう…
そう思って読み進めるも、どこかで違うような気がしてくる。安部公房のお話はそこが良い。
正解を見つけようと挑む人もいれば、なんとなく読んで終わる人もいること自体は他の小説と変わらないけれど、「読みといてくれ」という著者のメッセージをこの人からは感じない。(私の読解力不足で気にならないだけかもしれない。それほど大抵の作品は最後に行くにつれ、何かと関連しているものの完全には一致しないように感じる)
だから自由に読めるし、この感覚は絶対に本を読むことでしか手に入らない。それが六作も入っている。最高。
壁や荒野の中で、或いは外で、或いは両方で、この人の作品を読んでいる時は自由になれる。(精神的に)
自由だけれど、ほんの少しばかり疲れる。(体力的に)
Posted by ブクログ
夢か現か、現実的なのにどこか超現実で、夢を見ているよう。頭の中でイメージはできるのに言葉より強くはならない。
他作品で言うなら映画の『パプリカ』なんかが似たテイストだと思う。滑稽で愉快でどこか不安定で怖い。
Posted by ブクログ
国際的にノーベル賞に最も近い作家と呼ばれた「安部公房」の初期の代表作です。
『壁』は、作家デビューした安部公房の最初の短編集のタイトルで、収録作が芥川賞を受賞しました。
安部公房は、大岡昇平や三島由紀夫と同じく、第二次戦後派と呼ばれます。
第二次戦後派は戦後に登場し、戦前の小説技工を昇華、あるいは新たな技法を取り入れて優れた小説を生み出してきた作家たちで、その言葉の意味でいうと安部公房は、個人的には最も第二次戦後派らしい作家のように思っています。
安部公房は作家デビューの数年後に短編小説『壁 - S・カルマ氏の犯罪』を掲載します。
この作品はある不条理の中に突き落とされた男が、やがて果てしなく成長する壁になるという話で、川端康成の興味をそそり、芥川賞受賞を果たします。
その後、『バベルの塔の狸』と4つの短い話からなる『赤い繭』の3編を併せて、短編集として刊行されました。
本書でもその3作が併せて『壁』というタイトルで収録されています。
3作はそれぞれ独立した別の作品ですが、安部公房は一貫した意図で書いたものであると述べています。
また、3作に共通して、一見して意味の通らないような、現実離れした幻想的な展開をします。
ワンダーランドに迷い込んでしまったような状況の中、理屈がつかない理屈でストーリーが進み、作中の人物のみが納得する形で収束します。
安部公房は本作を書く上で"ルイス・キャロルの影響が強い"と語っています。
まさに不思議の国に迷い込んだような気持ちにさせてくれる展開で、多くの方がその内容を解釈しています。
"壁"3部作のそれぞれの感想は以下のとおりです。
・壁 - S・カルマ氏の犯罪 ...
芥川受賞作で、3作中最も長い、メインとなる作品です。
自分の名前が消えてしまった男がおり、彼は自分の事務所の名札から「S・カルマ」という名前を見つけますがしっくりこない。
彼の席には「S・カルマ」と書かれた名刺が座っていて、名刺に逃げられた男は虚無感からぽっかり胸に穴があいたような気持ちになります。
動物園に来た男は、ラクダを見ていたところ、空いた胸にラクダを窃盗しようとした罪で裁判にかけられてしまう。
「S・カルマ」氏のタイピストであったY子とその場を離れた男は、翌日Y子と動物園で逢う約束をしたが、そこにいたのはY子と名刺だった。
自分と名前が乖離して、名前の方が自分であるかのように振る舞っているところがおそらく肝で、名前という記号こそが世間で正常に暮らす場合、メインとなる側であるかのような印象を受けます。
作中に登場する、"裁判から逃れるためには世界の果てへ行く必要があり、そのためには世界を定義する必要がある、その世界の定義こそが壁である"といった理論も哲学的です。
複雑でくるくると移り変わる、端的にいえば奇妙な小説でした。
・バベルの塔の狸 ...
奇妙な動物に影をくわて逃げられてしまい、目だけを残して透明人間になってしまった男の話です。
その動物は"とらぬ狸"であり、バベルの塔には様々な哲学者の"とらぬ狸が"集まっています。
安部公房らしい暗喩的な、計算高いような、実は何も計算していないような内容で、童話のようなオチがちゃんとあるのが特徴です。
"とらぬ狸"は芥川龍之介の河童のようにおちゃめな感じがあります。
"壁"に比較するとストーリーの骨子がある程度ある、展開が比較的わかりやすい作品ですが、つまりどういうことなのかは読んで見つける必要があります。
・赤い繭 ...
本作は更に「赤い繭」「洪水」「魔法のチョーク」「事業」の4つの作品からなります。
それぞれ、赤い繭に変身した男の話、人間が液体になる話、描いたものが具現化するチョークの話、人肉加工事業の話となっています。
すべてわかりやすく読みやすいのですが、奇怪な雰囲気があり、印象強く感じました。
Posted by ブクログ
壁を隔てた向こう側に行ったら、そんなに理不尽なことに合うんだろうか、というような物語。
それは、夜中と未明の間にある壁であり、地面と空中の間にある壁かもしれない。
実態と影の間にある壁もあるかもしれない。
壁のこちら側でよかったな、あちら側には行きたくないな、という感想。
でも行きたいとか行きたくないとか、私情を挟ませないのもまた壁である。
Posted by ブクログ
【始】
壁というものがある。(序)
目 を覚ましました。(S・カルマ氏の犯罪)
ぼくのことをお話ししましょう。(バベルの塔の狸)
日が暮れかかる。(赤い繭)
ある貧しい、しかし誠実な、哲学者が宇宙の法則をさぐるために、屋上の平屋根に一台の望遠鏡を持ち出して、天体の運行をさぐっていた。(洪水)
雨もりと料理の湯気で、ぶよぶよになった場末のアパートの便所の隣に、貧しい画家のアルゴン君が住んでいた。(魔法のチョーク)
聖プリニウスは言った。(事業)
【終】
その中でぼくは静かに果てしなく成長してゆく壁なのです。(S・カルマ氏の犯罪)
もう詩人ではなくなったのですから、腹がすくのが当然なのでした。(バベルの塔の狸)
しばらくその中をごろごろした後で、彼の息子の玩具箱に移された。(赤い繭)
多分過飽和な液体人間たちの中の目に見えない心臓を中心にして。(洪水)
それは丁度絵になったアルゴン君の目のあたりからだった。(魔法のチョーク)
「彼の中の彼」殿(事業)
最初の2作は面白いけどそこそこ長いのでシュールに胃もたれする時があった。
後半の短編群が読みやすかった。
Sカルマ氏の犯罪、バベルの塔の狸、魔法のチョークが好み。
藤子F不二雄、夢野久作、筒井康隆、小林泰三を感じた。
2023.5.28
いや面白過ぎる。今までの小説で一番かもしれない。
挑戦もしている。
インスピレーションの塊。
相変わらずわからないところもあるがそれがいい。
Posted by ブクログ
不思議な物語である
話の筋がメチャクチャだか
テンポがいいので心地よく読める
キュビズムみたいに誰でも書けそうだか
安部公房しか書けない言葉
裁判のシーンは水ダウの小峠が出演した
「どんなにバレバレのダメドッキリでも芸人ならつい乗っかっちゃう説」を思い出しクスリとしてしまう
Posted by ブクログ
新潮文庫、昭和44年発行版を読んだ。
収録作は「S·カルマ氏の犯罪」、「バベルの塔の狸」、「赤い繭」(赤い繭、洪水、魔法のチョーク、事業)。
全編を通して悪い夢でも見ているような感覚であったが、面白かった。
「赤い繭」は国語の教科書にも載せられているが、なるほど一番まとまりがよく、短い中に安部公房のエッセンスの詰め込まれた作品であると気付かされた。
Posted by ブクログ
冒頭の「S・カルマ氏の犯罪」はゴーゴリの『鼻』を思わせる。名前を失った男の内なる「壁」が成長し、果ては自身を飲み込んでいく。名前は他者と区別する一つの壁かもしれない。そもそも、生物か否かの条件は、外界と隔てる壁があるか否かだ。人は壁がなければ生きていけないのかもしれない。
Posted by ブクログ
第一部の「S・カルマ氏の犯罪」はある日突然名前を失った男が、周りの人間から迫害され、最終的に壁になってしまう話。不条理小説であるカフカ『変身』の壁バージョンだろうか。いや、あちらは目覚めたらいきなり虫になっていた設定なのでちょっと違うか。でもモチーフは近いものを感じる。
第二部の「バベルの塔の狸」は、量子力学の考え方(タイムマシンが出てくるからアインシュタインの相対性理論か?)が所々にみられるのが印象的だけど、それが作品の本質じゃないことは明らか。じゃあ何?って聞かれるとゴニョゴニョだけど・・・
第三部の「赤い繭」「洪水」「魔法のチョーク」「事業」は比較的読みやすいけど、それはそれで読後に残るものがあんまり無いという。
何となく凄い作品であることは分かるんだけど、全体を通して『箱男』を上回る難解さで、何を書いてもとんちんかんな感想になりそうで怖い。こういう作品をちゃんと理解して読める人は、きっと頭のつくりが私なんかとは根本的に異なっているのだろうなあ。
Posted by ブクログ
自分というアイデンティティ、自分と他者とを区別しているもの、自分が社会生活を営むために必要としているもの。
それは、名前だったり、肩書きだったり、影であったり、家であったりする。
それらをなくしたとき、自分は自分といえるのか、社会に存在し続けることはできるのか。
壁は、社会生活に疲弊した自己を確立するためにも必要であるけれど、またその壁によって社会から隔てられ、拒絶され、隔離されたりもする。
ちょっとしたファンタジーやブラックジョークに富んだ揶揄、メタ的な表現もありつつ、深い洞察を必要とする、味わい深い物語でした。
Posted by ブクログ
簡潔に面白いと評していいのか躊躇われる作品。それは『壁』における主題を私が完璧に捉えられきれていないという不安からくるものだと思う。
しかし、捉えきれなくても、充分楽しめた。おそらく、ところどころに散りばめられた皮肉とコミカルさ(明るさ)がそういう楽しみをつくっているのだと思う。
第三部を除いて難解だった。いや難解だったというより、この作品との世界との距離感を掴みきれずにずるずると世界が進行していく感じ。SFじみたもしも話でとらえるのか、それとも主人公の主観的世界として捉えるべきなのか、多分、後者なんだろうかなあ……。
「名前」と影、第一部と第二部はどちらも内界と外界を隔てる「壁」がなくなるところからはじまる。すると世界はあらゆる論理の土台が壊れてしまう。物が動くし、結果が原因に先んじる。しかしここまでぐらいしか私にはわからない。つまり、第一部の「世界の果て」以降は内容を理解まで落しきれていない。
ただ再読したくなるほどの面白さが隠れている気配はとても感じる。たとえば第一部の裁判のくだり。コインを回されて長々と裏表を見せられる、一見馬鹿馬鹿しい議論。でも裁判は終わらない。だから有罪も無罪もない。しかし有罪になったときの罪はますます重くなる。延々と罪を重ねられ、裁かれ続ける。この意味を理解したい。
第三部はうってかわってかなり読みやすかったと思うし、面白い。
Posted by ブクログ
難しいなぁ。はちゃめちゃなユーモアが散りばめられているのだが、この物語のテーマを読み取るのが難しい。『トリストラムシャンディ』のような、奇抜さを感じた
Posted by ブクログ
第一部〜第三部、全六作が収録された短編集。どれも荒唐無稽、意味不明、奇想天外な世界観で、入り込めるものと全く入り込めないものとあった。個人的には代表作かつ芥川賞受賞作の「S・カルマ氏の犯罪」が圧巻だった。読み始めてしばらくは頭の中がクエスチョンマークで覆われる。でも次第にその世界観に馴染んでくる。
ある朝、突然「名前」を失った男が、途方に暮れて公園を歩いていると、自分とそっくりの姿をした自分の「名刺」が、職場のタイピストのY子と仲睦まじく過ごしているのを目撃する。右目だけでみるとそれは自分と瓜二つの人間、しかし左目だけでみると一枚の名刺・・・え?
さらに男は、名前とともに身体の「中身」も失ってしまったようで、目の前のものを欲するとそれを体内に「吸収」してしまうという現象が起こり始める。最初に吸収したものは本で見た曠野(こうや)風景。次は動物園のラクダ。そして彼は吸収した罪で裁判にかけられ、傍聴しにきた人々は彼に吸収されまいと法廷内を逃げ惑う・・・え?
ナンセンスに次ぐナンセンスなのだけれど、読んでいるうちじ、徐々に受け入れ可能な態勢になってしまう。お笑い芸人のZAZYがネタのつかみで「ただ今、ZAZYに見慣れていただく時間です」と言ってしばらくニヤニヤしながら無言で壇上を歩き回るあの、妙な空気感のような。一旦入り込んでしまえば、あとはもうおもしろくて仕方ない。わたしは特に72-75ページが最高だった。だからこの本を読み始めたけれど頓挫しそうになっている人がいたとしたら、なんとかしてそこまでは読んでみてほしいと思う。
安部公房は高校時代の相棒がよく読んでいた。頭が良くてイケメンで「孤高」という言葉がとてもしっくりくる素晴らしい彼の世界に少しでも首を突っ込みたくて、頑張って読もうとしたのだけれど、伊坂幸太郎を崇拝していた当時のパッパラパアなわたしには全く対応できないタイプの作家だった。心が折れたまま10年以上経ち、先日たまたま通りがかった神保町の「神田古本まつり」でこの本を見つけ、もう一回挑戦してみようと思って購入した(100円だったからというのもある)。さすがに高校のときよりはいろいろと免疫がついたらしく、6つの短編のうち少なくとも3つはおもしろいと感じるようになった。成長!
今回もなお読めなかったものは、50歳くらいになったらまたチャレンジしたい。
第一部 ◎S・カルマ氏の犯罪
第二部 ×バベルの塔の狸
第三部 ○赤い繭
○洪水
×魔法のチョーク
×事業
Posted by ブクログ
何を隠そう安倍公房大好きです。
シュルレアリスムを文にするとこうなるのか。個人的にはこの訳分からなさ具合がとても好きなんだけど、バベルの塔あたりになるとはやり若干混乱してくる。カルマ氏の犯罪程度だと公房ランドがちょうどよく楽しめていい感じ。
Posted by ブクログ
名前や身体など自分を証明するものを失い、社会との双方向の関係を断たれた人達の話です。“社会的な自分”と“本質的な自分”の対比を通して実存を考えることになります。社会との関わりを拒絶し、匿名で生きることを選んだ人(ホームレス)のことを思い出しました。厭世か達観か。
第一部 S・カルマ氏の犯罪
第二部 バベルの塔の狸
第三部 赤い繭(赤い繭・洪水・魔法のチョーク・事業)
Posted by ブクログ
名作家の名作ということで薦められて読んでみたけど、とても難しい。書いてある文章自体は理解できても、何を考えてこれを書いたのか、これによって何を伝えたかったのかは読み解けていない…
Posted by ブクログ
砂の女が非常に面白かったため、壁も読んでみたが、難解に感じた
壁と果ての見えない、踏み出す気にならない砂漠は似ているのかもしれないとぼんやり思ったがよくわからない
細かい描写や現実らしいところから一気に非現実的な要素がでてくるのが印象に残った
Posted by ブクログ
"砂の女"ではなく、あえてこちらを選んでみた。こういった世界観の小説は初めてだ。
形にとらわれない、抽象的な表現がとても多いが、読み進めていくと、安部公房の世界観がだんだんわかってくる。
私にとって読みやすい小説では決してないけれど、取り止めのない考え方に引き込まれて行ったのは確かだ。
Posted by ブクログ
第25回 芥川龍之介賞受賞作
彼の眼に映る現実が奇怪な不条理に変貌し、やがて自身も無機物の壁に変身する物語で、帰属する場所を失くした孤独な人間の実存的体験と、成長する固い壁に閉ざされる空虚な世界と自我の内部が、安部公房特有の寓意や叙事詩的な軽さで表現されている。ある朝、突然自分の名前を喪失してしまった男。以来彼は慣習に塗り固められた現実での存在権を失った。自らの帰属すべき場所を持たぬ彼の眼には、現実が奇怪な不条理の塊とうつる。他人との接触に支障を来たし、マネキン人形やラクダに奇妙な愛情を抱く。そして……。独特の寓意とユーモアで、孤独な人間の実存的体験を描き、その底に価値逆転の方向を探った芥川賞受賞の野心作。