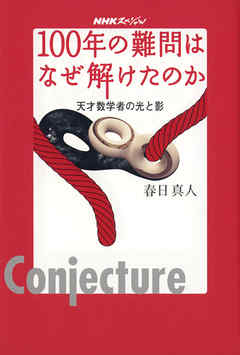感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書は、数学について書かれたものではなく、数学者という特殊な生き物について書かれたものである。したがって、「100の難問(ポアンカレ予想)」についての解説はほとんどなく、これを解いたペレルマンおよび、その関係者について焦点があてられている。 この方法は、決して悪いわけではなく、むしろ、ポアンカレ予想とは「3次元ホモトピー球面は3次元球面に同相」であり、これは・・・などと数学用語を並べたてるよりは良いのかもしれない(数学を学んだこと、特にトポリジーが大好きだった私にとっては若干ものたりないが)。 というわけで、この本は、謎の数学者ペレルマンに肉薄しようとする。しかし、このペレルマン、数学以外に興味がなく、外界との接触も断ち、母親と隠れるように生活している。数学者なら誰しも憧れるフィールズ賞まで拒絶し、数学ミレニアム問題を解いた者に与えらる100万ドルさえも拒否。どこまで、変わっているのか、天才もここまでくれば狂人と区別がつかない。このような人の人物像に肉薄するためには、一緒に過ごしたことのある人か、ペレルマンと同じ志を持っていた人に当たる以外手がなく、実際にそうしている。 そのインタビューの中、ある数学者が、「このような難問に一人で立ち向かうことは、なにより恐ろしいまでの孤独と立ち向かわなければならない。その厳しさが、明るく快活だったペレルマンをあのようにしてしまったのではないか」というようなことを言っていた。その時、10年解けなかった問題に取り組んだ日々のことを髣髴とした。ああ、そうだった。数学とはそういうものだった。覚醒と狂気の狭間にあるその断崖に一人立ち、深淵ともいえるその狂気に引き込まれる恐怖と、引き込まれたい願望との葛藤。これこそが、ペレルマンをしてポアンカレ予想を克服させ、と同時に人格を破壊させた。数学の本質とはかくも厳しいものである。
Posted by ブクログ
ペレリマン博士。ロシアの天才数学者。ポアンカレ予想を証明した。フィールズ賞を受賞したが拒否した。100年の間解かれなかったポアンカレが予想した問題(単連結な三次元閉多様体は三次元球面と同相である)がどうして解かれたかを追った内容。面白かった。
Posted by ブクログ
NHKスペシャルが元である。数学のミレニアム問題にもあげられているポアンカレ予想がついに証明された。一般向けのため数式はもちろんほとんどない。したがって数学者以外にはこの難問がどう難しいのかさえわからないが、この難問に挑んだ数学者の数々のドラマが推理小説並みに面白い。
著者の春日真人氏は東大大学院理学研究科を卒業したディレクターである。おそらく製作者に数学の要素がなければこの人間ドラマにスキャンダラスな面を強調しただけの全く面白くなかったであろうことは想像に硬くない。
Posted by ブクログ
あたし、数学が好きな人フェチかも。
でもこの本は、
数学ができる人には物足りないと思う。
微積がわかんないあたしくらいバカちんで、
数学好きが好きな人くらいが読んだら丁度いいかも。
読み終わった時に、春日真人さんを始め、取材クルーの皆さまに心の中でお礼を申し上げた。
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想を証明した、数学者ペレリマン氏の特集。
NHKスペシャルで放送されたものが書籍化されたものです。
数学と言うより、一人の数学者のドキュメンタリー。
Posted by ブクログ
数学の世界ってこんなのなんだー、って思った。
その世界に生きる人を通して不思議な世界を垣間見た感じ。
こんな考え方、こんな見方があるんだなーって、おもしろかった(^▽^)
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想を解いたベレルマンの、人と周辺について、書簡などを引用して説明している。
ポアンカレ予想を知らない方が、最初に読むのによい本。
なぜ、フィールズ賞を受賞しないかは、「ポアンカレ予想」
証明はどういうものか「ポアンカレ予想を解いた数学者」
を参照するとよいかもしれない。
最初に本書を読み、「ポアンカレ予想」「ポアンカレ予想を解いた数学者」の順に読んでいくと、
人と内容の両方がおぼろげながらでも理解できるかもしれない。
本書では、ポアンカレ予想がロープをかけたときに、表面から離れないように、回収できるかどうかと同じ問題だということを知りました。
また、特異点問題が最終的な証明に役立ったこともしりました。
制御問題で、特異点問題を解いたことがあるので、すごく親近感が沸きました。
Posted by ブクログ
「ポアンカレ予想」という世紀の難問に挑んだ数学者たちの100年におよぶ数々の戦い。
それはまさに人生をかけた死闘でした。
難問を解決したペレルマン博士の天才ぶりもさることながら、100年の間難問に挑んでは散っていった数学者達があってこその解決だったんだね?。
素晴らしい本です!数学嫌いなな人でも面白く読めちゃう!わかりやすいし、面白い!数学のイメージが変わるよ!!
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想を証明した数学者ペレリマンを追ったNHKのドキュメンタリー番組を元に書かれた本。
ポアンカレ予想はフランス人数学者アンリ・ポアンカレが1904年に発表した論文の最後に残した問いかけから生まれた。その問いかけとは「単連結な三次元閉多様体は、三次元球面と同相と言えるか」である。(端的に解説できない為詳細は省略)そして数学の7つの未解決問題、ミレニアム懸賞問題の一つだった。ミレニアム懸賞問題を証明した暁には100万ドルの懸賞金が約束されていた。
2006年、ロシア人数学者グレゴリ・ペレリマンによってポアンカレ予想は証明された。彼には数学界のノーベル賞と名高いフィールズ賞が授与されることとなった。しかしながら、彼は受賞を拒否した。さらに懸賞金の受取も拒んだ。一躍マスコミの注目の的となる中、彼はひたすらに沈黙を続けた。
そしてついに、ペレリマンは数学界ひいては人間社会から消息を眩ました。
【感想】
ポアンカレ予想について易しく知りたくて読みました。一般人向けに噛み砕かれた説明で、おおよそのイメージは掴めたので満足です。しかし言葉での説明には限界があり、数式に触れなければ真の理解はできないのだろうと思います。数学者が見ている世界はどんな面白さに満ち溢れているのか、凡人ながら気になります。
そしてマスメディアなのでしょうがないとは思うけれど、ペレリマンのことはそっとして置いて欲しいと思いました。執拗にコンタクトを取ろうとはしていたけれど、彼の身に立てば迷惑極まりない行為でしょう。彼は信念を持って社会との関わりを絶っているのですから。彼が次に表舞台に姿を現した時、歴史は再び大きく動くのかもしれません。
Posted by ブクログ
Nスペは観たけれどずいぶん前なので忘れている。でもたぶん番組の流れ通りだった気がする。四色問題の解決に、ブラックボックスである計算機の結果を信じてよいのか?という問いかけが、昨今の「AIを信じていいのか」に通ずるものがあると思った。天才サーストン博士が自分の育てられ方を窮屈だと感じていたように、大人の思惑と違う行動をする子に対して大人はどう対処してよいか分からず、自分の考えを規範とするしかなくどうしても押さえつけてしまうことはよくありそう。ポッキリ折れてしまわなければ良いけれど。本書に登場する数学者たちが純粋すぎてなぜか悲しくなる。今もこのような静かで孤独な闘いがどこかで行われているのだろう。でもたぶん本人たちはそれを望んでおり、それで良いのだと思う。
Posted by ブクログ
NHKスペシャルを書籍化した本なので、とても読みやすい。
テレビだったら、さらにわかりやすかったんだろうな。
ポアンカレ予想とそれに挑戦する数学者について、何となく触れることができた。
Posted by ブクログ
2007年に放送されたNHKスペシャルの内容らしいが、番組は観ていない。
本書は番組の内容を取材の様子を交えながら、一冊の本に書き下したものである。フランスの数学者であり、物理学者でもあるアンリ・ポアンカレが提起した超難問「ポアンカレ予想」に関して、これを解決したグリゴリー・ペレリマン博士に迫ろうというドキュメンタリーのような内容だ。
内容は、ポアンカレ予想とはどんな問題かというところから始まり、時間を追ってその難問に挑戦した数学者たちの成果や苦労などが描かれている。数学についての詳細な記述はもちろん出てこないが、専門用語などは注釈にしてわかりやすい解説になっていると思った。
数学の話も、先生方が語るたとえ話をもとに、丁寧な説明でおもしろい話になっていると感じる。ペレリマン博士の具体的な結果については理解するのが難しいが、それでもどんなことをして、そこがすごいのかはなんとなく伝わってきた気がする。
残念ながら、最後の下りではもう一度博士と再会することもなく、賞金の辞退やロシアにこもってしまった理由などは不明のままになったが、「間違いなく何かに挑戦し続けている」という文面が非常に印象に残った。また博士の新しい論文がarXivなどに現れることがあるのかもしれない。
Posted by ブクログ
非常に高潔な数学者が,多数の凡庸な数学者が作り出す社会と絶縁したというのが本当のところなのではないかなと邪推します。瑣末な研究を沢山行って生まれる業績で,学会に幅を利かせる人はどの業界にもいるからねぇ。
*****
彼の怒りは理解できないわけでもないですが。おそらく彼の心の中では,[フィールズ賞を]辞退したほうが気が楽だったのでしょう。(p.119 スメール博士の言葉)
数学の本質とは,世界をどういう視点で見るかということに尽きます。数学的な考え方を学べば,日常はまったく違って見えてきます。文字どおりの『見る』,つまり網膜に映るという意味ではありません。学ぶことによって見えてくるという意味です。(p.146 サーストン博士の言葉)
私は身に沁みて知っています。最初に何かを考えだすとき,そこには孤独がつきものなのです。(p.156 サーストン博士の言葉)
サンクトペテルブルクに戻ったペレリマン博士は,ステクロフ数学研究所に勤務し,何かに取り憑かれたかのように研究に没頭した。学生時代の博士を知る同僚たちは,その変わりように唖然としたという。
「大学院で一緒に勉強していた頃,ペレリマン先輩は明るい普通の若者でした。私たちは一緒にパーティーに参加したり,新年をお祝いしたりしたんです。夏休みには勤労奉仕でコルホーズ(集団農場)にも行きました。他の仲間となんら変わることはなかったんです。
でも,アメリカから戻ってきた彼は,まるで別人でした。ほとんど人と交流しなくなったのです。昔みたいに声をかけることもできない。私たちとお茶を飲んで議論することもなければ,祝日を祝うこともありません。驚きました。以前はあんな人じゃなかったのに」
ペレリマン博士はセミナーなどの共同作業がある日以外,研究所に顔を出さなくなっていった。人付き合いを極力避け,研究に打ち込む日々が続いた。(pp.175-176)
数学でもっとも特別な瞬間は,問題を違った角度から眺めたとき,以前見えていなかったものが突然明確になったと気づく瞬間です。鬱蒼とした森だと思っていたのに,適切な場所に自分が立つと,木が整然と並んでいるのが見えるのです。他の角度から見るとその構造は見えずに,混沌とした木だけが見えます。でも,適切な方向に自分が向くと,突然,この構造が見えます。数学とはこのようなものです。私にとってペレリマンの論文はその連続でした。私は何度も『美しい』と思いました。(p.196 ジョン・モーガン博士の言葉)
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想と、それを解決したペレルマン博士について追ったTVのドキュメンタリの書籍化。TVが元ネタなので、非常にわかりやすい説明がなされている。主題はポアンカレ予想よりもペレルマン博士について。数学者というものを、非常に真剣に理解しようとする姿勢が良い。
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想の解決とそのなぞについてNHKスペシャルでやっていたものを本にしたもの。
ポアンカレ予想の単純に見せかけた複雑な模様をインタビュー形式を交えながら。
数学者ってこんな人がいるんだ、というのを感じられた。
Posted by ブクログ
ペレリマン博士は、きっと、リーマン予想に挑んでいるに違いない!彼の家の周辺では、アメリカ国家安全保障局の諜報員がうろついていることだろう・・・
Posted by ブクログ
数学における最大の難問のひとつポワンカレ予想を証明し、一躍時の人となったものの、栄誉を拒み姿をくらませた天才数学者ペレリマンの実像に迫る、という数学ドキュメンタリー。数学という普通一般人が敬遠しがちな学問分野を扱う上では仕方のないことかもしれないが、周辺情報を盛り込みすぎて(その上それらについての解説は浅く、むしろ消化不良になる)、一番重要であろうペレリマンがこの予想と格闘する数年間の描写がかなり手薄になっていたことはいささか残念だった。とはいうものの、この本全体を通して語られる「問題と対峙する上で、ひとりでストイックに問題のことだけを追及するのか、自分の研究時間を犠牲にしてでも外部と交流をもち、自身の研究分野の底上げ及び発展を目指すか」という二つの態度の紹介は興味深かった(ちなみにペレリマンは前者のやりかた)。また、さまざまな数学者へのインタビューも普通に人生訓として読め、ためになる。
Posted by ブクログ
宇宙空間の「中」にいる人類が、宇宙の外側から見ないと分からないはずの「宇宙の形がどうなっているか」を予測できるなんて、ロマンがありますね!
Posted by ブクログ
難しい数学の話ではなく、ポアンカレ予想とは何か、どのようなアプローチがなされてきたかを示してくれるので、物語を読んでいる感覚。ペレリマン自身よりも、難問に立ち向かって解けなかった数学者の生き方が印象的。というかペレリマンは取材を一切受けてないので、謎のままです。
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想とその証明。
謎とその解明に力を注がずにはおられない人々がたくさん居る。数学の思考や解法が示されるが、技術論というより数学者たちの哲学のように思える。
彼らは、大きな謎が解けて喜ぶのではなく、それを足がかりにして、また次の深淵をのぞき続けるのだろうと思う。
面白いというより、興味深かった。
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想を解き明かしたグレゴリ・ペレリマンの話。
ポアンカレ予想を取り巻く数学者たちの話。
他の何も差し置いて熱中できるものに出会いたいものですね。
あと、ペレリマン博士のような天才に憧れます。
Posted by ブクログ
正直、ミレニアム問題もポアンカレ予想も知らなかった。理工学部の大学生になったということで、スタートラインとしてとっつきやすそうな本書を手に取ってみた。
数学を極めすぎたことによって人生があらぬ方向に行ってしまう。こんなにも難しいことに挑戦する博士たち、人類がまだ見ぬところに到達するために全てを目の前の難問に捧げる博士たち。好きなことにならここまで熱中できるのか。天才だからここまで極めてしまうのか。
そして数学は奥が深い。どんなに世界は変わっても数学は普遍的な態度を取り続ける。そこに数学という学問の魅力があるのかもしれない。
Posted by ブクログ
数学的な記述はほとんどないので、誰でも気楽に読むことができるが、理系の人が読むと少し(だいぶ?)物足りない。
Poincare予想は位相幾何学的な言葉で記載されているので、その主張を理解するだけでもすこし解説が必要であるが、穴が開いていない(単連結な)3次元空間は球体と同位相ということを二次元の例、つまり、平面上で穴が開いていない平面は球体の表面と同位相でしょ、というよくある言葉で置き換えている。
Perelmanの証明は全くといってよいほど記載されていない。
PerelmanがPoincare予想を証明したときに、位相幾何学ではなく微分幾何学のツールを使って証明したようであるが、その時に、位相幾何学者は3回ガッカリしたそうだ。
まずはじめに、自分ではなくPerelmanによってPoincare予想が解かれたことにガッカリし、次にその証明が位相幾何学ではなく微分幾何学を使用して解かれたことにガッカリし、そして最後にその証明が全く理解できなかったことにガッカリした、そうである。
Posted by ブクログ
ポアンカレ予想解読にまつわるドキュメンタリーの書籍化。概略の尻尾くらいはなんとなく分かったような気にさせられるNHKの力量おそるべし。
しかしテレビでやる内容ではないよな。この前のエヌスペもそうだったけど、数学はテレビ向きじゃない。活字じゃないと薄っぺらになり過ぎる。
Posted by ブクログ
急にポアンカレ予想について知りたくなり、2冊購入しました。簡単そうなこちらから読破。
うーん、ペレルマン(本書ではペレリマンになっていました)が出てくるまでは電車乗り過ごすほど引き込まれたのですが、最後がなんだか尻すぼみ感が。テレビ番組をまとめただけあって、概要を知るには最適な本だと思います。