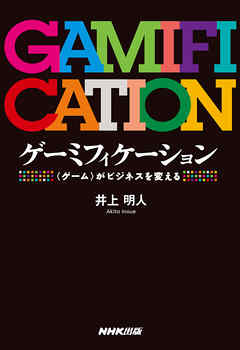感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ゲーミフィケーションの私的草分けになった作品。
「なにかゲームのような耳触りがする、面白そう!」
興味本位から手を伸ばし、ゲーミフィケーションの奥深さを知りました。
身の回りにあるゲームっぽさ、そこから生まれる無意識の関心、購買行動、習慣化。生活の中にある、遊びの要素がいかに私たちに影響を与えるか、教えてくれます。
同時に、この仕組みを理解していないと容易に騙されてしまう。依存の原因にもなりかねません。
知っていれば、つまらない仕事を面白くできる。
知らないと、気づかないうちにハメられているかも。
この分野にどっぷり浸かるきっかけづくりにどうぞ。
Posted by ブクログ
本書はゲーミフィケーションの事例を数多く挙げながら、何がゲーミフィケーションでありそうではないのか議論し、ゲーミフィケーションの意義や定義を述べている。
Posted by ブクログ
以前から持っていたゲーミフィケーションへの漠然とした知的好奇心、プラス、
最近強く感じはじめた仕事のつまらさな(個人的な問題ですけど・・・)を
打破するヒントが欲しくなり、「なんかそれっぽい本ない?」と
友人にリクエストしたら、返ってきたのがこの本。
まさに「それっぽい」分野への入り口として、良書でした。
日常の中の小さなゲームの仕掛けから始まり、スタバの企業戦略や軍事利用のシリアスゲームまで、既に世の中で起きている色々な実事例について紹介されています。
ソーシャルの次はゲームの時代だ、という考えには個人的にとても共感していて、
そう遠くない未来を思うとワクワクします。自分もそんな未来を作る仕事がしたいなぁ・・・。
(本の中では、ゲームの時代におけるマイナスの面の話も出てきます)
巻末で紹介されている他の本も読んでみつつ、いずれまたこの本を読み返してみたいなーと思っています。
最後に最も共感したフレーズを引用
〜〜〜
もしも、会社で働く同僚たちに、五時で退社することを共有してもらえるようなゲームを機能させることができたら?
たとえば、五時になって、子育てをしている同僚を退社させることに失敗したら、全員が「失敗した!」と落胆することができたなら?
〜〜〜
Posted by ブクログ
事例を解説しながら分かり易く説明されている。ゲーミフィケーションをあまり知らない人には、読みやすくて良い本。
もっと深く知りたければ、いろいろ本も紹介されているので、知見を深めていけそうだ。
Posted by ブクログ
贋作は何故か転売回数が多いと言います。人は無意識に判定しているのかも知れません。
自己的な目的だけでゲームの手法を使っても、あざとさを感じ取られてしまい、失敗するだけでしょう。
プレーヤーの共感を誘う、ゲームのベースとなるストーリーが重要ですね。
Posted by ブクログ
ゲーム的なインタラクティブ性を問題解決に応用するのがゲーミフィケーションか。
ビジネスと銘打っているが、実際の応用範囲は限りなく広いことがわかる。
ゲームをプレイした世代が増えてきて理解されやすくなったというのは面白いと思った。
Posted by ブクログ
単なる行動(主にビジネス)にゲーム的な要素を加えることで、自分が行動して欲しい相手に対してその行動をさせる、頻度を上げることができるという考え方をinspireされたように思う。自分の仕事に活かせそうなのでぜひ使ってみたい。
Posted by ブクログ
実例を交えながらゲーミフィケーションについて解説されている。
今まで培われてきたゲームのノウハウを社会やビジネスに適応させることがゲーミフィケーションだと述べられている。
今の社会も結果の可視化や競争によってゲームと言えるかもしれない。しかし,それぞれの立場やゴールが違っているため上手なゲーム設計にはなっていない事が多い。
ゲームは人を惹きつける魔力を持っている。
ゲームの可能性を感じることが出来る本だと感じた。
Posted by ブクログ
ゲーミフィケーションについて、具体的事例を紹介しつつ、分り易く説明されている。
<ゲームのメカニクスを設計する>
・ほどよい挑戦の感覚をつくる仕組み
アンロック/レベルデザイン/難易度の自動調整
・フィードバッグをより強く演出する仕組み
フィードバックを短くする/フィードバックの明示化/錯覚的演出
・フィードバックのバリエーション
緩急効果/音楽・映像のバリエーション追加/イベントの開催
・メカニクスの調整
ズルの応用/ズルの阻止
「ゲームプレイワーキング」
ゲームをしていると思っていたらいつの間にか交通整理をしている。ゲームをしながらお金が手に入る。そういった世界が訪れるかもしれない。
→AIの発達により人間の仕事が減るとか言われているし、将来的には、仕事と遊びの堺が薄いこういった考えが広まるかもしれないと思った。
Posted by ブクログ
「ソーシャルゲーム」のような、それ自体がビジネスとなっているゲームに限らず、「ゲーム」の考え方をより広範囲に応用することによって、対顧客マネジメントや、組織マネジメントにイノベーションを起こすことができると主張する一冊。
著者によれば、「ゲーマー世代」が生産と消費の中核を担う時代になったこと、またテクノロジーの発展により、あらゆるデータが計測可能になったこと、さらにはSNSやスマホの普及により、ゲームに不可欠な「フィードバック」に要する時間が大幅に短縮されたことから、企業の生産活動や顧客の消費活動の全般にわたって、ゲームの要素を継続的に活用することが可能になったという。
一方で、ゲームに関するリスクやその対処についても考察されており、著者の真摯で前向きな思いとともに、本質的にはインセンティブ設計の根本思想がしっかりしていないと、顧客にも社員にも振り向いてもらえないのだということも理解できる。単なるバズワードで片付けられないゲームという概念の奥深さが伝わってくる一冊。
Posted by ブクログ
2011-12年のソシャゲバブルと共ににわかに流行したゲーミフィケーションが題になっているが、内容はソシャゲとはあまり関係なく、継続的に物事を続けてもらうための仕組みとしてのゲームに注目して、その事例を集めて淡々と評論するというもの。「ゲーム」と単発の「遊び」の違いや、受け手に投げ出させないゲームデザインの要所などにも触れながら、誰かに何かをさせる仕組みとしてのゲームの強力さを知ることができた。
Posted by ブクログ
ゲーミフィケーション:ゲームの考え方や仕組みを社会的活動やサービスに利用していくこと。
オバマ大統領の選挙戦略やスターバックス、ディズニー、ソーシャルゲームなど多彩な事例を参照しつつ、丁寧に解説しているので私のようなゲーミフィケーションとは?と思っている人には最適な入門書だと思います。
Posted by ブクログ
よんだ、よかった。
世界的にはゲーミフィケーションの解説書は
マクゴニガルになるのかもしれないが、国内研究者では井上さんのものになるのだろう。よくまとまっているし、語り口もクリア。
学術にもビジネスにも偏ってなくてわかりやすい。
Posted by ブクログ
ゲームとは、テレビゲームとはまた違うもので、勝負や進化があるもの。そのゲームがソーシャルな時代となることで爆発的な飛躍と発展を見せる。今後は付き合い方。筆者も決して傲慢でなく、研究したいことを研究している熱意を感じた。
Posted by ブクログ
この書籍で最も役立っているのは、「外発的動機づけと内発的動機づけ」というコトバ、意味を学べたことですね。
今までぼんやり考え(思うくらいかも)ていたものがこれでハッキリしたというこ
と。
ユーザーを動かすための仕組みとして「外発的動機づけ」とは、商品や賞金という外部から与えてもらうものでの動機づけであり、「内発的動機づけ」とは、自分の感情面で「したい」「しなければならない」という動機づけである。
ゲーミフィケーションという大枠はまだ理解途中ですが、この外と内という2種類の感情、生活者心理のこを学べただけで大満足です。
そのあとにどうすれば成功するかの色々な事例(ランキングについてなど)が掲載されていたりするが、この外と内をしっかり理解•把握して進めないといけない。
脱線した部分でいうと、「マリオ」のゲームとしての素晴らしさ(レベルデザイン)にも感銘を受けた。そんなことを考えて構成されていたのねっと。これはユーザーに無意識な部分なのだけど、ゲームに対する考え方が少し変わった。
Posted by ブクログ
ビジネスやいろいろなものにゲームの要素を取り入れるという話。
この本を書くきっかけは震災後の節電をしながらこれはゲームになると気づいたところから。
冷蔵庫以外のコンセントを全て抜けば何Whとか、#denkimeterと言うタグでツイッター上でつぶやくところからゲームが広がり、iphoneアプリまでできてしまった。
オバマは選挙活動にゲームの要素を取り込んだマイバラクオバマ・ドットコムという選挙支援サイトの中で電話勧誘や戸別訪問をするとサイト内でのランクが上がって行く。RPGで経験値を積むとレベルが上がるのと似た様な設計である。
スターバックスでは紙コップ削減キャンペーンにあるアイデアが使われた。マイカップ持参でポイントを付与するのであればだれでも思いつくところを店に黒板とチョークで来店者がマイカップを持ってくるごとにチェックを入れる。記念すべき10人目はタダというゲームだ。
Facebookは従業員の満足度が非常に高い。その秘密として取り上げられるのがリップルという社内システムで、社内のメール、進捗管理、さらに評価制度にもつながるシステムになっている。インターフェースはfacebookと似ており簡単な連絡はチャットの様なやり取りができる。(そういえば中国のQQもそんな感じらしい)いいねボタンだけでなく特別な際にはサンクスボタンがありこれが評価に直結するらしい。
ゲーム要素を入れれば何でもうまく行くということではないらしい。
敷居を低くし入りやすくすること、ハマる要素をうまく盛り込むことなどいくつか条件はある。
40代前半以下は子供の頃から普通にゲームに慣れ親しんでいるので受け入れられやすくなっているんじゃないかと言ってるがまあわかる気はする。
Posted by ブクログ
「ゲーミフィケーション」ちらほら聞く言葉なので読んでみた。
端的にはゲーム的な要素を使うことで、持続したり楽しむことを促すことのようで、
冒頭では著者の始めた節電ゲームの事例を紹介している。単純に電力メーターを読んでツイートするだけでも、過去との比較やフォロワーとの交流でゲームになるといういい例だ。
オバマ大統領の選挙活動に使用されたSNSも面白い。オバマ大統領と言えばソーシャルの活用とは聞いていたが、具体的に中身を聞いてみるとなるほどと言ったものである。
幾つか要点を紹介してみると
・支援活動の記録が残る
・支援活動を行うことでポイントが貯まり、レベルが上がっていく
・レベルに応じた支援活動を促す(無理させない)
・時差まで考慮して勧誘対象を指名する
・献金記録を使用し、直近に献金した人に頻繁な催促はしない
というふうに、支援者にも勧誘先にも不快感や負担を与えず、参加・継続しやすい仕組みである。単純にソーシャル・ネットワークの活用等というと、いかに情報をばらまくかという方向に全力を注ぎそうなイメージだったが、このシステムは情報の使い所をきちんと考えられている。
SNSではあるものの、「ゲーム的」なエッセンスを引き出していたのだ。
ゲーミフィケーションに必須な要素の一つが「フィードバック」である。
結果の分からない事を続けてもゲーム足り得ない。
そしてフィードバックは遅すぎても行けない。人の欲望は時間とともに衰えていく。
素早く、適切なタイミングでのフィードバックが必要である。
ゲームシステムやソーシャルといった要素はゲームの持続性を強固にする意味では重要だが、必須というわけではない。
計測して数値化することで様々な日常からフィードバックを引き出すことができる。例えば歩数計のようなものは江戸時代頃から存在したらしいが、より簡単で安価になったことで身近になり、ポケットピカチュウのようにゲーム機そのものになったこともあるが、今ではNike+のようにあくまでも歩数計を軸にしながら発信や記録により十分楽しめるものになっている。
また、技術の進歩により機器も安価になり、高速軽量となっている。近年普及しているスマートフォンであれば計測・記録・発信を行うことができ、ソーシャル要素との連携も容易である。
ゲーム化することで日常をより楽しめる面があるのは確かだが、忘れていはいけないことは
・どんなゲームも合わない人間は居る
・どんなゲームも飽きる可能性がある
・モラルを下げるようなマイナス要素もある
・デザインは容易いことではない
・作って終わりではなく、運用して調整は必要
といったところ。
モチベーションを引き出し、発展と幸福のために役立てて欲しいとは思うものの、ただ導入すればいいという事にはならない。
孔子の言葉
”これを知る者は、これを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず”
というのは自分も好きな言葉。
これをゲーミフィケーションと関連付けるのはちょっとやり過ぎな気がするが、
単なる動機を引き出すだけでなく、楽しむことでよりよい効果を期待する考えはゲーミフィケーションの仕組みを問わず大切である。
Posted by ブクログ
ビフォー
ゲーミフィケーションは例えば〇〇を××時までに終わらせるのようなミッションを課すものと捉えていた。本書を読むことで面白いミッションの課し方が学べると思った。
気づき
本書はそういったノウハウ本ではなかった。一方で、スタバのカルマカップなどゲーミフィケーションを取り入れた事例がいくつも紹介されており、気づきを得るヒントになった。また、一般のゲーム設計についても触れられており、ゲーミフィケーションの理論的なものが知れた気がする。
TODO
とはいえ、タイムアタックや日々のタスクをミッションとして課すことは個人のゲーミフィケーションとしては成立していると思うので「今月は何冊本を読み、感想を残す」のようなミッションを作り、生活をメリハリあるものにしていく。
Posted by ブクログ
「ゲームにすればうまくいく」の後に読んだ本。前述の本とくらべて、テレビゲームやコンピューターゲームに関する事例が多く書かれていて、ビジネス向けというよりもゲーム開発者向けに寄った本だった。
Posted by ブクログ
ゲーミフィケーションという概念を知る入門として、ちょうど良かったです。
10年近く前の本なので、最近のゲーミフィケーションに関する&もう少し専門的な本も読みたいとおもいます。
Posted by ブクログ
少し興味のあったゲーミフィケーションについて、いろんな視点から書いてあり、勉強になった。「飽きる」という感情がある限り、ゲーミフィケーションには限界があると思った。本書が書かれてからだいぶ経つが、ゲーミフィケーションはあまりいい形で進歩してないと思う。それよりはIOTみたいなものの方が未来があるような気がする。
Posted by ブクログ
最低限の仕組み(補助線)を入れるだけで、節電もゲームになる。
紙コップを減らすアイディア「カルマカップ」
→キリ番の人は飲み物が無料に。スタンプカード(10杯で1杯無料)は10杯まで我慢しないといけないが、カルマカップはクジを引く感じ。
ストックホルム スピードカメラ宝くじ
→速度を守った人を褒めるシステム
数値として測れるものはゲームにしやすい
仕組みがあるとゲームになる
→ギネス記録 測れるものがあれば何でもゲームになる。ギネス記録の仕組みが無いと、頭でスイカの早割りに挑戦したりしないだろう。
Posted by ブクログ
事例集としてよくまとまっている。p121の「測るテクノロジーのコスト構造が変わった」の章はビッグデータの議論とも重なる部分があり、興味深く、「次の10年はゲームの一年」というのがひどく現実に目の前に迫ってくる。決してゲームだけに適用だけでなく、数多くの業種で考えるべき事項。
Posted by ブクログ
【要約】
・「物語」から「ゲーム」が人々を惹きつける要素になり、その具体的事例が増えてきており、その潮流は今後もしばらく続く。
【ノート】
・確か、「商店街を盛り返すには」というテーマで本を探していたら、これが引っかかってきたような。
・測る技術の進化」「システムからのフィードバックを得る時間が短縮した」「ゲームに抵抗のない世代がオッサン年齢になってきた」のがゲーミフィケーション発展の大きな要素
・ゲーミフィケーションによって人々は自由意志で楽しく参加してくるようになる
・ゲーミフィケーションも、その適用に危うさはある(Amrica's Armyサイトなど)
Posted by ブクログ
単なる流行言葉で終わらせたくないという著者の意欲が感じられるし、実際、多くの可能性を秘めた概念だと思う。あとがきの熱さがいい。
にしてもマリオってあんな計算されたゲームだったのね。知らんかった。
Posted by ブクログ
ゲームの考え方、定義の仕方を色々なものに応用することについて書いている。
実例等も豊富でわかりやすい。
類似の本で一方的なゲーム賛美みたいなものがあったけれど、この本では考えうるデメリット等にも触れていて良い。
Posted by ブクログ
モチベーション維持、自己成長といったことに関連して、
この考え方が使えないかということで。
序盤はとても面白かったが、最後のほうはゲームデザインの話になって
ちょっと面白さが低下。
まとめ:あくまで、現実世界での行動を促進するためにゲーム様のシステムを作ること
実例はおもしろかったが、そこにはまっていくための要素の解説がもう少しほしかった。最後の部分でゲームの構造の解説に落とし込んでしまうよりも、
なぜヒトがはまるかの心理の分析がほしい。
娯楽がヒトを魅了する過程をもっと知りたいと思った。
マイバラクオバマドットコム:支援者が選挙活動にどれだけ貢献したかをポイント化して、ゲームとして楽しんでいるうちに選挙活動を応援するシステム。
しるためのゲームではなく、行動をゲーム化する。
歩数をはかる。測定できれば、それはゲームになりうる。
ソーシャルかによって、スケールはあっという間に。
構造解析など。ゲーム化することで、仕事を楽しんで行う。
それはもはや、仕事ではなくゲーム。
ポイント制は、外発的な動機付けに近い
ゲーミフィケーションは、内発的な動機付けに。
それをうまく引き出すゲームの構築が大事。
ポイント制は、ゲーミフィケーションではない。
(その境目は非常に難しい・ポイント制も、ゲーミフィケーションの一種かと思うが、単にポイントを集めるだけでは、やはり、ゲーム性は低い)
シリアスゲームは、社会問題をゲームに入れる
ゲーミフィケーションは、ゲームを社会のさまざまなところに持ち込むこと
コストは小さい。
スタバのカルマカップ:舞カップを使うのを促進する。
ポイントカードが不要に参加しやすくなる。
でも、総費用は換わらない。むしろカード発行手数料は減る、
ギャンブル感。
ゲーミフィケーションは、補助線を引くこと
生活のいたるところに、ゲームは存在しうる。
ジンガ:リアルワールドで特定のものを買うと、
ゲームのアイテムが手に入る。
フォースクエア、バッジヴィル、スカベンジャー。
リアルワールドの行動が、繁栄されるシステム。
図れるものは改善される。と誰かが言ったが、それと一緒。
図れるものであれば、多くのものはゲームになりうる。
計ることのコスト構造が変われば、ゲームのルールも変わりうる。
(適正スピードで走っているヒトを評価する宝くじとか)
適せtな速度でのフィードバックシステムが必要
フィードバックの速度が上がったのは、
ソーシャルシステム、スマホなどのシステムを含む
流行するためには、システムが認知される必要がある。
(紙の流行と印刷技術の関係のように)
ゲーム世代がある一定数以上になった現代だからこその流行。
ここら辺から、本の内容がゲーミフィケーションではなく、ゲームになりつつある。
関係性の強化に使える。
フィードバックを可視化する! これは大事。
技術の変化
遊びやすさ、説明書がなくても理解ができて、楽しみがわかる。
アンロック
レベルデザイン
Posted by ブクログ
今話題の言葉、"ゲーミフィケーション"についての本。
ゲーミフィケーションとは、ただテレビゲームのようなものを作ることではなく、ゲームで培われてきた概念を実社会に応用して組み込むこと。それにより、社会は大きく効率的、楽しいものに変わるという筆者の切り口。
私はゲームに小さい頃から慣れ親しんでおり、ゲームの概念を世の中に適応することは十分に可能だと考える。また、ゲームというもの自体が、誰にでも受け入れられ、社会も変化しどこでも遊べる時代になってきたからこそゲーミフィケーションは今後定着していく概念になっていくのだなと改めてこの本を通じて思えた。
ゲームはオタクのような特定の人が遊ぶもの、という固定概念を持っている方にはぜひこれを読んでほしい。