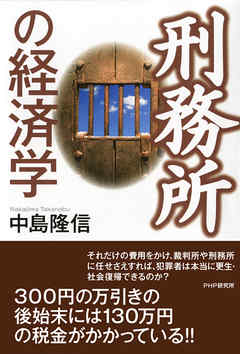感情タグBEST3
Posted by ブクログ
【読書その35】内閣府の村木厚子統括官が、国家賠償金を長崎県雲仙市の社会福祉法人「南高愛隣会」に寄付し、障害を抱える累犯者の社会復帰支援や刑事司法制度の見直しに充てるための基金が創設されることになり、3月10日(土)にそのシンポジウムがあった。そのシンポジウムに参加し、改めて勉強しようと思って手にとった本。著者は、「障害者の経済学」で有名な慶応大学の中島隆信氏。
人生に挫折はつきもの。人は、挫折を繰り返し、それを乗り越え、その都度、自分自身を見直し、人生をやり直していく。
しかし、犯罪を犯した人は、それが一度であっても一旦「前科者」のラベルを貼られると、人生のやり直しをするのは非常に難しくなる。つまり、前科者は、社会から排除されてしまう。
著者は、「前科者」であっても、社会から前科者を排除するのではなく、彼らの居場所を見つけることが可能であり、そうすべきであるという。それを、経済学の「比較優位の原則」から、社会的に失敗(犯罪)を赦すという考え方を論じる。
「比較優位の原則」とは、ある優秀なスーパーマン(絶対優位)が、「あれもこれも」となんでもやってしまうよりも、そのスーパーマンとそうでない人がそれぞれ自分の中で得意な方に特化して(比較優位)、お互いに交換した方が、社会全体の厚生が高まるという考え方。失敗を赦すとは、失敗をしても、やり直しができる仕組みが社会に備わっていることを意味するのだ。
社会で居場所を見つけて生活するため、重要なのは、やはり、仕事である。出所者の雇用に協力的な雇用主は全国8600ほど。その半分が建設業。次に製造業、サービス業と続く。ほとんどが中小企業であり、不況下で厳しい経営状況。自分が上越市で担当した出所者のケースも同様であった。協力雇用主はやはり建設業が中心。なかなか雇用には踏み出せない状況。
また、山本譲司氏の「獄窓記」により世に明らかになった刑務所の福祉施設化。刑務所の中の約3割は福祉的支援が必要と言われる。自立が困難な高齢者あるいは障害を持つ受刑者は、生活に困っては窃盗や詐欺を繰り返す。彼らにとっては塀外は厳しく、塀の中の方が優しいという。そのため、彼らの中には刑務所に戻りたいがために犯罪を犯すものもいるという。
では、社会から前科者を排除するのではなくて、彼らの居場所を見つけるにはどうするればいいのか。最近やっとそのための取組が進んできた。更生保護と福祉の連携である。
高齢や障害により自立が困難な出所者が、退所後、直ちに福祉サービス等につなげ、地域生活に定着できるよう、各都道府県に地域生活定着センターが設置され、センターと保護観察所が協働で支援を進めている。センターは現在47箇所に設置され、今年度中に全ての自治体で設置される予定である。さらに、民間レベルでは上述した長崎県の南高愛隣会で平成21年から社会福祉法人として初めて更生保護施設の運営に乗り出すなど、先進的取組を進めている。
特にこの本を読んで感銘を受けたのは以下の文である。以下引用する。
人々を感動させることは重要。感動は社会を一時的に望ましい方向へ振り向かせる効果がある。しかし、振り向いた先に一定の合理性が存在しなけれ時間の経過と共に再び元の方向に戻る。「人間ドラマ」の効果は局所的。一過性のものでしかない。引用終わり。
やはり、合理的に説明できないと、世の中を変えられない。これを心にとめて、いかに合理的に説明できる能力を磨くか、自己研鑽に努めたい。
Posted by ブクログ
経済学がテーマの本ではあるが、日本における犯罪者への処遇、刑罰や刑務所の内情、そして元・刑務所収容者への更生支援の実情も分かりやすく記載されていて法律を学ぶ人間にも大変勉強になる本である。
少額の窃盗でも繰り返せば懲役刑になる可能性がある。300円のパン1個を何度も盗んだ窃盗犯を刑務所に収監し、半年間懲役刑に就かせ、釈放までにかかる費用は約130万円ほど(本書刊行時、2011年)そのお金は税金から支払われる。
犯罪を犯した人間が社会に与えた損害とその犯罪者を収監し、懲役刑を科して何年も刑務所で生活させるために必要な費用。後者が前者よりも重くなれば刑罰の意味を考えなければならない。しかし日本の司法は犯罪被害者への救済が不足している。そのため傷つけられた被害者の感情は加害者へのより一層の厳罰を求める声へと変化し、結果として費用はさらに増えてしまう。それだけの費用をかけて、出所した人間が本当に更生できているのか。
刑務所に収監された人のうち、知的障がい者や低学歴の人間の数は非常に多い。それらの人々が犯罪に手を染めた原因にはそういった障がいや経歴が関係していることも多いという。
犯罪者が同じ犯罪を二度と犯さないように自分自身を理解し、自尊心を回復し、反省して更生するには刑務所での手厚い支援が必要になる。しかし刑務所は常に手一杯で、刑務官という仕事もインセンティブを得られるような仕事ではなく本人達のモチベーションも保ちにくい。
このような現状に対して、経済学の観点から評価し改善点を提案しつつ、日本の更生支援について様々な活動や機関も紹介されていて、非常に勉強になった。
ニュースで犯罪者が懲役刑になり刑務所に収監されたのを見て、やれやれ一安心だ、もう自分には関係がない。そう考えることも多いだろう。しかし本書にも書かれているが、刑務所はゴミ箱ではない。見たくないものを刑務所に押し込めておけばそれで終わりではないのだ。
10年近く前の本なので、紹介されている内容が現在と少し違うこともあると思われるが、非常に有用な本であると思う。
Posted by ブクログ
no one left behind(SDG)という意味では、確かに、元受刑者の問題は、考えなければいけない問題ですね。integration、難しい。
後半、刑務所の経済学、と言いながら、単なる各論の読み物になってしまってない?!と思いながらつらつら読んでいたのだけど、最後の最後で、経済学で重要な「比較優位」の原則に照らすなら、総合職ばかり雇ってる場合じゃないし、技能別にしてそういう人も入りやすいようにすべき、という論に戻ってきたので、溜飲が下がりました(笑)。
一番の衝撃は、更正制度回りの諸々が、まさかのボランティアの方々や寄付金で賄われてやっと回っているという点。 篤志家すぎる...。
お金...こんだけ赤字出してても、日本、全然足りてないねんなぁ(国家予算)
Posted by ブクログ
世の中の実際の流れを体感してみないと、経済学なんて理解できないです。私も当然、大した勉強をしてこなかったので、全く身についておりません。なので、また一から勉強し直さねばと思います。
本書は「刑務所の経済学」という一見マイナーな話題のものかと思われますが、実は世の中のファクトを経済学的に分析する方法をわかりやすく理解させてくれます。
未だ社会に接する機会がない、経済学部生や商学部生、また大学時代に全く経済学を学んでこなかった人には、どういう風に世の中のファクトを分析していけばよいのか、そのためには経済学の知識が役に立つんだ、ということを気づかされる良書です。
Posted by ブクログ
経済学帝国主義って言葉があるらしい。社会のいろんな分野に経済学が口を出すこと。でもそういう観点からの分析も確かに重要だな。刑事司法だって,正義とかだけじゃなく,経済合理性も無視しちゃいけない。
犯罪の内容とか裁判の経緯とか,判決がどうなったとかで普通人々の関心は終ってしまい,刑務所での処遇とか,出所後のことなど,殆ど注目を集めない。著者はそれを大変憂慮。刑務所の事なかれ主義とか,矯正の実効性とか,保護観察の問題とか,一向に改善しないのは世間が関心を寄せないからでもある。
本書は,経済学者が書いた(主に刑務所の下流の)刑事政策の本。そんなに具体的に経済学を適用しているわけではないけれど,犯罪を犯してしまった人たちや障害者など,社会から排除され,不可視化されている人たちに,居場所が必要なことを,比較優位の原則を援用して訴えている。
実際に刑務所に収容されている人って,高齢者,知的障害者がかなり多くを占めるようだ。凶悪犯罪とかばかり報道されるからって,受刑者がみんな怖い人たちってわけではないんだよね。あたりまえだけど。そういう人たちに,犯罪者の烙印を押して社会から排除するのは,結局社会のためにならない。
ただ,第五章「少年犯罪とサイコパス」の後半で,世の中には極めて冷静で戦略的,自己中心的で良心をもたない先天的脳障害「サイコパス」が結構な割合でいると言っている。こういった人たちへの対処として,その特性を社会に活かすような仕組みが必要だと言うが,いったいどうすればいいのだろう?この部分だけ異色な内容で違和感があった。
Posted by ブクログ
経済学では当たり前の視点で世の中を眺めるといかに不合理なことが多いものか、著者は刑務所をテーマに考察をすすめる。
とくに犯罪し服役したものを出所後も隔離する社会は、実は経済的にも見合わないことを明らかにする。
同じ事象を異なる分野から眺める意義を痛感。
Posted by ブクログ
「お寺の経済学」「大相撲の経済学」などの著者が次に狙うターゲットは「刑務所」だ。いずれもタイトルには「経済学」とあり、幾つかの経済学用語を交え分析したりしているが、基本的には社会学のようなものと思ったほうが良い。
幸いにして此れまで刑務所とは縁がない生活を送る我々であり、犯罪者が罪を償う為に行く場所が刑務所で、テレビで話題になった犯罪ですら有罪が確定するとそれで興味の外になっているが果たして刑務所とはどのような仕組みなのか。
実刑を受け刑務所に収監されるがそこでは出所後の更生をサポートするよりも、如何にして刑期を無事に勤め送り出すかが目的になっている。故に、刑期が長ければ長いほど社会生活に復帰することは困難になる。出所後の再犯もある意味では刑務所の中の衣食住が保証された「安定した生活」を求めてのものとなる。従い今や刑務所も高齢者・障害者の収容施設と化している現実があるようだが、何か間違っては居ないだろうか。
また考えなくてはならないのは、そうした刑務所でのコスト。一人の収容で年間200万円程度のコストがかかっているのだという。仮出所で刑務所を出たは良いが生活費にも事欠き、わずか数百円、数千円の食逃げや窃盗の微罪で、実刑を言い渡される事になるが刑務所でのコストに加え、裁判所・国選弁護士費用等も含めると年間300万円程度になるのは犯罪の程度と比べ経済的にはどうか、という疑問も呈している。
とは言え、より少数の刑務官が低コストで多数の収監者を管理するという実態からすると刑期を務める中で高度な更生教育をすることが出来るのかは極めて疑問であるし、そのインセンティブも働かない。出所後の生活を面倒見る前提としての保護観察士制度も昔のような出所者を迎え入れる地域社会、雇用を生む背景としての経済成長、篤志家が消えた社会ではかなり難しいと言える。
検察官の犯罪など裁判制度をめぐる議論も活発ではあるが、塀の中に落ちた後の受刑者がたどるその後の生活もなかなか奥の深い問題だ。