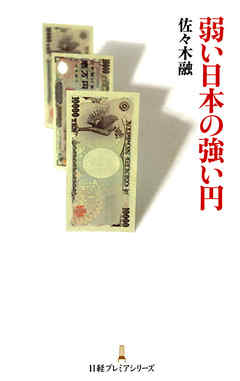感情タグBEST3
Posted by ブクログ
目から鱗の名著。為替相場に関して一般的な解釈や解説を一刀両断し、丁寧な解説がなされる。日頃あまり為替相場に縁がない人でも、十分に理解できるように書かれている。新社会人などにも最適。果たして円高は悪なのか、デフレは悪なのか。タイムリーな話題でもあり、永遠のテーマでもある。
Posted by ブクログ
為替についての本・・・
いくら世界の景気が悪いからって・・・
日本経済のほうがもっと悪いんじゃないの?
低成長で・・・
超低金利・・・
国の借金だってハンパないし・・・
原発だって・・・
少子高齢化も進んで人口も減り始め・・・
政治も混迷を深めるばかり・・・
なのに!
こんな日本なのに、何で円が買われて円高になっているの?
ええ・・・
これ読めばスッキリです・・・
結構分かりやすいし・・・
よく分からないところはすっ飛ばしても内容は理解できる(はず)・・・
為替相場は国力の違いを反映する・・・
経済力の弱い国の通貨は売られる・・・
人口減少がその国の通貨の下落に繋がる・・・
なんてのは間違った先入観です・・・
ええ・・・
その先入観植えつけられてました・・・
別に国力ほとんど関係ないし・・・
それより長期では購買力平価の方が大事だもんね・・・
物価の上げ下げがどうなるかの方が大事・・・
投機筋の動きは基本的にニュートラル・・・
それから・・・
円に買われる理由なんていらないんだよ・・・
経常黒字国なのか赤字国なのか・・・
対外純債権国なのか債務国なのか・・・
資本の出し手の国なのか受け手の国なのか・・・
とかねー
こういう実際を知らないボクとしては非常に面白かった・・・
違和感の解消にもなりました・・・
あー、もっと・・・
早く・・・
ちゃんと・・・
勉強しておけば・・・
うーむ・・・
Posted by ブクログ
為替変動の原理に、完全納得。
一般向けの経済書で、為替変動の原理をここまで解明してわかりやすく書いた本はないのでは。
国力が強いと通貨も強くなる。なのになぜ円高なのか。日本は強いのか。
日本人の多くが抱くそんな疑問を見事に表したタイトル。
しかし読んでみると、国力と通貨の強弱は全く関係ない、とバッサリ。
ニュースで語られる為替変動理由のいい加減さも痛烈に指摘。
要は、通貨と通貨の間でお金がどう流れているかで為替相場は決まる。
つまり、アメリカは経常赤字(貿易赤字)だからドル安になって当たり前。
中長期的には、物価上昇=通貨の価値下落。
つまり、日本は他国よりインフレ率がずっと低かったので、円高になって当たり前。
――完全に納得。
これで考えると、当面は円高だ。
「ジャパンショック」を読んで、円安への揺り戻しを考えていた自分が恥ずかしい、、、
Posted by ブクログ
著者の日銀から外資銀行の経歴から導き出された為替相場の考え方が面白い!
一般的に言われて来たことと、かなり乖離があり混乱する可能性もあるが、著者の考え方も相場の動き方からすると説得力がある
Posted by ブクログ
目からうろこの名著
為替は、貿易収支や所得収支、すなわち資本のフローによって影響されるのであり、一貫して経常収支黒字国である日本の円が経常収支赤字国である米国のドルに対して円高基調が続くのは当然だ。
国力が弱いとか、人口が減るとか、景気が悪いとかいうようなことは、為替に対する影響はない、または逆の影響がある。むしろ日本の景気が悪いと円は安くなるという傾向がある。景気が悪くて、みんながリスクを取らなくなると、海外投資を引き上げるからだ。
Posted by ブクログ
昨年購入して「積ん読」してる間に安倍政権になって円安がガンガン進んじゃって、時期を逸したかな〜と心配しながら読みましたが、全然そんなことなかった。
外国為替のメカニズムについて、たいへん分かりやすく学ぶことができました。
「少子化で国力が衰退する国の通貨が高いのはおかしい」
「こんなに莫大な財政赤字を抱えている国の通貨が買われるわけがない」
「大震災の直後なのに円が買われるのは何故だ?」
巷間云われるこういった言説がナンセンスであることが解説されます。
通貨の相対価値は「国力」などという曖昧な概念で決まるわけでない。
為替市場はあまりに大きな市場で、多様なプレーヤーがそれぞれ異なる動機に基づき売り買いを行っている(これを「ファンダメンタルズ」という)。
特定のプレーヤーが市場を操作することなどできない。
「投機筋」が悪者にされることが多いが、投機的な取引は、売ったら買い戻し買ったら売り戻す必要があるので中期的には市場に対してニュートラルである。
むしろ、貿易収支、証券投資、直接投資などの片道切符のフローによる影響が大きい。
日本や米国は投資資金を豊富に持っているため、円や米ドルは好景気になると外貨投資するために売られて下がり、不景気になると手じまいするために買われて上がる。
円安になると日経平均株価が上がる、と思われているが、株価が上がる好景気だから円安になるという逆の因果もある。
東日本大震災など有事の際に、円が高くなるのも、日本が債権国であるがゆえに、海外投資を控える流れが強まるからである。
さらに日本は貿易黒字国(最近は赤字ですが)であるがために、輸出で稼いだドルを国内で使うために円に変える取引が常にある。
従って、円が「買われる理由」などなくても常に買わているのであり、「売られる理由」があるだけが必要なのである(米ドルはその逆)。
為替レートといえば、ついつい米ドル/円レートばかりに注目が集まるが、他の主要通貨を含めた相対レートを論じなければ意味がない。
例えば、日本の輸出企業にとって今日では米ドル/円レートよりも円/ウォンレートの方が重要である。
…といったところがエッセンスでしょうか。
で、中長期的な為替レートの傾向は、物価上昇率の差により影響を受ける、と解説されます。
著者は、金融緩和によりインフレ率を上げようとするリフレ策には懐疑的な立場です。
その理由として、デフレの方が国民の購買力は高まること、制御できないインフレに陥る副作用があること、そしてそもそもゼロ金利下で量的緩和をしても金利がこれ以上下がらないので円安にはならないこと、を挙げています。
最後の「ゼロ金利下で…」の部分については、完全に外れましたね。
というか量的緩和を実際にする前から円安が進んだわけですが。
「期待」という心理的要因で為替レートが動くメカニズムを捨象していたのか。
このあたりについての著者の見解も聴いてみたいところです。
Posted by ブクログ
人気アナリストによる為替相場の解説書。著者は、長年、日銀やモルガンチェース銀行で為替取引に従事した知識、経験から説得力ある話が展開している。為替市場のアクターをはじめ、為替レートが動くメカニズムが理解できた。
「円という通貨は、投資家のリスク回避志向が高まり、世界的に株価が下落するような時には最も強い通貨となる一方、投資家のリスク選好度が高まり、世界的に株価が上昇するような時には最も弱い通貨となる」p41
「日本の物価上昇率が、他国の物価上昇率を下回り続けるなら円高方向、逆に日本の物価上昇率が、他国の物価上昇率を上回るようになるなら円安方向である」p99
「今のように巨額な財政赤字を抱え、しかもなお増え続けている時でも長期金利が上昇しないのは、日本のインフレ率が低いからである」p105
「日本の輸出企業は円相場がどのような動きをしていても、輸出で稼いだ外貨を売却して円を買わなければならない」p126
「米政府は「強いドルを支持する」と言いながら、穏やかな米ドル下落を実現しており、その意味では米国の為替政策は成功していると言えるであろう」p180
Posted by ブクログ
自分がいかに思い違いをしていたかわかった。本文中で誤解されているということを自分では信じていた。たとえば、為替は国家間の経済の差を反映しているとか、日本の少子化にともなって円安になるなど。実際には為替は二つの通貨の交換レートというだけのもので、このレートは中期的には資本の流れによって、長期的には物価の上昇率の差で決まるとのこと。身近でありながら曖昧な為替というものをわかりやすく知ることができる。
Posted by ブクログ
素人には、若干、難しいというか、筋を追うのに手間がかかる部分がありますが、為替の動きの基本的な原因を知るには、よい本だと思います。
先日読んだ藤巻さんの本は、「とにかく円安に」という論調でしたが、こちらの本では、「現在の円高には、そうなる理由があり、その理由を考えると、今後しばらくは円高基調だろう」ということが、冷静な語り口で説明されています。
この本を読んで、我々は、いかに、物事の一部しか見ていないかを痛感しました。
言われてみれば当たり前でも、多くのことを見過ごしているんですね。
Posted by ブクログ
筆者は、"為替について、間違った情報、浅はかな情報が多いことに危惧し、つとめてわかりやすく書いた本"という。私は1度読んだだけでは、深い理解はできず2度読んだ。それでも全部理解できたかわからないが、基本中の基本の知識がついて、良かったと思う。
・国力、人口の増減は為替に関係ない。シンプルに、その国の通貨で物の売買をするから、為替の取引が発生する
・世界の景気が良いと円安、ドル安へ → もっともお金を持つ国の人(米、日)が、自国通貨を売って株等に投資するから。
・為替は「実質実効レートで考える。(物価上昇率も勘案したレート)
・日本は資金の出し手である。日本にnegativeなことが起こっても、日本から出て行くような海外からの短期的投資が少ないから(東北の大震災直後は株価が下がったがすぐ戻った。対してニュージーランドの震災は戻らなかった)
2011年に発刊されたこの本であるが、2015年の今読んで、興味深いことは、アベノミクスによって、この著者が言うことが実際に起こっているということである。アベノミクスで物価が上がり、円は安くなった。でも賃金は上がらない。資金は目減り。円相場はインフレ次第ということがよくわかる。著者はデフレで何が悪いという姿勢だが、一般のサラリマンもそれに同意する。デフレを悪者扱いするのは、大企業と仲良しの政治家の言葉であることを、今、本当に理解する。
また、少し本題からそれるが、これも面白いなと思ったのが、「ヘッジファンドは案外いい人」ということである。ハゲタカのようなイメージがあるが、著者曰く、できるヘッジファンドというのは、人当たりがよく、情報に貪欲で、コミュニケーション力に長ける・・・
仕事ができる人って、要は人柄、あらゆる職場で共通なんだなあ、と興味深かった。
また、しばらくして、為替、経済状況が変化した折に読み返してみたい。その時は、日本の経済はどうんっているんだろう。
Posted by ブクログ
2011年、円が70円台後半で推移していた頃に書かれた一冊。為替ストラテジストの立場から、為替と国力が相関するといった為替に関する様々な誤解を説明する。
ドルと円だけみていても為替相場はわからず、複数の通貨の動きを見る必要があることや、為替取引は巨大な市場であり、投機的な動きの他に、純粋にその通貨での支払いや利益確定が必要だからという企業などの動きも反映される。そのため、国による市場介入は無意味というような点は、目から鱗だった。
円安がよいか円高がよいかという論点は、まさに現在のアベノミクスを巡ってなされている議論の中心。議論はわかれるところだろうが、本書のような為替の専門家の意見はもっと紹介されるべきだろう。
Posted by ブクログ
とてもおもしろい本でした
為替についてわかりやすく書かれています
為替は難しくてよくわからないというイメージが少し変わりました
円高は円が高くなっているのか、ドルが安くなっているのかで違う
円ドル相場ではなく円ウォン相場のほうが景気に影響している
Posted by ブクログ
人気アナリストが書いた為替相場の本。なぜ円高になるのか、なぜ東日本大震災で円は買われたのか、理由がよくわかる『気がする』本。
金融系の本としては素人にも分かりやすくて良書です。
Posted by ブクログ
為替相場は国力を現すものではなく交換レートであることを改めて認識した。
「(為替相場は)中長期的には主に貿易や資本のフローがどちらに向かって流れているかで決まり、長期的には主に物価の上昇率の差で決まる。であるから、本当に円高傾向を止めたいのであれば、第1にデフレを止めること、第2に日本の投資家・企業がリスクを積極的に取れるような環境をつくり、対外投資を進めやすくすることである。」(p.236)という著者は無理やりインフレを起こすくらいならデフレの方がマシとのことで「(問題は)活発に消費が行えない消費者と、リスクを取って事業を拡大しようとしない企業のほうにある。そしてそのような状況をつくっているのは国の構造的・制度的・税制的な問題である。金融政策で解決できる問題ではないのだ。」という。
そうだとすると世間は日銀総裁後任人事で騒がしいが実は今後の景気回復には余り効果がないのかもしれないと思った。
Posted by ブクログ
為替を見るのに重要なのは3点
その国が資金の出してなのか資金の受けてなのかという点
その国が経常黒字国から経常赤字国かという点
その国が債権国か債務国かという点
Posted by ブクログ
為替相場について、平易に解説。
為替相場は通貨と通貨の交換レートであり、国力の違い、経済力の違い、人口の増減などで動くものでない。そして、介入によっても、円安誘導などできない。と解説。
円高の本当の原因に目を向け、低インフレ傾向が続く状態を何とか変えることや、ゼロ金利や量的緩和政策のような異常な金融政策を続ければ通貨の信認が失われ悪性のインフレが起きると警告を発している。
大変興味深く読むことができ、分かりやすかった。
Posted by ブクログ
円相場の状況をみながら、為替相場の動きを解説する。相場の変動は短期、中期、長期的な視点で異なる。金利、資本フローや物価が主な要因。ドル円だけでなくクロス円を見渡すことで全体を掴みながら、刻々と変わる経済構造に従った対応が必要。
Posted by ブクログ
為替相場に関する思い込みを、ラディカルな視点で見直すことで、そうした思い込みに振り回されないスタンスのとり方を教えてくれる。特に、為替相場にかかわるプレイヤーが他の金融市場に比べていかに多様であるか。また、ドル/円相場だけでなく、ユーロ・豪ドル・ウォン等々とドルや円の関係も見なければ、各通貨の価値の変化はわからない。といった指摘は、言われてみれば当然だが、素人にとっては目から鱗だった。あと、現在の日本経済に対する処方箋として最後にあげていた、稼いだ外貨を国内の内需拡大に活かすべき、という指摘が、以前読んだ藻谷 浩介『デフレの正体 経済は「人口の波」で動く』 と同じで、印象に残った。
Posted by ブクログ
マスコミで語られる円が強いとか弱いとか、買われてるとか売られているとか、それが「どの通貨に対して」という視点が抜けているという主張はもっと広まってよい。通貨の強さが何で決まりそれがどういう意味を持つのかという、知っているようで知らない根本的な知識を教えてくれる名著。
Posted by ブクログ
良書。
最近の為替レートの推移がよく理解できました。
Booklog評価が高いことからも、理解の容易さが分かりますね。
1章 円高と円安ーその本質を理解する
為替相場では、どの通貨を先に持ってくるか決まっている。
ユーロ→ポンド→豪ドル→NZドル→米ドル
<クロス円の動き>
①02年~04年のITバブル回復期の各通貨に対する円相場変動率。
→USD/JPYでみると、20%USD安だが、JPYは強かったわけではない。
AUD+19
EUR+18
CAD+3
JPY 0
USD-22
②08年~8-12月の米金融危機後
→USD/円でみると-20%安だが、AUD/USDでみると17%USD高となる。決してUSDが弱かったわけではない。
JPY 0
USD -20
EUR -23
CAD -30
AUD -35
すなわち、相場を理解するには、クロス円の動きの理解が必要。
①は、株価上昇時の動きと整合。資金が豊富にある国が積極的に自国通貨を売る。また、金利が低いので円キャリー取引のような取引が発生する。
②は、株価下落時の動きと整合している。日本は常に経常黒字なので、円売りが行われる。
日本の財政赤字とレート推移の関連は高くない。
日本は、海外から流入している投資資金が少ない。
Posted by ブクログ
投機化し、実態とかけ離れているといわれる為替市場。
しかし、ドルを売る円を買うという実需が微妙に相場のキーになっている。
インフレ率が大きな流れを作る。
為替介入は見透かされ、注目されるがために逆効果の結果になってしまう。
Posted by ブクログ
資産運用する上で、為替相場の動きは避けて通れない。
これは2014年末に読んだ2011年出版の元日銀行員のアナリストの為替相場、特にドル円相場の動きの要因を持論を交えて解説した書である。
まずは、整理のために要約。
通貨の強弱は国力ではなく、通貨のフローの結果でしかなく、またその相関は2国間の金利差、特に2年物の国債金利との相関が強く、長期的な動向を見れば購買力平価との乖離を解消する方向に向かうといったもの。
また日本は経常収支が黒字(執筆時)であり、今後も、貿易収支が赤字になっても、それが所得収支の黒字を上回って、経常収支が赤字になることは当面想定されないことから、何もなくても円は買われ続け円高方向に向かうが(円高に理由はいらない)、景気が良くなれば、国内投資家の国内債券等の安全資産への投資から、国外の株式や債券のリスク資産への投資に移っていくことで円が売られ円安になる。
通貨の強弱をみる際は、ドル、円、ユーロ、豪ドル等の多通貨間の強弱関係が実質であって、ドル円の関係だけで円安円高と認識してはならない。
おおよそ、一般的な解説であるけれど、何点かは注意が必要だ。
購買力平価は、基準とする年をいつにするかによって、その乖離は大きく違ってくるし、あくまで一物一価が成り立つ世界での話であるので、実際に参考とする場合は相対購買力平価を用いる必要がある。
また金利差との相関は、分析期間をどう取るかで相関有無が違う。ここ10年弱は相関があっても、それ以上の期間でみると相関関係が変わる。2年物と10年物で分析期間が違うのはそれを隠しているように思える。結局はトレンドでしかない。
ただ、これらいくつかに注意すれば、為替の動向を理解する上で良書だと思う。
Posted by ブクログ
為替市場をはじめとする金融市場の動きは複雑で予測し難く、理解しにくいものであると思っており、その印象は変わらない。
しかし、知っておいて損のないトレンドや事実は多くあるように思える。
その、いくつかが本書の中から得られた。
第一は、日本とアメリカの相違点と共通点である。
*相違点
①日本は世界第二位の経常黒字国
アメリカは世界最大の経常赤字国
②日本は世界最大の純債権国
アメリカは世界最大の純債務国
*共通点
①共に比較的低金利である
②金融債券市場が巨大で、資金調達が用意
第二に、こうした共通点から、日本とアメリカの為替市場には同じトレンドがあることである。
それは「世界的に好景気なときには円・ドルが売られて盛んに投資されるため円安・ドル安になり、世界的にリスク回避の傾向が強まると円・ドルが買い戻され円高・ドル高になる」ということである。
第三に、上記の相違点により、共通のトレンドを持ちながらドル/円市場への影響の程度が異なる点である。それは日本が経常黒字による恒常的な円買いがあるのに対し、アメリカは経常赤字による恒常的なドル売りがあるため、長期的に円高/ドル安のトレンドにあることである。
第四は、こうしたトレンドが変化する要因としては、日本・アメリカの物価水準と金利の変化があるということである。
第五は、為替市場においては今後、ドル/円相場の変化よりも円/ウォン相場の方が、日本の製造業に与える影響が強くなるということ。
第六に、介入による効果はほぼ無く、国家としてのリスクが大きいということ。特に100兆円を超える巨大な外国為替資金特別会計が抱える巨額の金利リスクと為替リスクは、日本の財政上、非常に危惧すべきものである。
ドル安/円高が進めば含み損は増大し続け、逆に日本国内の金利上昇が起きれば外貨準備は赤字を垂れ流し続けることになる。
また、100兆円を超える外貨の運用は実質不可能で、コントロール出来なくなっているのが現状である。一方で、不自然な円買いを行えば、市場に外貨準備の限界を見透かされ、逆に暴落を招く危険がある。
このように膨張した外国為替資金特別会計の扱いは、日本の財政上危惧すべき大問題の一つである。
以上が、本書を読み改めて確認または新たに学んだ内容である。
Posted by ブクログ
為替をやる人なら、読むべき。
この本読んでたら過去の負け分の何割かは防げていたはず。
私のようなパンピーでも驚くほど理解が進む。
円が上がり、ドルが下がる。
円高ドル安と言うが、
円高なのか?ドル安なのか?
例えば
1ユーロ100円が90円になった。
1ドル80円が70円になった。
ユーロから見てもドルから見ても円が上がっているので、この場合円高だと言えそうだ。
では、
1ユーロ100円のまま動きがない。
1ドル80円が70円になった。
この場合は?
例えばユーロドル相場が
1ユーロ1.3ドルが1.5ドルになっていたとすると、
ドルは円に対してもユーロに対しても下がっている。
これはドル安と言えそうだ。
この辺りは簡単。確かにそうだし、実際ほとんどの人はこの感覚を持って見ているはず。
Posted by ブクログ
セミナー
本も読んだ。辛うじて冒頭部の為替はどう見るかのところと、あとは斜め読み。
どの通貨を先にもってくるかが決まっているって、初めて知った。
クロス円の動きがキーになる。一定期間の各通貨の対円相場の変動率を積み木のように積み上げて分析するとよい。
日本の景気がよくなると、円相場は円安に動く。
インフレ率が肝
日本の企業収益にとって米ドル/円相場の下落は既にネガティブではなくなっているが、円安が企業収益にプラスに働くことは事実である。ただし、そのは対米ドルでの円安ではなく、米ドル以外の通貨に対する円安が必要となる
韓国ウォンに対する円安は企業収益に大きなメリットがある
円高を使って海外に行くべし、は、榊原さんと同じ。