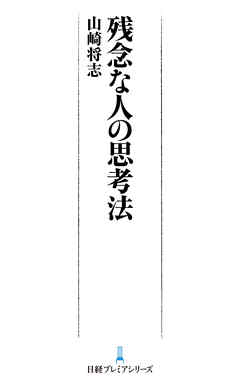感情タグBEST3
Posted by ブクログ
書類選考では、送り手は何者でこれまでどんなことをやってきたか。会社のどの部分に興味を持ったか、採用広告のどこに魅力を感じて応募してきたのか。こういうポジションがあったら、もしかしたら役に立てるかもしれないと、当人はどう認識しているか。
仕事に自分を合わせる…!
Posted by ブクログ
『2分でわかる!ビジネス名著100冊のエッセンス』水野俊哉 著
に紹介されていて、
居ても立っても居られず読みました。
具体例が出るたびに、
生保営業のわたしも
工場勤務の夫も
「あーー!そうなんだよ、
わたし(俺)も残念な人なんだよ!」
と激しく同意しながら読みました。
"残念な人" は表面ばかりに目が行き、
"プライオリティ思考"に欠ける
というのがまとめかと思います。
安宅和人さんがいうところの「イシュー」と
似ているかもしれません。
(同じコンサル業界の方ですし)
相手の立場を汲みながら考えること
自分のゴールがなにかを考えること
それから
「ちゃんと考える」って何なの?
というところにも気づきがありました。
社会人ならば弁えておきたい
マインドセットがたくさんあります。
Posted by ブクログ
仕事の成果=プライオリティ×能力×ヤル気
なんですよね
結局プライオリティの正しさがクローズアップされますが実は能力とヤル気が十分にないと仕事の成果は現れないんですよね。
能力とヤル気があるのを前提にしてプライオリティの優先順位を正しくつけるためには全体を見る必要があります。
ある程度俯瞰的に見ないと優先順位はつけれないので。
読んでて再確認をたくさんできる本でした。
Posted by ブクログ
残念なビジネスマンの思考法というより、それに対するイケてる思考法の紹介のほうが印象に残りました。
この本を読むのは3回目なのですが、毎回アウディのサービス話は感動します。
ただ、筆者が経験した一つ一つのエピソードや学びは面白いのですが、なぜ「一流は割り算で考える」という章のタイトルにつながるのかよくわかりませんでした。
採用面接で面接者がみるべきパフォーマンスの高い人の見分け方は参考になった(面接される側としても)
Posted by ブクログ
自分も「残念な人」だっとと今更ながら自覚させられた。
・残念な人=前提条件が既に間違っている人。自分かも。勘違いして走り出す。
・低価格サービスだからこそできること。へぇー、確かに自分がそのサービスを体感できるから、いいところも悪いところもわかる。
・注意するだけでなく、伝票などにチェックボックスを付けて確認させる。いい方法だ。
・市場を売上だけで捉えない。シェアとか市場の大きさを意識する。
・事業計画を前年比で考えない。シェアで考える。今まで本当に間違えてきた。会社指導しているとき、シェアを意識してきたのは一時だったような気がする。
・大量販売、低価格の大手に商店街が潰されたのではない。魅力がないだけ。
・プロのコンサルタントとは、人ができないことをやれる人、多くの人ができることをとてつもないレベルで実行する人。
・その時期、その場所でプライオリティをどうつけるか。プライオリティは時期、場所で変わる。
Posted by ブクログ
日経新聞広告のタイトルに触発され、購入。文章は読みやすく、興味深いことも書かれていたが、1冊のまとまりとしては惜しいところ。
全体にマーケティング系のコンサルタントを経験してきた著者だけに、マーケティング中心の話が多い。
あと、売れるセールスマンと売れないセールスマンの違いとか。
恐らく著者は世の中のビジネス本を多読しているようなので、本の後半は特に何かの成功本で読んだことのある内容が多かった。意図せずして書いたのだろうが、まったく新しい考え方、というのはみんな欲しがってるけど、難しいことなのだろう。
著者の言いたかったことは「今のやり方がおかしい、工夫すればよくなることを気づくことが大事」と「気が付いたことを放置せず、行動におこすことが大事」かな?
SMARTの法則
Specific(具体的である)
Measurable(測定可能である)
Agreed(納得している)
Realistic(実現可能である)
Timely(今やるべきことである、または期限がある)
ハーズバーグの2要因論
・「好き」の反対は「無関心」
・「不満足」の反対は「不満足が存在しないこと」
※著者のサイン本だった
Posted by ブクログ
残念な人は「もったいない人」
プライオリティが間違っている。前提条件が間違っている。
プライオリティの正否、適否を考えないひと。
目次に「本書の構成」が書かれており、章ごとの主旨が分かりやすくなってます。
プライオリティ、前提条件を常に考えることが重要。
自分は残念な人になってないか、確認するためによい本です。
Posted by ブクログ
残念な人は作られる。というのは同意出来る。
オペレーターになってしまうとその仕事の背景にある意味が分からなくなる。
学習、試行錯誤の機会が与えられないからだ。
二流は掛け算で考え、一流は割り算で考えると言われる。
二流は積み上げ式で考えるが、一流はセオリーを知っているから
全体から割り戻したり、計画から逆算する。
Posted by ブクログ
残念な人の思考について具体的エピソードを交えつつ紹介し、さらにどうすれば残念な人にならないかを指南しています。当たり前っちゃ当たり前の事を書いていますが、時々『おっ!』と思わせるような事があり、一読の価値はあります。
相手の思考や前提条件を明確にしなければ仕事はスムーズに進まないのは当然だし、だからそれらを改善すれば残念な人にならないのだと言いますけど、そもそも残念な人の思考は出来る人とは違っていて、そう簡単には改善できませんし、所謂『空気を読む』といった行動や観察力はなかなかマニュアル化しづらいものです。『残念な人の思考法』と『出来る人の思考法』を対比してあるだけで、具体的に思考法を変えるにはどうすれば良いかが書かれていないのがちょっと残念です。
……といっても、書きようがないですが(笑)
集中力の高い人は仕事が出来る、と後半にありました。僕は、俯瞰的視野をもってスケジューリングやマネージングできるのは分散力だと思います。で、結局のところ、集中力があって分散力もある人が出来る人であって、どっちかしかない人は残念な人になっちゃうんじゃないかな~なんて思います。
僕の評価はA-にします。
Posted by ブクログ
残念な人というよりも、残念でない人の思考法とはという視点で読みました。
この本の主張として、自分は”システム思考”の重要性をあらためて感じました。
全体像をつかんで(心意気として)、結論先出しによる逆算思考。
著者は、”割り算”と呼んでいます。
他に、
■PREP法
P:Point 結論
R:Reason 理由
E:Example 具体例
P:Point 結論
いわゆるコミュニケーションアイテムとして、相手への伝え方
■SMARTの法則
Specific 具体的
Measurable 測定可能
Agreed 納得
Realistic 実現可能
Timely タイミング(優先順位、納期)
マインド(意識)はなかなか改善しない。 まずは行動志向での改善を。
本書では、ハーズバーグの二要因論の一つである”衛生要因”の解説があり、
”トイレ”の例えで説明されていました。
公衆トイレに入り、汚いと不満であるが、綺麗だとしてもそれは当たり前であると感じる。
今まで組織論の学習で 自分も理解に苦しんでいましたが、やっと理解できました!!
Posted by ブクログ
微妙に納得できない記述もないではないが,概ね著者の意見に賛同.
自分にも,元同僚にも,元後輩にもあてはまるところが多々.
実例もリアル.
さて努力して改善できるか・・・ それが問題.
Posted by ブクログ
「段取り」と「相手の視点」を考慮したプライオリティ設定をすることにより、アウトプットの質を高められることを、様々な観点から、また具体的事象の深堀によって示した本といえる。
Posted by ブクログ
ふむふむとうなずきながら読んだ。
・前提を間違えてる人は、能力があってもやる気があっても成果がでない。
・営業には、顧客を操縦するフレームワークが必要。
SMARTの法則
・specific
・measurable
・agreed
・realistic
・timely
・人間には二種類の欲求があり、苦痛を避けようという動物的な欲求(衛生要因)と、心理的に成長しようという人間的な欲求(動機づけ要因)がある。仕事に対して満足を感じるのは、後者が満たされた時である。
・職場は出会いに最適な場所、そして最も恋愛が難しい場所。
Posted by ブクログ
残念な人にならないためには…
プライオリティの考え方(自分は何を優先するのか)
仕事は塗り絵(営業しているので枠を始めに決め、中は後から塗っていくは分かりやすかった)
自分のスキルを上げるために精進し、どの会社、どの仕事でも出来る能力の成長をしていく。
Posted by ブクログ
主観による内容が大きく、鵜呑みにするのもナンセンス。愚痴っぽい印象で★2つ…と思ったが、示唆に富む例え話もあり★3つ。
プライオリティ、優先順位付を大切に。本当に大切なことは?やりたいことは?という問いかけは、スナフキンにも通じる。
また、プライオリティは状況により変動する。ただ、状況が変わっても不変なものもある。例えば、対人業務は優先度が高い。個人業務は低くしても影響は出にくい。
プライオリティを考えるうえで、プロダクトライフサイクルマネジメント、PLMは役立つ。導入期、成長期、成熟期、衰退期間と、どのタイミングなら、何を重視すべきか変動する。
貯金が1億円あったらやらないことは、やらなくていいことである…確かに。この考え方は、やりたいことが明確になる。少額の株の短期売買なんかもやらなくなりそうだが、長期投資はどうだろうか?
安心して仕事を任せられる人は、「期限内」に「期待したもの」を出してくる。自分はそれができているか?「期待されているもの」は何か?仕事には正解がないので、進めながら確認しなければならない。
上司とは、人として上なのではなくただの役割でしかない。その役割を全うできているか?
採用面接にあたり、スキルの有無を確認するのはナンセンス。過去の事実を聞き、能力や適性を炙り出していく。
ストーリーのない資格取得に価値はない。
「本当にワシのためにがんばろう、と思ってもらわないといけない。だから、ワシも本当にそいつのためにがんばろう、と思って仕事をお願いするんだよ」
意識改革は効果測定てきないので意味がない。
エンドユーザーになるな、非エンドユーザーになれ。
Posted by ブクログ
仕事上のプライオリティや、大状況が把握できていないために、まじめに働いても結果がともなわない「残念な人」にならないためのヒントを提示している本です。
具体的な例にそくして説明がされているので、それぞれの読者が仕事のなかで役に立つ部分を見つけ出すこともできそうです。また、自分の仕事に直接関係がないという読者でも、自分の仕事の姿勢を見なおすための視点をあたえてくれそうな内容だと感じました。
Posted by ブクログ
私は読書といえば小説しか読まないし、
実用書があまり好きではありません。
この本もやむを得ずという感じで読むことになったのですが、
付箋を貼りまくることになりました。
まず、残念な人という言葉にドキッとしました。それで買いました。
かなり分かりやすく実体験を含めて書いてあるので、
さらさらと読めます。
当たり前のことしか書いていないように思うかもしれませんが、
実例があるので砕いて理解でき、
実践しやすいのではないかと思いました。
普段こういう本を読まない人にも読みやすいと思います。
Posted by ブクログ
本のタイトル、章・節の表題はキャッチーだが、内容的にはそれほど刺激的ではない。仕事は一生懸命やればよいというものではなく、よく考えて、本質を見抜き、効率的にやりましょうという話。
ただ目の前に積まれた仕事を粛々とこなしていくだけでは成果は上がりにくい。全体像と本質を捉え、効率的に進めていかないと「残念な人」になってしまう。「残念な人」とそうでない人とでは、やっていることはほとんど同じに見えても、その裏にある意図によって意味が全然違ってくる。それが差になる。ということを著者の経験を交えて、具体例を挙げてわかりやすく説明している。
タイトルと内容は一致しているとは言い難いが、自分が「残念な人」にならないための再確認には良い本かも。
Posted by ブクログ
残念な人の思考法というよりも、うまく事を運ぶための、小さなテクニックがちりばめられた本。
小さなテクニックのうちのいくつかは、かなり参考になった。
Posted by ブクログ
・低価格だからこそ商品やサービスのレベルを上げられるチャンスがある(何度も客として試せるから。一泊5万のホテルは従業員でも泊まれない)
・拙い事業計画は前年実績に伸び率を掛け合わせて作られ、優れた事業計画は市場に対するシェアをベースに立てられる
・「わかりました。で、私に何をしてほしいのですか?」
→行動を促す
・高いパフォーマンス
?具体的である
?過去形で話をしている
?後付ではない
?後悔やポリシーではなく実際の行動
?他人と関わる部分はその会話の詳細まで覚えている
Posted by ブクログ
書いてあることはよくある啓発関係のビジネス書。要は会社に頼らず自分の能力を高めることが必要ということ。ゴールを明確にし、全体像を組み立てる”塗り絵”を例にしたくだりはわかりやすい。
Posted by ブクログ
なんだかあれこれ書いてあって言いたいことがぼけているように感じてしまう。本の厚さの割に読むのに手間取った。著者の仕事がビジネスコンサルタントだからと言われればそれまでなのだけれど、この本のターゲットにしている読者層はある程度キャリアを積んで転職を考えているような人達なのだろう。タイトルから『残念な人』はなぜそうなのか原因を解き明かすような内容かと勝手に思っていたのもあり、私には向かない本だった。
Posted by ブクログ
この著者の本は結構読んでいるが、少し飽きてきた。ただ年間粗利一億円稼ぐ営業マンの話が参考になった。
実践する塗り絵的仕事術
1.商品のターゲット顧客リストと、厚手のB5用紙を用意
2.顧客リストにかたっぱしから架電し、買う可能性がある客がいるかどうか探る。
3.見込みありの客に関する情報をB5用紙に記入
4.相手のコメントに応じ次回電話する曜日ごとにB5用紙を分類
5.その曜日に該当するB5用紙の束を取り出して、その客だけに電話を入れる
Posted by ブクログ
仕事で成功するためのプライオリティーのつけ方を教えてくれる本。
具体的な例を出して、優先順位のつけ方、目の付け所を丁寧に書かれている。
意識は変えなくてもいいという考え方もあるんだということを学べてよかった。
Posted by ブクログ
残念な人は、前提条件で間違えている。ということにつきるだろう。特に、目的の理解、優先順位、効率化、あたりをちゃんと考えて行動することが基本。ただそれは、経験しながら身につけていくことでもあるので、みんな最初は残念な人なのだと思う。
Posted by ブクログ
プライオリティ思考。
ボトルネックは何か?
相手がイライラしない報告のしかた=PREP法。
Point=結論
Reason=理由
Example=具体例
Point=結論繰り返し。
相手に求めること=理解、意見、「行動」
ゴールが見えないとイライラする。
納期を明確に言う。
「考え方と前提条件」を共有する。上司視点で。
成功の元は成功。
やりたいことはやりたくないことから見えてくる。
Posted by ブクログ
売れる営業はどんな仕事の仕方をしているのだろうか。
「何の絵を描くのかを明確にする」
市場を知るということである。市場の大きさ、カタチ、複雑さなども調べる。まずは輪郭をはっきりさせることであり、それは描かない部分との境目をはっきりさせることでもある。つまり、それは、対象としない市場を明確にすることと同義である。
「パーツの形と色を知る」
いわゆるセグメンテーションの問題である。一口にスーパーマーケットという市場を狙うといっても、立地、扱っている商品、規模によって、いくつものセグメンテーションに分類することができる。
「どこをどう塗ればそれらしく見えるか考える」
営業では、こちらがイメージした顧客イメージに最も近い顧客層セグメントに対して自分の商品が刺さるかどうかを確かめる。つまり、どのセグメントから攻めれば最も効果的なのか、ツボを見つけることである。
「枠を塗る」
テストマーケティングやテストセールスによって、セグメントごとの成功パターンを事前につかんでおくと後が楽。
「中身を塗る」
セグメントごとの成功パターンに従い、淡々と営業をかけていく。
【年間粗利一億円の営業マンの塗り絵術】
①その商品のターゲット顧客リストと、厚手のB5用紙を用意する。
②顧客リストに片端から連絡する。
目的は買う可能性のある客かどうかを探ること。一回目の電話では、決して売り込まない。
③一回目の電話で「見込みアリ」の客に関する情報をB5用紙に記入する。
顧客の業界に関する新聞の切り抜きなども、電話の際の話題のために添付する。重要なのは「来週電話して」「担当者が木曜に出張から帰る」といった、相手のコメントを記入することである。
④相手のコメントに応じて、次回電話する曜日別にB5用紙を分類る。
⑤月曜なら月曜の分、火曜なら火曜の分というふうに、その曜日に該当するB5用紙の束を取り出して、その客だけに電話する。
この方法によって、毎週末には翌週の仕事のスケジュールが明確になる。
賢いやつだと思われる話し方。論理的に、明晰に話す。「PREP法」。
PREP法とは、結論を示し(Point)、理由を述べ(Reason)、具体例を述べ相手を納得へ導き(Example)、再度結論を示す(Point)
「この問題は明日までに解決する必要があります。(P)なぜなら、明日を逃すと関連する他のプロジェクトの遅延をひきおこしかねないからです。(R)Aプロジェクトが遅れると○○という問題が発生し、Bに悪影響を与えると△△にダメージを与えます。(E)だからこの問題は明日までに解決しないといけません。(P)」
加えて、相手のアクションを明確にすることも忘れてはならない。仕事においては「行動してもらう」ことをゴールに置かねばならない。
「ついては、私はこれから述べる三つのことを早急にやりたいが、了解してもらえますか。さらに、あなたには◇◇をしていただきたいのですが、可能ですか」
「仕事が速い」と思ってもらうことも大事なことである。報告書や企画書などの提出を求められたら、まずは、目的やその使われ方、アウトプットのイメージなどを確認する。次に、受けたら必ず納期を伝える。たとえ最後までできていなかったとしても、約束の時間に連絡して、どこまでできていて、残りはどうすればいつ完成するかを伝える。
キーパーソンの合意なくして次に進めない場合は、悩んでいても意味がない。多少強引にでも接触を試み、承認してもらう必要がある。
異なる部署や顧客企業の担当者の元に出向いて人脈を広げ、時には真剣に語り合う機会を数多く持つべきだ。多少強引なくらいに接触を持つ。