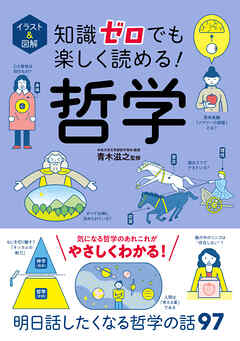感情タグBEST3
Posted by ブクログ
哲学に興味があったものの全く勉強したことなく
本当に0→1に独学で勉強したい人にオススメです。
イラスト付きなので理解しやすいですし
沢山の人物が出てきますが何となく聞いた事あるけどよくわかんないって人たちのストーリーが乗ってました。
分野的に少し難しいとは思いますが
2週目で理解を深めることもできるので購入して良かったと思っています。
Posted by ブクログ
哲学という言葉はよく聞きます。しかし何と聞かれても何だろうという感じでしたので、手に取りました。
ざっとの雰囲気は掴めました。読んだその時は理解できても難解なテーマであまり心に残りません。ここから気になるもの見つけて深掘りするのかと思います。
時代ごとに章立てされていますが、自分が興味を持てず知識もないのでいきなり色々叩き込まれた気分です。それでも最後まで読めたのは、カラーで図や絵があり短い文章でまとめられていたからだと思います。
Posted by ブクログ
哲学について簡潔なテキストと図解で説明されている。タイトルのとおりで知識ゼロでも楽しく読めると思う。
テーマが幅広いため読み飛ばすところが少なくて読むのに時間がかかってしまった(テーマが限定的で深掘りされているような本であれば詳細で興味のないところは読み飛ばせば良いが、本書の形式ではそういうわけにもいかない)。時間をかけられる場合は読みやすくて良いと思う。
053ページ
ヴィトゲンシュタインは、感覚や感情、意志など、自分の体験を自分のためだけに記録する言語を「私的言語」と呼び、私的言語は他人が理解できないので、無意味なものと主張しました。
→上司の言っていることが理解されない、というケースではこの私的言語の性質が原因の一部になっていることもあると思う。ただし単純に説明不足や説明下手の要素もあるだろう。
068ページ
デカルトは生得体験をもとに演繹法によって正しい知識を得られると考えました。
082ページ
ベーコンは、イドラを排除して正しい知識を得る方法として、「帰納法」を重視しました。
→演繹法と帰納法については読む前から知っていたが、こうやってデカルトとベーコンを比べることは考えられていなかったので参考になる。巻末の索引で演繹法は載っているのになぜか機能法は載っていないため、後で探せるようにページ数をメモしておく。
144ページ
カントは生涯独身でしたが、「ひとりで食事をすることは、哲学者にとって不健康」と考え、毎夕、知人や友人を招いて会食をしました。会食の席では、カントはユーモアに富んだ会話を好みましたが、哲学や学問の話は厳禁だったそうです。
→哲学者以外の独身者にも響くものがある。会食を真似したいところだがハードルが高くてできそうにない。
180ページ
ボーヴォワールは、生物学的な性差である「セックス」と、社会的・文化的な性差である「ジェンダー」の違いを明確にしようとします。
→私もこの両者に違いがあることを理解できていなかった。プログラミングの変数名でsexと書くのが恥ずかしくてgenderと書きます、という話を聞いたことがあるが、言葉の定義が異なるならこの言い換えは本質的には良くないのかもしれない。
188ページ
ソシュールは、言語には「シニフィアン」(意味するもの)と「シニフィエ」(意味されるもの)があるといい、言語が異なると、「シニフィアン」と「シニフィエ」の結びつきが変化すると考えました。
→ソシュールの名前は言語学者として聞いたことはあったけど哲学者の分類でもあるということを本書で知った。
→シニフィアンとシニフィエが何なのかサッパリわからないし、図解を見てもわからなかった。Wikipediaを見てようやく理解した。正直、本書の図解が悪い。
↓
シニフィアンとは、語のもつ感覚的側面のことである。たとえば、海という言葉に関して言えば、「海」という文字や「うみ」という音声のことである。一方、シニフィエとは、このシニフィアンによって意味されたり表されたりする海のイメージや海という概念ないし意味内容のことである。
Posted by ブクログ
映画『ぼくらの哲学教室』と、それを契機に読んだ『これからの仕事になぜ哲学が必要なのか』(岡本裕一郎著)の、副読本として、字引的に使えるかなと買ったもの。
イラストが豊富で、哲学とはなんぞや?を、古代から現代まで、大きな時代で括って、その歴史、変遷を見開きページ単位にまとめて見せてくれる。
各章のあたまに、「ざっくりわかる!」と題して、その時代の哲学の特徴、テーマとしたものをまとめてくれている。
「~とは何か?」と、”存在”を問うことで世界を把握しようとする古代哲学。中世になると、「神」の存在の証明のために哲学は使われる。近代になると、”認識”がテーマだ。認識する精神(主観)と認識される物体(客観)という考えが導入される。人間にはものごとを認識する力がある。だから”我思う、故に我あり”(デカルト)なのだ。近代後期になると、認識される物が、「自由」「幸福」といった抽象概念になり、その真理を探ろうとする一方で、その客体の如何に関わらず自分の存在(実存)を求める考え方もでてくる。そして、現代哲学は、心(自己)を中心に発展してきた近代哲学の考え方を批判し、「言葉」を中心に考えようとしたり、そもそも己の実存というのものも、個々人で成り立つものではなく、環境によって形作られ、システムによって規定されると構造主義なんかが唱えられるようになる。
元は、普遍的な真理を模索してきた哲学だが、いまや他との差異があることに注目するなど、これまで求めてきた『大きな物語』ではなく『小さな物語』を互いに認め合おうと、まさに多様性の時代に、それがポスト・モダンの思想だそうな。
要は、哲学は常に常識を疑ってかかれ、常に新しい視点を見出せ、ということがその本質にあるということだ。それは、序章に既に書いてあった。
「ひと言でいえば「問い」の学問」
ということだ。思考力を養う学問であり、多分、まだまだ思考訓練は永遠に継続され、つねに、いまある常識を疑って、刷新(ないしは以前の思考への揺り戻し)を繰り返していくのだろう。
「ざっくり」歴史を概観してくれたことで、大きな流れは分かった。
で、だから? だから、哲学って何?ってことも含め、永遠に問い続けていかなければならないのだろうな。 ふぅ、、、やれやれ。