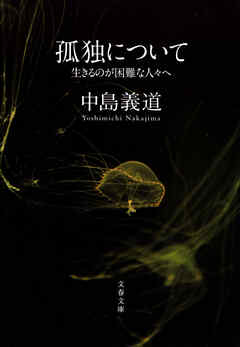感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『私の嫌いな10の人々』 を書いた哲学の教授、中島先生の本。まず冒頭に、この本を書く理由が宣言され、その後は祖父母の代からのルーツ、両親や姉など自分をとりまく人々の説明、そして自分史へと続きます。感受性が強すぎて?!他人とのつきあいを社交辞令的にテキトウに流すことができなくて?!周囲の<フツウのひとたち>と違い過ぎ、周りに合わせろと強要されてなお周りに合わせることが出来ずに苦行のような日々を送っていた子供時代の話から、ある教授にいじめ抜かれたという助手時代の話まで、すごく具体的なエピソードとともに、過去の体験が赤裸々に綴られています。その記憶力のすごさはきっと、辛かったという強い感情に裏打ちされているような気がして、大変だったのだなぁ、と思いました。中島先生ほどとんがった人でなくても、例えば「孤独」を「マイペース」くらいの柔らかい言葉に置き換えて読むと、素直にふむふむふむ、とストンと納得しながら読めるのではないでしょうか。
Posted by ブクログ
あなたは俺か。
そう思うような考えばかりだ。
しかし、どれも彼の体験に出自を持つ言葉で、当然自分には当てはまるべくもない。それでもなお、ああ自分の感じた思いはまさにこういうことがいいたかったんだ、と思う。
Posted by ブクログ
とても強度のある本。筆者の極端ぶりはとても美しいです。すごく落ち込んでいる時に読むとこころが軽くなるというか、悩んでいる状態に諦めがつきます。逆にそこそこうまく行っている時に読むと、自分の中途半端さに落ち込みます。
Posted by ブクログ
そこそこにこなしているつもりだけれど、どこか生きづらい。
でも、こんなに極端に生きづらいという人がいることは、なんだか安心する。
デラシネ(根なし草)
Posted by ブクログ
ある病気を患い、「死」を肌で感じた時から「独り」を意識するようになった。でも、それはまだ「独り」であって「孤独」ではなかった。けれど、明日が訪れる不思議を意識できるようになってから、「孤独」を少しずつ自分のものにできてきたように思う。
そんな想いにかかった靄を払ってくれたのがこの本。自信や確信が持てないまま離れられなかった「不安」。その「不安」を磨き上げればよい、と教えてもらって、心が少し軽くなった。
Posted by ブクログ
おもしろい。とにかくおもしろい。(僕と同じ人種が居た!)という発見とでも言おうか。
この本は、著者自身の孤独にまつわる自分史であり、したがって、深い哲学的思想がどうこういう類の本ではない。著者の偏屈で混迷極まる孤独っぷりを、これでもかと開けっ広げに語り尽くす。そこが痛快で楽しい。タイトルだけ見れば、めちゃくちゃ重そうなテーマだけれど。
著者はあとがきでこう書いている。「いつか、自分のぶざまな人生について書いてみたいと思っていた。なぜ、周りの者たちがすいすい進んでゆくところを、自分ひとりだけ転倒するのか?なぜ、こんなにも他人とうまくいかず、なぜこんなにも生き方が下手なのか?要領が悪く、不器用なのか?なぜ、こんなにも自分が嫌いなのか?そして他人はもっと嫌いなのか?なぜ(自分を含めた)人間の嫌なところばかりが見えてしまうのか?つまり、なぜこんなにも生きるのが困難なのか書いてみたいと願っていた。」願っていたけれど、「書けば書くほど憂鬱になる」という有様で、ある意味で呆れるくだらなさ。
思えば、僕たちは幼いときから、(明るく楽しく元気よく、みんなと仲良く遊びましょう)と大人たちに教えられてきた。裏を返せば、大人しかったり、根暗だったり、みんなと遊ばなかったり、一人で本を読んでこもったりすること、つまり孤独であることは、半ば絶対悪のように刷り込まれてきたのである。それは社会性を育むため、協調性を育むため、という大義名分があるからだ。しかし、大人になってあることに気付く。確かに社会性や協調性は生きてい
くうえで大切だけど、しかし、じゃあ、時に無性に独りっきりになりたい気分に襲われるのはどうしてなの?と。トイレに鍵を掛けて、便座に腰を掛けているときに味わう、あの独りぼっちの安堵感は何なの?と。
人間は社会的生物だと言った人もいたが、そもそも人間なんて身勝手・自己中心的な生き物である。しかし、自己チューだけでは世の中を生きていけないので、社会性・協調性という仮面を被り、皆、生きているのであり、往々にして、仮面は息苦しいのだ。だから人間には(少しでもいいから)孤独な時間が必要なのである。‘本当に素直な自分に帰れる時間’が必要なのだ。孤独であることは悪いことではない。孤独を楽しめる人間になりたい。
はっきり言って、しょーもない本である。でもこういう本があるから救われる。少なくとも、僕は救われた。皆さんにおかれては、本屋さんで見かけたとき、序章をパラパラと読み、おもしろいと感じたらば、是非買って読むべし。上辻推薦。
Posted by ブクログ
新聞記事で中島義道氏を知りました。
東大卒の哲学者で記事はニーチェブームに疑問を呈していました。
面白うそうな人だなぁと思ったので買ってみました。
本の内容は自伝です。
言葉のタッチがハッキリしているので気難しく厳しい人の様に感じますが実際はとても繊細な人で優しい人なんでしょうね。
そうなんですよね…一見柔和で物腰やわらかい人っていざとなると逃げちゃったりするけど、普段は素っ気ない態度で近寄り難い人が以外に見ていてくれて危機の時に手を差し伸べてくれたりしてくれるのよね。
疲れている人に、こんな生き方もあるよと教えてくれる本です。
Posted by ブクログ
これは、人間嫌いで自分勝手、優秀で努力家で妥協ができない頑固者、そんな著者の自伝。
考えすぎてしまうからこそ何もできなくなる。そんな部分に共感した。
私は、考え無いことにした。感じるがままにあることを選んだ。
著者は考え続けることにした。思考の袋小路で孤独であることを選んだ。
何かを訴えるわけでもなく、教鞭をたれるわけでもなく、自身の半生について潔いまでに正直に書き連ねている。正直であるがゆえに、著者のズルさ、強かさがリアルに感じられる。
私は彼から何かを得るわけでも、師として仰ぐわけでもない。
ただ、彼の不幸な人生を嘲笑い、けれどもその一部に深く共感し、安心して己の孤独にはいらんとするだけである。
Posted by ブクログ
「私は他人に執着することが嫌いである。」と始まるが、父親や留学生たち、Y教授に対する述懐は、執着そのものである。筆者の溜飲が下がるだけだ。
積極的に孤独な時間を作ることは、必要であると、歳を重ねるにつれて思う。しかし、それだけを追うことは、自分にはできない。
人生のある期間に、孤独な時間にどっぷり浸かることで、他者との関わりに幸せを感じることができるのだと思う。
Posted by ブクログ
明るく元気で、前向きに、人に囲まれて快活に生きてる人は、この本を手に取ることはないでしょう。逆に、こういう陰気なタイトルに惹きつけられるのは、著者と同類(または近い)の暗さを持ってるってことでしょう。そういう、ごく一部の人にとっては、胸にズキッとくる痛みと一緒に、共感と勇気を感じられる本じゃないかな。
最近は、ポジティブ・シンキングが徹底してて、ネガティブなことをちょっとでも考えると害になる、ネガティブ発言をする人には近寄らない、みたいな雰囲気があったり、仲間を大切に、家族を大切にっていう傾向も強まってる気もするんですが、素直にそう思えている人にとっては、異次元の内容でしょうねぇ、きっと。
でも、ひねくれ者は、世間で当たり前とされていることは、はたして本当に正しいのか?と、否定してみるのです。だから、みんなとは違うものが見えてくる。そして、変人は意外にもポジティブで、読後感はむしろ、すがすがしかったです。
世の大多数の人にとっては、どうでもいいことを、考えに考えて、考え抜くのが哲学。私にはおもしろいです。