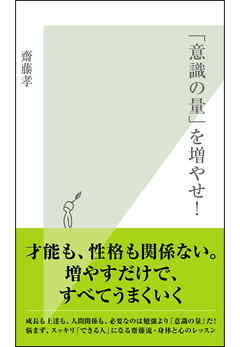感情タグBEST3
Posted by ブクログ
再読だが新たな発見。
以前は自分のキャパを広げるためだったが、今回は教える立場として読んだ。
人格や才能と切り離して、
「意識の量」として、
努力でなんとかなる領域を提示した
着眼点が素晴らしい
Posted by ブクログ
よく気が付く人・仕事ができる人は意識の量が多いという著者の気づきから書かれた本です。勘働きがいい人、いっしょにチームを組みたいと思ってもらえる人とはいったいどういう人か・・がよくわかります。自分の分身「意識小僧」の人数を増やし、能力を上げるメソッドも(お茶だし名人は仕事もうまい・名幹事は仕事ができる・・・) 巷で見かける「なるほど」が満載の本。
Posted by ブクログ
古本で200円で買ったが、3000円の価値があったと感じる。
非常に大事なことが、具体的に分かりやすく書いてある。
「意識の量」についての意識が増すこと、間違いなし!(^^)
バンバン行動して、ぐんぐん成長するためには不可欠の要素が
「意識の量」だろう。
仕事などで伸び悩んでいる人におすすめする。
Posted by ブクログ
求められていることを的確に理解し、自分の役割の中で最大限に力を発揮できる人。
仕事も婚活も結婚生活もそう。
意識が曖昧な人のまずい点は、自分がうまくできた経験を蓄積できないこと。
成功体験boxを溜め込んでいく。
Posted by ブクログ
意識の量を増やすとは、「なんとなく」日々を過ごすことを止めて、よく考えて行動して行くことだと感じた。
それが大切なことはわかっているが、実践することは難しい。
毎日を考えずに過ごすことは脳のエネルギーコストの節約にはなるが成長はできない。
「なんとなく」、半ば反射敵に生きてしまっている自分には日々の生活を見直す良い機会となった。
また時間が立って読み返しながら意識の量が増えたか確認してみたい。
Posted by ブクログ
すごく為になった。仕事する上で、どういう意識でいるか、どうしたらいいか概念が書いてある。最近少し怠けていた自分に、喝が入った。
どの世代でもオススメだけど、特に就活生や新社会人は読んだらいいと思う。
Posted by ブクログ
共感度の高い一冊。
周りにとても感度の高いアンテナを常に張り続けることは、とても体力のいることであるが、でもそれを自動化する、すなわち自分が自然とできるような余裕と心持をしておくことで、その状況でいったいなにが起こっているのか、すぐ自分の理解がすることができ、困ったことが起こったときの対策も打ちやすくなる、という風に理解しました。
他の人と仕事をしたい、と思われたい人のための秘訣がここにつまっている?
私も、チームジーニアスの一員になれるよう、改めてがんばってみよう。
Posted by ブクログ
自分も意識の量がかなり低いです。
社会人になって、だいぶ経つのに、できていないことが?多いことに改めて気づきます。
そんな自分を棚上げするのであれば、是非多くの若い方に読んで?ほしい本です。
Posted by ブクログ
著者から選書。気が効く、状況に適した反応、立ち居振る舞い、といったことの総称を「意識の量」と定義し、社会に求められる人材とは意識の量が多い人だと喝破。行動を変えれば意識が変わる。日常生活の基本的なこと、睡眠、食事、運動、掃除を整えれば、自ずと意識は洗練される。
Posted by ブクログ
社会人2年目になった私にとって為になる一冊だった。
私の尊敬できる人たちを思い浮かべると「確かに!」と共感できることも多かった。
これからの仕事や人間関係でも少なからずとも少しは実践できそうだなと思えた。
斎藤孝さんの本いくつか手に取ったが全てとても読みやすい。この本もその一冊と思う。
Posted by ブクログ
意識の量に意識をしていなかった生活から、変わるだけでもいろいろな面で良いスパイラルになることが理解できる。
著者の言う通り、最近意識の量が少ない人が多い
Posted by ブクログ
意識の量を増やせ!ってどうゆうことなのかと思ったら
要は質よりも量、常日頃様々なことにアンテナを張り巡らせろということ(らしい
意識高い系とは全く違う「意識の量多い系」ってことですかね(たぶん
ベテランと新人の例で言うならば、どんだけ場数を踏んできたかってこと
そこでちゃんと自分の糧になっているという事だと思う
自己啓発系の本は普段読まないのだけど、これは良いなと思った。
胡散臭くないから。はっはっは
自意識メタボ。この言葉凄く好き。
Posted by ブクログ
とにかく続ける。その結果意識の量が増える。
幼稚園の日課を見ていてもその意を強くする。
人の話を聞いて言語化する。
リストアップすることはよいトレーニングとなる。
自意識を捨て、自分を変えていく。
人脈とは誰を知っているか。ではなく、誰に知られているか。
よくしゃべる。よく間違える。よく笑う。つまり、よくトライし、よく失敗し、どんどん吹っ切る。
環境を変える。そして今何を意識してやっているかを常に考える。
意識の量を増やす。とは著者の標語とのことだがよく分かり、共感できる。
Posted by ブクログ
あとがきにもあるが、心は変化するが意識は「ワザ」である。
心もコントロールできるが、意識についてはより容易である。意識の量や質が人生を変えるとしたら?
それは当然、意識に注意するしかあるまい。
行動は何より大切である。意識する、というのも行動の一つではないのでしょうか。
Posted by ブクログ
普段からどれだけ自分のしていることに意識がまわっているか、というのが意識の量。
何をするにも「いましていることの意味」を考えさせられると思うと、疲れるけど確かに役立つんやろうなぁ。
よくしゃべる、よく間違える、よく笑う、の三原則がいい。それってめちゃくちゃ愛嬌のあるひとやなぁと思った。
Posted by ブクログ
日頃よく使う意識するとか意識が足りないという意識という言葉に焦点があたっていて、普段よりよく使うが実はあまりその意味や具体例がわかってない人、自分には目から鱗だった。意識の量を増やすという一つの考え方のほか、具体例やすぐに実践したくなるような話が色々あり読み応えがあった。
Posted by ブクログ
人脈、とは、自分が何人の人を知っているかではない、
何人の人が自分のことを知っていてくれるかである。
他人の意識の中に残るような、
印象のある人こそが、真の人脈を持つと言える。
進路や、人生についての悩みは友人ではなく経験をつんだ人間にするべき。
Posted by ブクログ
今シゴトがうまく行ってない理由を分析。すると…
1.語学ができない、かつ自信がないから、コミュニケーションができない
…これはもう勉強するしかないです。
2.慣れていない。
…これも慣れるしかない、といえばそれまでですが、自分を改善していくためにきっと
できることがある!
と思い、本を読みまくっています。
この本もそう。かなり目からウロコ。今の自分にまさにぴったり。
「意識の量」が少ない。確かに。同時に複数のことを走らせることを、
自分は完全に放棄していたけれど、
これだけの仕事量と、日本とちがって情報化された職場環境のなかでは
何人もの「意識小僧」を頭の中に働かせることが大事!ということを
この本から学びました。
で、じゃあどうすれば意識の量が増えるかと。それは、もう練習です。
訓練。日々の積み重ね。イチローの世界、「練習ハ不可能ヲ可能ニス」です。
いつのまにか富士山登りきってました、みたいな状態になるべく頑張るのです。
あ、もう七合目だ、八合目だ、おれも大したもんだなーではだめで、
あ、まだ山あるじゃん、と思いながら常に上を見ていくことです。
Posted by ブクログ
後半の方で少し飽きてしまったので、かいつまんで読ませていただきました。
社会人になったばっかりの方や、上下関係が厳しいところにいなかった方は読んでみると良いと思います。
コロナ禍で人との関わりが乏しくなった今では中々難しいかもしれないけど、ちょっとした行動に意識を向けることで得られる気づきは大きいと思います。
Posted by ブクログ
自分の解釈は、意識の量を増やす=想像力を働かせるということかな。いろいろなことに気を配れて、先読みできる人が意識量の多い人。
周りが見えているようで見えてないことがあるから、意識増強メソッドを実践して、意識の量を増やしていきたい。
Posted by ブクログ
・内容
キーワード: 意識、EQ(社会的知能)、自己 客観性、感知力・対応力
【ソーシャルインテリジェンス】
意識の量を訓練により増やし、集中させることで人間関係をうまくやっていける能力(=社会適応力)。加えて、感覚の鋭化、優先順位も重要。
・メモ
近年、意識の曖昧さ・切迫感の無さが顕著。人柄がいいのと使える人材かは全く別。やっているつもりとできているは全く違う。多くのことを同時に意識し、その意識配分を間違えない。意識は志向性を持つ。思いやり、気遣いを自然に行う。意識のトレース【人の意識に入り込む感覚】を養う。意識を上手に用いて、細胞レベルで自分を変えていく。スポーツ等における体験として、ゾーン、フローがある。
参考: 思考の整理学【ちくま文庫】
『思考』のすごい力【PHP研究所】
語彙: 俯瞰、件(くだん)、齟齬
・自分の感覚
白・黒、グレー、グレースケール。
顕在意識(マインドフルネス)と潜在意識。
Posted by ブクログ
仕事が出来る人は意識の量が多い人のこと。意識の量を増やすのは、訓練すれば出来ると説いています。
仕事が出来るとはどういうことか、頭がいいとはどういうことか、これまでと違う気づきを得ることが出来ました。
ポイントは「質ではなく量」を言っていること。意識を研ぎ澄ませといってもなにをすればいいかわからないが、量を増やすのは具体策がわかりやすい。
色々なことに興味を持つこと、知らない場所に行ってみる等刺激を得る努力が必要。
臨機応変な対応が出来るには相手視点の意識を常にしておかないといけない。
Posted by ブクログ
本書は自己の過ちを受け入れ、気づきと改善をするために「意識の量」を増やすことを提案している。
意識という言葉が使いやすく、これが意識か?と思う場面もあったが,物事のとらえ方,自己分析,コミュニケーションなど多岐に渡って紹介しており,参考になる。
メモの取り方が「意識の量」とどうつながるのかは分からないが,メモをとるという過程には、話を聞く、再構築する、内容を書きとめるなど複雑化した作業であるから同時にいろいろな力を求められてそれを意識ととらえているのだろうと解釈している。
このメモの取り方は興味があったため以下に引用する。
メモ力
レベル1 人の話を聞いて、それを書きとめる。
レベル2 構造的に整理したメモがとれる。
レベル3 自分のインスピレーションも同時にメモする。
メモも構造的にとれると、見返したときに一目でさっと内容が把握できる。ただ、箇条書きにするのでなく、数字や記号を使いながら階層構造に整理できるか。関連する内容を線や矢印でつないだり、原因と結果を判別しやすいようにしたりできると、メモとしての価値がなかなか高い。さらにワンランク上のメモとは、聞いた話をメモするだけでなく、それを聞いたときに自分が感じたこととか、疑問に思ったこと、自分の中で炸裂したインスピレーションをも書き込んでいくメモの仕方だ。メモに自分に自分のコメントを入れていく。P94
会議や打ち合わせには、必ずテーマがある。はじめに、いま何を求められて会議をしているのか、リクエストをキーワードで真ん中に書き込む。そのうえで、「ではどうするか」を話し合い、出てきたアイディアを次々書き込んでいく。その案で懸念されること、矛盾することも書いていく。その紙を意識の展開図だと考え、脳の中の意識をその場で広げていく。影響すること、矛盾すること、作数することを矢印でつなぐと、みんなの意識が同じ志向性をもつので、話が逆走したり堂々巡りになったりしにくい。P98
Posted by ブクログ
他人が求めているものをいかに汲み取るか、そのために意識の小人を増やすことが大切という話。
周りに気をつけながらの人もいるとは思うが、携帯を見ながら、イヤフォンで音楽を聞きながら歩いていて、ぶつかる人が増えたのは意識が減ったかた(自分の世界に閉じこもっているから)なのだな、と思えた。
また、相手に想いを伝えるためには語彙力が必要であり、そのためには読書がやはり有効らしい。もっと読まねば。
Posted by ブクログ
齋藤先生の本にしては珍しく具体的な例が少ないかな、という印象の一冊。
もちろんおっしゃっていることは正鵠を射ているし、意識の量→好奇心旺盛的なところから新たな道が切り開かれるんですよ、というところに異論はない。
でもせっかくならもっともっと昔のいろんな人の話が入ってきたほうが説得力があって納得感も高まるんじゃないかなと思います。
Posted by ブクログ
またまた上司からお借りした本
この本でいう意識の量とは一般的に気遣い、心配りを仕事全般に落とし込んだ事を言っているのだと思う
どんな人にも思い当たるフシはたくさんあるだろう
これまでよりも少しづつ意識の量を増やしていく事は大切だが
一気呵成に行おうとするとパニックを起こすかもしれないので要注意。