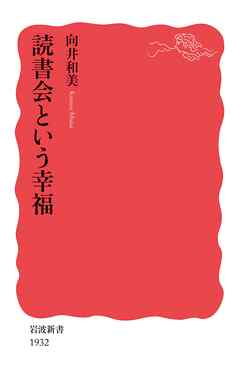感情タグBEST3
Posted by ブクログ
プリズン・ブック・クラブの翻訳もされている、向井和美さんのエッセイ。読書会に三十年以上参加されていて、読書会の魅力を語っている。うんうん、分かる分かる!という内容で、やっぱり読書会って良いなあと思える。「読書会を成功させるヒント」も参考になる。
Posted by ブクログ
本書のレビューを書く前に、とても情けない身の上話をさせていただく。
私は2年前に社内読書会を立ち上げて、月に3回のペースでスケジュールを組んでいるが、参加者が集まらない。そしてメンバーが定着しない。ドタキャンする人もいる。いつも最低4人集めるようにしているが、予定通り開催できるのは2回に1回程度。いろいろな人に声をかけて、宣伝メールも送るのだが、無視されることも多い。自分よりずっと下の後輩社員にすら、無視される。職場の中で、わざと私に聞こえるように「読書会?そんなもの出て意味あるの?飲みに行かない?」「読書会って、意識高い系を狙ったねずみ講なんでしょ?」と大声で話す輩もいる。
もともと神経は図太いタイプなのだが、さすがにこのような日常が続くと、なんだか気が落ち込んでくるものである。そんな自分を何とか奮い立たせるために手に取った一冊。筆者は35年も続いている読書会に、29年間通われたそうだ。そしてご自身も司書として働きながら、若者たちの読書会を主宰されている。それだけ長ければメンバーの入れ替わりも激しいだろうと思いきや、固定メンバーが多いらしい。
てっきり読書会の運営ノウハウや新規メンバーの増やし方が書かれているのかと思ったが、普段参加されている読書会でのやり取りや、筆者ご自身の「人生の振り返り」を綴った内容であった。ただし、ページをめくるにつれて、静かに、そして丁寧に、年月をかけて積み重ねてきた筆者の人間的な魅力が、じわじわと伝わってきた。「本について語り合うことは、人生について語り合うこと」という筆者の決め台詞に、私は一気に引き込まれてしまった。個人的には、何十年も続けている茶道に続いて綴った『日々是好日』を読んだ時のような感覚である。
「去る者追わず」「誰彼むやみに誘わず」「大事な想いを人に話したいが、分かりあえる少人数だけでいい」という、筆者の読書会に対する距離感は一見中途半端に見えるが、程よく心地よいものでもある。筆者にとって読書会とは、大事な箱入り娘のような存在なのだろうか。
「急用ができた」「仕事が忙しくて読む暇がない」「1人で読むほうがいい」などなど、読書会に参加しない(本を読まない)言い訳は、いくらでも作ることができる。その小さな積み重ねによって、読書会から足が遠ざかる。そんな振る舞いが、不思議と他のメンバーにも伝播するので、会員が1人1人と減っていく。会費は無料だが、事前に時間をかけて本を読んでこないといけない読書会より、お金をかけてでも、同世代の若者と飲み会やデートに行く方が魅力的なのかも知れない。そんな風に感じるお年頃であってもしょうがないのだ。そして、一生読書会に来ないかもしれないし、数年経ってある時、ふと戻ってくることもありうる。
名著を読んで、自らの言葉で感想を述べるだけなのに、新たな発見と感動がある。そして家族のように人生かけて付き合う仲間がいて、本当にうらやましい。30年も継続するわけである。
それに比べて、毎回参加者の人数を見てクヨクヨしている自分なんて、吹けば飛ぶような、チョロい人間である。周りがどんな噂をしようと、奇異の目で私を見る奴がいるだろうと関係ない。これまで1回でも参加してくれた社員に感謝しつつ、私は読書会の看板を掲げ続けていく。
若手社員たちが、読書会に興味を持ってもらえず、リピート参加してもらえなくとも、長い人生のどこかで、ふと「読書会やっていたな。まだやっているのかな。」と思い出す瞬間があると信じて、細く長く、灯を消さずにいるつもりだ。読書会を辞めたくなったときには、この本を再読すれば良い。
そして私が老後になって、読書会を継続しようと躍起になっていた記憶を、酒の肴にできるくらいには、日々粘り強く開催していこう。
Posted by ブクログ
この本を読んだら、読書会を体験してみたくなっちゃいますよね〜。
他の仲間と読むことで、自分1人では気づかなかった視点を得られたり、自分の中で必ずしも十分に形成されていない思いが、他の仲間の話を聞くうちに化学反応が起きて具体的に表現出来るようになるという体験について、著者が自らの経験を通して語ってくれる静かで熱い内容。
早速、会社近くの本屋さん主催の読書会に登録して先日第一回目がありました。ドキドキでしたが、1つの共通した課題本が皆の拠り処。
Posted by ブクログ
翻訳家、司書。参加した読書会で読んだ本は35年で180作品。読書会を通じて触れる古典文学そして読書そのものの魅力。
読者という極めて個人的な行為が読書会という集団行動を通じて変化する。何とも面白いことだ。取っ付き難い古典文学も毎月の課題として数年かけてみんなで読んでいく、しかも自分では気づかなかった解釈や魅力も堪能できる。
巻末に実際に読書会で題材とした作品のリスト付き。これだけの作品に触れた人が羨ましい。
読書会を探して参加してみたくなる間違いなしです。
Posted by ブクログ
コロナ禍の中で友人とzoomで一つの本を一緒に読む、という体験から読書会に興味を持ち、晶文社「読書会の教室」を読んで、ますます、もっとやってみたいモードが高まっているタイミングでの岩波新書。題名も「読書会の幸福」ってホンワカムード。でも中身は超ハード。のっけから子供時代が両親の不仲で地獄だった話。文体も柔らかくて、しかも読書会の体験記や読書会の運営のノウハウや、読む前にこちらが期待していた構成もちゃんと盛り込まれているのですが、そういう気軽さを覆いつくす、本と人生の熱い物語。著者の人生。なにせ「もしかしたら、わたしがこれまで人を殺さずにいられたのは、本があったから、そして読書会があったからだと言ってよいかもしれない」ですから。読書会の数少ない男性メンバーのTさんのエピソードは、まるで短編小説のようだし、現在のパートナーとの関係もそこまで書く?ということをスルッと紛れ込ませてくるし…恩師や父親の最期の話もグッときます。まさに生きることは文学を読むこと、読んだ文学について人と語らうことは生き延びること、という文学の力を感じました。まさに章のタイトルになっている「文学に生かされて」の迫力。著者にとっての「読書会の幸福」は「読書会に生かされて」という意味なのだと合点しました。この著者、やさしい文体でも結構、凶暴です。カズオ・イシグロ「日の名残り」で丸谷才一の誤読にも噛みついているし…それにしても巻末についている1987年からの読書リストの豊饒さよ。文中に出てくる「ぼくはこのほとんどを読まずに死ぬのか…」このつぶやきは自分のつぶやきでもあります。
Posted by ブクログ
『読書会』
気になってはいるのだが、元来臆病な人間で人前で話したりも苦手だし、自分に合いそうな読書会コミュニティを見つけられないということもあって敬遠してきた。
だが読書会に関する本は好きで、いくつか読んでいる。
本書はその読書会のなかでも刑務所内の読書会を描いた傑作ノンフィクション『プリズン・ブッククラブ』を翻訳した向井和美さんの本ということで手に取った。
これは素晴らしかった。
本への愛も素晴らしいが、読んでいるだけで読書会に行きたくなるようなワクワクに満ちていた。
難しい本に挑戦するのにも一人だと挫折することもあるが、読書会で話すという課題があると頑張って読もうと思えるという部分。
そんなもんかな? なんて思っていたが、巻末の読書会で課題になって読破した図書リストを見ると自分も挫折したような本がズラズラと並んでいた。『失われた時を求めて』『戦争と平和』『チボー家の人々』などの大作も人と一緒なら挑戦しようって思うかもしれない。
そして一人でも面白いのだが、他者がいると視点が広がる面白さもある。自分が木にしなかった部分を、他人はとても気にしていたり、自分には答えが出せなかったものが、他人には見えていたり、と。
そういう視点の広がりという面白さもあるよなって思った。
著者が自慢する巻末のリストも素晴らしい。
Posted by ブクログ
新聞の書評を読んで興味がわき手に取った新書です。
冒頭、「わたしの両親は、けんかばかりしている夫婦だった…..」から始まり「わたしがこれまで人を殺さずにいられたのは…..」という文章を読んで、この本はどんな展開になるのだろうと少し心配になってしまいました。
でも、読み進めると好感を持てるようになりました。著者の30年に及ぶ読書会での活動や、本をとおして人とつながる熱い想いが、丁寧に語られています。また、翻訳家である著者が翻訳家視点での読書を語る部分は、今まで気づかなかったことを教えもらい、新鮮な気持ちで読みました。
本書は古典文学を中心に、200冊近くの本を取り上げています。読んだことがない作品が大半です。全部読みたくなりますが、無理かな?
Posted by ブクログ
読書は一人で楽しんでもOKです。でも他の読者と話し合うと、文学を通して深い人生の話もできる。読書会に行くのが恥ずかしい・緊張する・ハードルが高いと思ている自分も感想を共有したくなった。
Posted by ブクログ
長年読書会に参加してきた翻訳者である筆者によるエッセイ。作品論あり、読書論、読書会論ありの、多彩な内容となっていて飽きさせない。チョイスされている本は、ともすれば「高尚」と揶揄されかねないような、文学畑の本たちです。本を通じて人とつながること、本を通じれば、人と繋がり合うことができる幸せが、存分に語られている。
Posted by ブクログ
読書会の楽しさを知らせてくれる面白い本だ.小生も某所の読書会のメンバーだが、運営のことなど参考になる点が多かったが、小学生で本を読まない、or 読めない人がいることには驚いた.大人で読書をしない人は多いが、子供の時は何かしら読むものと思っていたので意外だった.筆者の参加している読書会では有名な古典作品に取り組んでいるようで、凄いなと感じたし、議論の内容も素晴らしいと感じた.
Posted by ブクログ
2022.9月末、JWAVEの早朝番組の最終回で紹介され、すぐ予約した本。
読書会に参加したいと思いながら、なかなかできないので、何か良い知恵がもらえたら…と読み始めました。
司書、翻訳家。私にはまぶしい肩書の著者が、30年参加している読書会に誘われたきっかけ、そこで読まれた作品リスト、著者の半生を時々のぞかせながら、読書会を成功させるヒントなどもコラム的に紹介。とても有益でした。
「本好きの生徒は往々にして内向的」
「(著者の師匠と著者が)ふたりとも内向的で話下手」
自分もやっぱり内向的と再認識…
読書会はある意味社交界…だから成功させるヒントも必要なのでしょう。
自分自身はパートナーと2人読書会もどきをしています。
それくらいでちょうどいいほど、内気なのです…
それからこの場所に記録できているので、仮想読書会体験中、ですね。
本の紹介本としてもひきつけられました。
並行して読んでいる別の本と同時にヘミングウェイを紹介され、読まなくては。
アチュべ
マンガレリ
ガイイ
フランス組曲
魔の山
ロリータ
チボー家の人々
トルストイ
チェーホフ
プルースト…
果たして生きてる間に読めるのでしょうか!?
「Tさん」のエピソードも、心に残りました。
著者の師匠、東江一紀さんの翻訳にも、特に若い頃お世話になりました。
合掌。
Posted by ブクログ
30年余り続く読書会の秘訣は課題本にふだんでは手に取らないであろう古典本を深く読みいろんな人の感想を聞く楽しみらしい。私が参加する読書会はおすすめ本を紹介することが多いですがオンライン開催になってからは全国たまに海外からもといろんな意見が聞け楽しいですよ。
Posted by ブクログ
最後まで読み切れてはいないが、読書会という場を通じての人の交流、知らない本との出会いの素晴らしさは私も日々実感している。
今は幼子を抱えながら、同じ立場のママとのビジネス書を中心としたオンライン読書会ばかりだが、そのうち、ライフワークの1つとなるくらいいろいろ広めていきたい
Posted by ブクログ
読書会の魅力を語るエッセイ。普段行っている読書会を始め、さまざまな形式の読書会について紹介している。
本書のテーマは「本を語ることは人生を語ること」。読書し終わってまとまり切らない半熟状態な思いを読書会という場で語り合うことで、自身の考えが整理されたり、思いもよらない視点に出会えたりする。また、意見を聞いて言いたいことが湧き上がり、自身の体験も交えて話したくなってくる。そうして、思いは形となり、知っている人/初めての人と繋がりができていく。
1人で読書するのもいいけど、読書会に参加して語り合う読書も他にはない魅力があることを教えてくれる。
Posted by ブクログ
1.この本を一言で表すと?
読書会の意義と魅力をまとめた本。
2.よかった点を3~5つ
・「本を通して人とつながる」喜びを味わえているのかもしれない。(p6)
→読書会の魅力の一つだと思う。
・司書として主催する(p46)
→主催者としての苦労が書かれていて共感できた。中学高校の生徒を対象とした読書会ならではの難しさがあると感じた。
・読書会を成功させるためのヒント⑥話し合いの内容を記録しておく(p192)
→報告書をまとめて参加者に共有するのは読書会を継続して行くためのいいアイディアかと思った。
2.参考にならなかった所(つっこみ所)
・思いがけない効用を(p12)は読書会経験者としてほぼ既に知っている内容であった。
・Ⅵ翻訳家の視点から(p136)
→文章を書くための役に立つ情報は書かれていたのは良いが、読書会について関係があるだろうか?
・文学を語ることは私たち自身の人生を語ることなのだから。(p199)
→このこと自体は否定をしないが、ビジネス書を語ることも人生を語ることにはならないだろうか?
3.実践してみようとおもうこと
・文学作品をもっと読むべきと思った。
4.議論したいこと
・文学作品の読書会に参加したことはあるか?ビジネス書の読書会との違いはあるか?
5.全体の感想・その他
・著者があとがきで述べているようにこの本は良くも悪くも中身が内向きである。
・本の中盤の文学作品の読書会の感想を述べている部分では、著者の読書会の感想を述べているだけだと思っていたが、あとがきを読んでこのセクションの意義がわかった。
Posted by ブクログ
後半は少し飛ばし読みあり。
思っていたような内容以外も入っていて、そこは飛ばさせてもらった。
読書会の行いかたや長続きするポイント。著者本人は司書もしているので、中高生の本との出会いを画策するところや中高生の読書会、ビブリオバトルなど興味のある内容も多く紹介されていて参考になった。
読書会が江戸時代には存在したということや、読書会と称して政治について集まって語っていた時代などなど読書会について知れた。
Posted by ブクログ
読書会、いいなぁ。参加してみたくなりました。でも、著者が参加している会は、外国作品ばかりなので、私には敷居が高い。もう少しハードルの低い会に参加してみたい。
Posted by ブクログ
本は命だ。読もう。生きよう。
読書会、やりたい! 生きるために。楽しく、より人生を味わうために。
「読書会の利点はまずなんといっても、自分では手を出さないような本や挫折しそうな本でも、みなで読めばいつのまにか読めてしまうことだ」(ⅳ)
その通り。
読書をワークにしてしまえばいいのだ。さあやろう!
Posted by ブクログ
10年以上、読書会を続けられているのには、さまざまな工夫をされているのだなと思った。
文学には沼があると手をつけないでいたが、この本を読んで、外国文学に興味を持った。