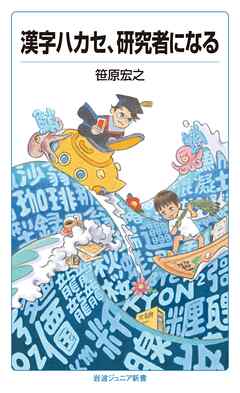感情タグBEST3
Posted by ブクログ
小さいときから漢字は好きではなかった。
たとえば近畿地方の「畿」。糸の上の部分とか田とかを1つの文字になぜ詰め込まなければならないのか、もっと簡単にできないのかと思っていた。大学で中国語の履修をしたとき簡体字がうらやましくて、私も「言(ごん)べん」を手書きするとき7画で書くのが邪魔くさくて簡体字のように略して書いたものだ。一方で、日本人は漢字を簡略化したカタカナやひらがなを発明しており、漢字の簡略化には歴史上でも実績があるのだから、現代でも漢字を日本人なりに簡略化した第三の「かな」の発明は可能なのではとも思ったりした。
いや、こう書くと、私がただ単に漢字の画数を減らすべきだと主張しているように見えてしまう。そうでなくて私が言いたいのは、ほぼ無制限に広がっている漢字使用法の“交通整理”だ。でもその思いとはうらはらに、私の漢字への疑問は社会人になってパソコンなどを文章作成で日常的に使うようになってから、つまりJIS文字コードによる第一水準、第二水準等への振り分けが適用されてから最大化した。
――なぜ「近」や「遠」は点が1つのしんにょう(之繞)なのに「辻」は点が2つなのか?
なぜ、横棒がななめになった「芦」が上位の水準で、書き文字で一般的な「草かんむりに戸(横棒が真横)」の字が環境依存文字なのか?
なぜ人名では士(下の横棒が短い)に口の「吉」と同じくらいの頻度で、土に口という下の横棒のほうが長い字が使われているのか?2つは別の文字なのか?また、はしごだかと言われる「高」の字や、立つさきと言われる「崎」の字が標準文字と並んで存在する意味はあるのか?私はただ単に昔の手書き時代の戸籍係が人名に使う漢字を深く考えずに自分の癖のままに戸籍に記載した結果、誤用された文字が一般化してしまい今に至ると思っているが。
以上から、私は「漢字ハカセ」にこれらの疑問をすっきりと整理してほしいと、この本を読む前には考えていた。
だが著者のアプローチ方法は、そういうものとは異なっていた。著者は漢字の複雑かつ多岐な利用実態に日本人が積み上げてきた多彩な歴史的背景を見いだし、興味をふくらませ、混然とした状態の使用法を著者独自の視点から体系化しようとした、というほうが正しいと言える。つまり、私が誤用ではとして挙げた使用法も含めて漢字の使用実態を正確に把握したうえで、取捨選択して一定の合理性が見いだせれば受容すべきというスタンスだ。
もちろんその受容へのプロセスは簡単ではない。この本では著者が中学生のころの漢字との趣味的な付き合いから始まって、一生涯付き合っていく仕事として漢字を受け入れ、カタカナの「ハカセ」から名実ともに「博士」へと歩む道のりが、中高生向きにやさしい文体で書かれている。その中でも著者が関心をもった「国字」についての記載は特に興味深い。
国字とは、中国由来ではない、日本で作られた漢字だ。国字一覧表はネットで簡単に見ることができる。私が出会った人で苆野さんという方がいた。「苆」ってどう読むの?「きり」?調べると「すさ」と読む国字だと知った。ちなみに著者の名字の「笹」も国字だ。これらの竹かんむりの国字といい、蛯や鰯などの生き物を表す国字といい、花鳥風月を表す文字が目に付くのは日本ならではかもしれない。
もう1つ、本書の内容で私が興味をもったのが、著者が中学生くらいのときに「当て字」の使われ方を町じゅうから探していたというくだり。ちょうどそのころYMOが台頭してトンプーという曲名に「東風」を、ライディーンには「雷電」を当てたりしているのや、暴走族がその名称に難読漢字を当てているのにも興味を示してノートに書きためていたらしい。その暴走族というので私も思い出したことがある。何年も前だが、工事中のフェンスに黒ペンキみたいなもので「神怒閥斗」と書かれていたのを見た。「シンドバット」と読むのだろうけれど、当時は「うまい!」と感心(?)した。ぜひ著者の当て字コレクションに加えてほしい。
以上、レビューという性質からやや逸脱した私の趣味満載の文章になってしまったが、これで興味がわいた人は、この本も十分楽しめるはず。
Posted by ブクログ
筆者の自伝的研究紹介の本。途中から見坊豪紀氏に似ているなあと思ったら、筆者が尊敬していて交流があったことも書かれていた。数日前に読んだ三省堂国語辞典と明解国語辞典の話とシンクロした。時々こういうことが起きるから面白い。
岩波ジュニア新書からの刊行であり、中学生や高校生にもおすすめである。
Posted by ブクログ
漢字に取りつかれ、子どものころに漢字ハカセと呼ばれていた著者が博士になる過程が書かれています。
地道で気の遠くなるようなサンプルの収集に研究することの大変さと、当て字や地名、常用漢字表の在り方について知ることができます。
岩波ジュニア新書なので、小学校高学年から高校生向きの本です。中・高の受験問題になりそうな内容です。
論文に取り組んだ時の詳細も書かれているので、論文ってどう取り組んだらいいのか、と悩んでいる大学生も読んで欲しい1冊です。
811
Posted by ブクログ
漢字のトリビア中心の本かと思ったら、想像以上にタイトル通りの本だった。
漢字ハカセと呼ばれた少年が本当に研究者となるまでが描かれている。
小学生のとき漢字に目覚め、中学生のときには研究を始めていて、それが本当に「研究」と言えるレベルのものなので仰天する。
天才肌というよりは、学究タイプ。研究対象にとことんこだわって調べ尽くし、そこから答えを導き出す。研究者以外の人生がこの方にあるだろうか?と思うし、本当に研究者になれるのかわからない中学生の段階でこれほどのめり込む息子を持った親御さんは正直言って心配だったのではないかとすら思う。
その真面目さ、正直さは文章から濃厚に伝わってきた。中学生のとき書いた自分のノートの誤字までそのまま活字にしてあり、普通なら直して書くのに(だって誰も気づかないよ!)。書いてあったら、間違いであろうと手を加えない研究者魂。
そんな真面目な笹原さんだけに、好きだった夏目雅子が伊集院静と結婚したとき、「すらすらと薔薇という字を書いたから(好きになった)」と言っているのを聞いて、「自分も書けるのに!」と大変悔しい思いをしたというところは笑ってしまった。
そんな笹原さんではあるがご結婚もされてご子息もいらっしゃるとのこと。どんな女性にどうやってアタックしたのか非常に気になるが、それは書かれていなかったのが残念だった。(主題から逸れるので仕方ないが…。)