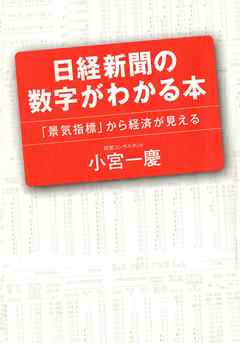感情タグBEST3
Posted by ブクログ
月曜日経の「景気指標」の読み方。
統計情報の間に関係性を見出して、自分で経済を読み解く。月曜の新聞は、ニュースが少ないので、あまり注目していなかったが、この本によって、月曜が楽しみになる。
指標の定義も、知らなかったことが多く、ためになる。
ビジネスマンとして、差をつけるにはもってこいの情報だと思います。
Posted by ブクログ
日経新聞の読み方としては画期的な名著。
日経新聞の数字に焦点を当てて、経済の本質を指標などから推定していくところは非常にわかりやすくよかったと思う。
基礎トレーニングを経た後に、日本国内編として
①GDP、②企業活動、③業種別の動向(半導体、鉄鋼、ゼネコンなど)、④雇用、⑤物価、⑥金融、を各章でみる。
海外編として
①超大国アメリカ、②ヨーロッパ経済、③アジア経済、④商品相場(現物、先物)を押さえる
パート2 実践トレーニング編では、
①「100年に一度の経済危機」と過去の比較、
②景気底入れの兆しを探す、
③中国は世界経済の機関車か
を考えて10指標(国内、海外)がある。
なかなか面白い本だったと思う。
Posted by ブクログ
ずっと読もうと思っていたが、先延ばしになってしまっていた。世読み終わって、やはりもっと早く読んでおけば。。という後悔だ。ずっと日経新聞は読んでいるが、この本を読むと全然読み方が変わる。またひとつ世界の見方、ニュースの捉え方がわかるようになる。小宮さんありがとうございます。
Posted by ブクログ
日経新聞の読み方の説明だけでなく、基準となる数字、数字の動きから読み取れる経済変化、他国と日本の経済の関わりなど、多岐にわたり読みやすく書かれています。
聞いたことしかないような単語も、わかりやすい定義から書かれており、講義を受けている感覚になります!
Posted by ブクログ
高校数学で大きくつまづいて(というかサボって)以来、数字に苦手意識のある私。
「日経新聞を毎日読んでいるという人の中でも、月曜日の日経新聞に『景気指標欄』があることを知っている人はあまり多くないようです。さらに、この景気指標欄をちゃんと読んでいる人となると、かなり少ないのではないでしょうか。」
小宮さんのこの言葉の通り、私は景気指標欄があることは知っていましたが、いつもGDPを確認するだけでした。
しかし、本書を片手に今月17日の景気指標欄を確認してみましたが、結構楽しい作業でした。小宮さんが述べるように、指標の横のつながりを見るのがおもしろい。
この著書が発刊されたのが2009年なので、本書内での日経新聞のサンプルは「100年に1度の不況」を示す数値ばかりなのですが、今月17日の指標では、製造業の工場稼働率指数(05年を100)が09年5月の72.8から10年2月には90.1まで回復していること、また、09年4月は140.3だった製品在庫率指数10年3月には102.7にまで減少(在庫が減った)し、それに連動して生産指数09年12月でプラスに転換、以後増加を続けています。
年明けから製造業大手の回復がとりあげられていましたが、それは数字で見ても確かでした。
しかし、07年度より実質GDPが未だ30兆円少なく、「これから」という時にギリシャ不安。欧州の緊縮財政に発展すれば、円高・ユーロ安で日本の輸出はまた落ち込んでしまう可能性もあります。またドル高・ユーロ安で米国の輸出も落ち込み、輸入を縮小されてしまうと、これまた日本の輸出は減少です・・・と、これは16日の日経新聞のネタ。
・・・とりあえず研修期間中に、こういう話題も正確に理解できるようにしたいです。
Posted by ブクログ
毎週月曜日に掲載される「景気指標」の読みかたを具体的に提案している。数字の羅列にアレルギー反応を示すのではなく、まずはその指標の定義を理解する。毎週数字を追ううちに、その値が示す意味、増減、歴史などを絡めて、どんなバックグラウンドがあるのか仮説をたて、一ヶ月後の日経平均とドル高などを予想できるようになる。
・ゼネコンが好調の時は、景気は低迷し始めている
・在庫の増え方にも善し悪しがある。
・広告扱い高は名目GDPとパラレルで動く
・企業は、業績が悪くなるとすぐに3Kを切る。
(3K=広告費・交通費・交際費)
・倒産件数が月間1500件を超えると危ない
景気指標のことはもちろんなのだが、「数字の読み方」という点においては、理系の論文の読み方にも共通する部分が多いと思った。
ポイント
1:定義を知る
2:主な数字を覚えて基準を作る
3:定点観測で時系列の変化を見る
4:一つの数字に関心を持つ
5:数字と数字を関連付ける
6:仮説を立てて経済を見る
7:数字を予測してみる
Posted by ブクログ
日経新聞の見方が変わる本。重要なことは数字に表れる。
自分自身の数字を読み解くための基準を決めて、定点観測して、仮説を立てて検証していくことが大事である。
Posted by ブクログ
日経新聞の経済指標の読み方がわかった。
また、経済指標が読めると経済の流れがわかる
非常にためになる本
これから毎週月曜日は指標を読む日になる
Posted by ブクログ
一見、無機質に見える景気指標欄から真の経済を考える方法が書かれている。数字を追う事で、仮説を立て、検証をするトレーニングを通して、論理的思考力を養う事が出来る。
Posted by ブクログ
日経新聞の景気指標を読むための基礎知識が説明されている。
合わせて、景気指標から、現実に何が起こっているか仮設を立てて、仮説を検証する事が重要と説いている。
経済を勉強し始めた私には、とても勉強になり、刺激となった。
読み応えがあった。
Posted by ブクログ
これまで、日経新聞の月曜日に掲載されている景気指標欄は素通りしていた。素通りならまだいい方で、存在していることすら知らなかったと言ってもいい。
その呪文にしか見えなかった景気指標欄の見方を、本書では丁寧に解説してくれる。
個別の用語の定義を詳しく解説してくれていることはもちろん、事例もふんだんに盛り込まれており、実際にどのように知識を生かして情報の分析を行えば良いのかという道筋も示してくれている。
手元に、最新の新聞を置いて、自分なりの仮説を立て、景気指標欄を読むようになったのはまぎれもなくこの本のおかげ。
出版された年代が少し古いので、時代背景の理解という点では少し物足りないところはあるが、リーマンショックなど、当時の様子を数字を眺めながら考えることができる点は、歴史的な知識を補充する、基準となる節目の数字を頭に入れるという意味でむしろ貴重に思える。
正確な知識、自分なりの仮説、自分なりの検証のプロセスを経て、少しずつ数字を通して社会の動きを理解できるようになると思う。
Posted by ブクログ
著者の小宮先生の講演に参加したことがあります。1時間30分の講演だったのですが、経済という、ある意味難しい話のはずなのに、あっという間に時間が過ぎてしまいました。もっと聞きたいと思ったことを記憶しています。
その時のお話の一部がこの本に書いてあります。大事なのは数字を読むこともそうなのですが、自分なりの基準をもつことと、間違っててもよいから仮説を立てることというのがよくわかります。ここには書いてませんでしたが、当然、その時に立てた仮説が正しいか検証することも重要ですね。経済を読めるようになることはもちろんですが、「考える」トレーニングにもなる内容でした。経済を知りたいと思っている方は必読の本です。
Posted by ブクログ
日経は購読しているものの、記事を流し読みしているだけで、経済に関する基礎知識の不足を痛感していたので、ちょうどいい、入門書になりました。
景気指標はほとんど見てなかったので、これからちゃんとチェックしようと、最近発売されたワークブックを購入して、ちゃんと勉強しようと思います。
Posted by ブクログ
うーん、初めてGDPの意味が分かった。
GDP以外にも色んな経済の数字の意味が分かりました。
たぶん高校の公民の授業なんかで習うような定義が載っているんだと思います・・・が、大事なのはそれぞれの数字が関係し合っているということですね。
じゃなきゃ、数字は単なる数字です。
いかに数字と数字の関係を紐づけて将来の経済を予測していくか、そして自分の行動に役立てていくか、それを学ぶためには非常によい本だとおもいますね。
Posted by ブクログ
日経新聞のマクロ指標の読み方と経済動向との結び付け方を基礎から学ぶことができる良著。
・名目GDP 実際の金額
・実質GDP ある時点の貨幣価値でみた場合にいくらになるか。
日本のGDPはだいたい500兆前後。
・日銀短観 景況感良いー悪い DIディフュージョンインデックス 変化や傾向を示した数値。量はわからない
・景気動向指数CIコンポジションインデックス 変化の方向と量がわかる。生産雇用などの指標のうち景気に敏感なものを統合したもの。
・優先的に削減される3K(広告・交通・交際)
・建設業の業績は世の中の景気よりも少し遅れて動く。
・ざっくりした大きな数字が頭に入っていると、新しい数字や別の数字との比較ができる。
・直接投資が赤字なのは、対外設備投資の方が大きいということ。
・一つの数字に注目し、その数字に関心を持つことが大事。
・日経景気インデックス 速報性が高い。日経BI
・米住宅着工数 景気低迷からの脱出の先行指標。年換算100万戸を超えると上向き。150万戸ペースで好景気。
・アメリカの貯蓄率もサブプライム後あがっていて、4%くらいで日本並。
・数字を予測してみる。将来の数字、。
・製品在庫率指数 と 生産指数や稼働率指数から景気の動向をみる。
・アメリカの成長 個人消費。
・消費者物価→マイナス デフレ
・中国1%のインフレが適正水準。
・消費支出 民需を表す
・機械受注 企業の投資意欲 設備投資指標
・貿易、通関 外需を表す
・公共工事 政府支出
・企業倒産件数 1500を超えると日本経済に深刻な影響
・米国個人消費 アメリカGDPの70%を占める
・中国GDP 390兆円 三十兆元
数値目安も示してくれていることがありがたい。
Posted by ブクログ
・P.75 所定外労働時間
日経新聞にこのような指標が掲載されていることにびっくりしました。残業時間削減によって、給与所得減少→個人消費減少→生産指数減少→雇用減少・・・。まさにデフレスパイラルですね。
・P.160 中国は米国債の最大のお客さん
この本で、最も学び&へ~の多かった箇所です。
『中国が対米輸出によりドルを大量保有する→中国企業は元に交換するため、ドル売り/元買いで元レートが上がる
→中国政府がレートの安定化のため、ドル買い/元売りを実施→中国政府は集めたドルを米国債で運用』
だから、アメリカは中国が米国債を購入してくれないと困るため、中国の貿易黒字を減少させたくない。
そして、中国も自らが米国債を買わないと、米国債の市場価格やドルレートが暴落して、自持ちの米ドル関連資産が目減りする。ほんまに持ちつ持たれつですね。非常に勉強になりました。
Posted by ブクログ
押さえておきたい10指標
1.国内総生産(GDP)
GDP=民需+政府支出+貿易収支
GDPから支払われる大部分が人件であるので、
GDPの額が増えることは、給料の総額が増えることに繋がる。
「民需」
2.消費支出(2人以上世帯)
GDPの55%強を支える「家計の支出」(<「民需」)を端的に表した数字
3.機械受注
企業の投資意欲を表す
「外需」
4.貿易・通関
「政府支出」
5.公共工事請負金額
政府の建設投資額の5%をカバー
■景気の底入れを判断
6.稼働率指数
企業の増産のタイミングを把握する
+鉱工業指数(製造業)企業在庫を判断
7.現金給与総額
一人当たりの給与の総額
8.消費者物価指数
デフレに進む危険サインを示す
9.新発10年国債利回り
不況下、デフレ時の金利上昇は最悪
10.企業倒産件数
日本だと月に1500件が危険域
Posted by ブクログ
日経新聞の月曜版へ掲載されている景気指標の読み方が分かりやすく説明されており、新聞の活用の仕方が広がった。世相の読み方など、教科書として活用できると思った。
Posted by ブクログ
良書。日経新聞の数字を根気よく追ってけば、経済のことが色々分かるというコンセプト。難しいことは書いておらず、非常に参考になる。やる気さえあれば、だれでも簡単に続けられる。
Posted by ブクログ
日経新聞の月曜日版の景気指標欄に特化したかなり
マニアックな本です。
この本が出版されていた当時は、日経を紙で購読していたので、
手帳に数字をメモりながら読んでいた記憶があります。
景気指標欄を読むだけで、1~2時間は平気でかかってしまいます。
現在は、日経電子版を購読しているのですが、
景気指標欄はじめその他の数値・指標はかなり残念な
感じです。
スマホでは、数字を見ることはできなく、PCでも
新聞のイメージを画面でそのまま見ることになるので
とても追い切れる感じではないです。
まあ、でも数字を追えるにこしたことはないですね。
Posted by ブクログ
経済指標の意味、その推移が示す動向がまとまっている。指標欄は膨大な数字の羅列につい読み飛ばしてしまうページだが、この本を通して読みとけるようになると面白いページに変わる。他の記事、ニュースとのリンクも意識すると数字力は確実に向上する。
Posted by ブクログ
景気指標から経済が見えるというサブタイトル。
時間がない時は景気指標の真ん中の文字だけ読んでいたけど
それでは×!ということ。今年はしっかり確認しよう。
<日本>
国内総生産=GDP=人件費:家計支出がGDP55%を支える。だから大事!
消費支出2人以上世帯前年比:8月から前年比プラスに転じたな。
法人企業営業利益:マイナス続き
日銀短観:若干マイナスが少ないか。
景気動向指数 CI composite index(景気に敏感な指数をcomposite)
:一致指数が昨年1年かけて改善
現金給与総額:前年同月と比べ昨年はすべての月でマイナス。
有効求人倍率:0.5前後 激減状況が継続。厳しい。
企業・消費者物価指数
マネタリーベース(貨幣の流通量):マネーサプライが膨張すると景気が良くなる
コールレート:今は0金利政策
新発10年国債利回り:不景気にこれがあがると設備投資が一層減退。
<米国>
GDP=世界の4分の1を占めて、かつ7割が個人消費
失業率=昨年1月7.6→先月10.0
雇用非農業部門=一昨年で307万人、昨年の11か月間で407万人の雇用が減少。
オバマ政権の350万人雇用創出では間に合わない!
米国の自動車・住宅着工も重要。
<中国>
やはり1人勝ちが続く。