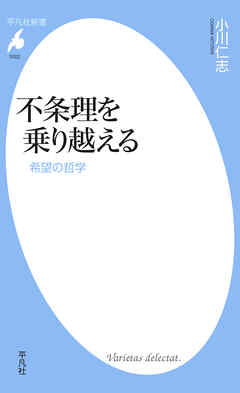感情タグBEST3
Posted by ブクログ
50歳になったら、専門スキルよりも教養や哲学を重視して大局観みたいなものとか賢者を目指そう(なんんかこう言っている時点で頭悪い子みたいだけど)と哲学をカジュアルに読める本をと思って読んでみた。
システムデザインを検討するときに、情報通信システムというインフラがあってその上に業種ごとのアプリケーションがのっかるように、経営戦略の環境分析(5FとかPEST)などを考える思考のインフラツールというか方法論として、哲学を活用しよう!といった感じのコメントを序章で著者はしているように思う。
ファリード・ザカリアの10個の教訓の解説やアフターコロナを事例に「何が残り、何が戻り、何が変わるのか?」という思考枠組みのアイデアを提示している点は、考えている人には当たり前な思考回路なのだろうけど、自分のおかれる環境分析を考える点でとても有益な話だと感じた。破壊は創造の第一歩なんて話もあるけれど、その点も本書はふれている。もう少し拡張してパラダイムシフトのメカニズムのような話をしていて「秩序の更新」と「けがれ」という言葉で議論している。けがれと汚れの違いをふまえて行動経済学や保険会社のCM、公衆衛生の分野で応用されて話題になったナッジの事例から世の中の変化について見解を示している。情報と意思決定の重要性についての指摘や、パラダイムシフトという価値観の変化には、「状態の価値」と「行動の価値」といったコンセプトツールを提供していた。SNSのデジタル民主主義に関する話題にもふれていて、群集心理やカリスマ性、単純化の話をなるほどと感じる解説もある。
雑多に有益だなぁと思ったことを羅列してみたけど、思考ツールの部品をいろいろ見せてもらった感じがするので、読者はこれらを組み合わせたり変形させたりしてカスタマイズして考えてくれ、ということなのだろう。そうすれば、世の中で起こっていることに対して自分なりの見解をもてるようになるんだろうなぁと思う。たまに読み返して思考のブラッシュアップに使おう。