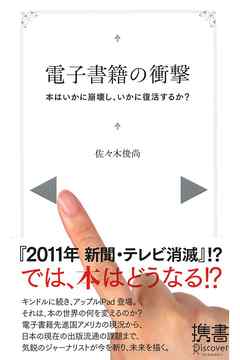感情タグBEST3
Posted by ブクログ
レコード▶CD▶ストリーミングと変遷してきた音楽を例に、電子書籍の登場により本も音楽の同じような道を辿るのかどうかが語られる。
ざっくりいうと、本の持つ一貫した情報量は音楽のストリーミングのような配信の形にはそぐわない。しかし、ビジネスの目で見ると出版業界の衰退は著しいのが事実である。 と言ったところですかね。
すごく読み進めやすい1冊であり、とくに音楽の変遷との対比が良い。終盤の「読者からすれば電子書籍に不利益などひとつも無い」とはほんとにその通りだと思いますね。
Posted by ブクログ
"電子書籍の登場により、本、出版業界はどうなっていくのか?どんな世界になっていくのかを研究した本とでもいえばいいか。
端的に言えば、流通の劇的な変化を伴うビジネススタイルの変革であり、読者の視点でみれば(まだ発展途上だが)ライフスタイルの変革である。
この本の中で、音楽業界で起こった出来事を電子書籍の登場と重ねて紹介している。
目から鱗が落ちた。ブライアン・イーノというイギリスのミュージシャンの言葉を引用している。
「もはや音楽に歴史というものはないと思う。つまり、すべてが現在に属している。これはデジタル化がもたらした結果のひとつで、すべての人がすべてを所有できるようになった。」(Time Out Tokyoより)
このコメントには多くのことが語られている。
詳細は、本文を是非お読みいただきたい。
私なりに解釈した内容をメモしておくと、昔はレコードやCDを購入し人ぞれぞれが生活に音楽を積み上げてきた。そして、その履歴が歴史であったが、現在はデジタル化した音楽がネット上にあるだけ。新曲なのか50年前の曲なのか意識せずに入手できる。また、アルバムというアーティストやスタジオが編集した一つの作品も、曲単位に入手できる為に意識されなくなった。もし自分が作り手であれば、考えさせられる現象だ。ビートルズの「サージャントペパーズ」「アビーロード」といったアルバムとして作品そのもの(曲順や曲と曲のつなぎ方など含めて作品)といえるような傑作が生まれたとしても、デジタル化された世界では、ユーザーが1曲ずつ気に入ったものをダウンロードすることも可能であるし、曲の順番もある意味ユーザー側が選択できることになる。
さて、電子書籍の登場で音楽業界と同様の動きをするのだろうか?本の世界では、パッケージ化されていたものが無くなり作品そのものが陳列される状態だと著者は考えている。どういうことかは、本書で確認を!
今後の展開が楽しみであり、読書が好きな自分もいずれ手にするであろう電子書籍。キンドルなのかiPadなのかは、今後の動向次第。もう一つ、この本を読んで興味を持ったのが出版業界のビジネスモデルがどうなっていくのか?この動向にも興味を持った。"
Posted by ブクログ
書籍(本と雑誌)産業の歴史の復習から電子書籍産業の歴史を、音楽産業と絡めながら分かりやすく書かれた本。
日本の音楽産業の現在の状況はグダグダですが、日本の書籍産業もかなりドロドロしてるな、と実感。
結局、電子書籍と紙の書籍のどちらも一長一短なんですが、e-inkを搭載した電子書籍リーダーの表示が紙のように表示されるので、流れとしては電子書籍な〜。
今読んでも、いろいろ考えさせられる本です。
Posted by ブクログ
具体的にしっかり描かれた本である
マイクロコンテンツ化:バラバラに分解されて流通する
それがまとめられてマッシュアップされる
機械単体で売れる事態は終わって、ネットワーク化またはエコシステムとして成立が必要
PF化されている。地主と小作人
Posted by ブクログ
電子書籍が世間に出回る=本が売れなくなる、という風な説明がされたりすることにどうしても納得できなかった僕には明確な答えとして提示された本だった。いい書籍でした。プラットフォームの話はとてもわかりやすく、その強かな戦略によるappleの音楽業界の席巻からの例示はわかりやすかった。
Posted by ブクログ
電子書籍の本なのに、音楽配信の話がやたらと出てくる。(あと、最後にはケータイ小説の話も。)
音楽の分野で進んだデジタル化・アンビエント化・マイクロ化・フラット化・プラットフォーム戦争…etc.というものが、電子書籍の分野でもあとを追っかけるように出てきますよ、という論旨だからだ。すごく分かりやすいし、納得がいく。
音楽配信をチェックしとけば、電子書籍の将来が分かる、という視座を与えてくれるので、今後もそういう見方をしていけばいいわけだ、な、と。
Posted by ブクログ
電子書籍のこれまでを楽曲配信の歴史と絡めて考察し、これからの電子書籍がどうなっていくのかが書かれた本。『本はコンテンツとしてでなく、コンテキストとして読まれる』『書き手と読み手がインタラクティブとなり、ソーシャルメディアをコンテキストとしてコアなファンに読まれる』というような、従来のマスな書店販売とは異なった配信・読み方がなされていく(すでにそうなっている)、と書かれている。活字中毒者のわたしとしても、これから電子書籍のプラットフォームがどうなっていくかは関心事であり、日本の出版社もこうした流れに感情的に抵抗するのではなく、先んじて流れを作っていくくらいの意気込みが欲しいと思った。
Posted by ブクログ
コンテンツをとりまく状況が変わってきている。
出版もそれは例外ではない。
時代の潮流が、出版業界にも、すぐそこまでせまってきている。
そのなかで、出版ビジネスは、コンテンツのありかたはどう変わっていくのか?
この本は、その指標となる一つになると思う。
また、今まで積み上げてきた出版の歴史もふまえて紹介されていたのがよかった。
でも、一方で、紙の本は永遠になくならないと思う。
やっぱり紙の重みは、物質の重みは重要だと思うから。
Posted by ブクログ
電子書籍に関するトップジャーナリストだと思う。情報収集が広く、今後についての洞察が深い。確かに文章を読むという経験自体がかなり変わりつつありますが、今後はどこに向かうのかという描写に説得力があり、大変面白かったです。
Posted by ブクログ
電子書籍を持ち運んで読むことができるデバイス、キンドル。
そして、パソコン、携帯電話に続く新たな情報端末の形として注目を浴びるipad。
これらの機器が新たな情報の時代を築き上げていこうとするなかで、電子書籍が急増することが予想されているが、この電子書籍は社会にどのような変化をもたらすのか。
この新書ではパッケージからオンライン配信に移行していった例としての音楽についても言及しつつ、本の未来を述べている。
電子書籍がどんな特徴を持つか、日本の出版や書籍流通の現状にどのように関連していくかなどを詳しく、わかりやすくまとめていていい。
ただ、サブタイトルにある『本の復活』については最後まではっきりとした答えがないように思えるので、紙媒体の本がどうなるのか?に興味があると少し的外れな感があった。
Posted by ブクログ
via @ikues 。
新書っぽく非常に分かりやすく書かれている。実は流れをよく知らなかったので、このくらいのやつが調度良かったかも。Readerについてはちょっとしか触れられてないね^^;
Posted by ブクログ
筆者の既刊と同じく未来予想図が先走っててマスを殺し過ぎな感はあるが、それに至るまでの道筋は丁寧。日本の出版流通の経緯に加えて海外の出版事例の紹介も多く、電子書籍のこれからを考えるには純粋に役立つ一冊。
Posted by ブクログ
佐々木俊尚さんの本で一番好き&的を射てる本。
2010年でのこの内容には先見の明がある。
ただ、本当の衝撃を受けるのは今のアメリカの様に電子書籍が紙媒体の本の売上を抜くようになってからだと思うので2014年が元年あたりだと思った。
Posted by ブクログ
2010年発行で、タブレット端末が発売されて、タブレットをネット端末よりも、電子書籍端末としてとらえているが、基本的にはしっかり時代の波をよんでいるのではないだろうか。
前半は音楽業界の盛衰の歴史と、iTunes store を絡めて、同じような波が出版界にも来ているとしている。そのうえでプラットフォームと、コンテンツの量が重要なキーになると考えている。
今後の出版界はセルフパブリッシングになると考えている。元月刊アスキーにいただけあって、編集だけではなく、IT関係の流れもよく知っているようであった。
Posted by ブクログ
電子書籍について丁寧に書かれている本。
電子書籍はこれからどうなるのか、
電子書籍によって紙の本はどうなるのか、
について、音楽のiTunesを例に読み解く。
私も電子書籍の普及に
「大量のできの悪い本が良本を駆逐するのでは」
と一抹の不安がありましたが、
それはグーテンベルクが活版印刷の技術を発明したときにも言われたことで、
今現在を見れば彼の発明がどういう結果を残したかは言わずもがな。
日本版キンドルの登場を心待ちにしています。
Posted by ブクログ
2010年前半に出た本ですが、なぜ電子書籍の普及が遅れているのか、電子書籍時代がどんな時代になるのか、について説得力のある見通しを示してくれています。にしても2年経ってもまだ立ち上がらない電子書籍市場。。この本に描かれる本と読者の出会いが実現されるのはいつになるのやら。
Posted by ブクログ
IT系の業界動向の分析には定評のある佐々木俊尚の一冊。
電子書籍の未来を占うのに、音楽業界をたとえに出すところはさすがの一言。
今後、出版業界も音楽業界と同様、特定の流通業者が握る未来になるのか?
Posted by ブクログ
津田さんの「音楽は〜」を読んだあとだったので、
その本版という感じで読めた。
途中までは「ふんふん」って感じで読んでたけれど、
文脈とかが出てきて、ひとつにまとまったときに「おおー」ってなった。
そして、これからがすごくたのしみになった。
----------
・コンテンツはアンビエント化していく。
→私は所有にこだわりがないので確かにって思った。
・ケータイ小説はコンテンツではなくコンテキスト(文脈)
→私がしたいのもここかもしれない
・マイクロインフルエンサーから情報を手に入れていく
→確かに今ブログや知人からいい本いい音楽をしることが多い。
Posted by ブクログ
★電子書籍で読んだ
【ポイント】
電子書籍だと、マーカーがひけない。
メモ帳を立ち上げて、読みながらポイントの入力。ちょっとたいへん。
で、今回はキーワードのみ
コンテキスト(書籍文脈) アンビエント化 リパッケージ
取次ぎのデータ配本
←→「本棚は管理するものではなく、編集するものだ」
4章 出版文化
情報が出版社やテレビ局、新聞社に独占されていて、過剰な冨がもたらされていた時代のなごりにしがみつき、その時代に蓄積された富で飽食し、惰眠をむさぼるのは自由です。
そもそも、検索できない情報はもはや生きた情報とはいえない。
まとめ
?タブレットの出現
?タブレットで、本の購入、読むぷらッとホーム
?本のフラット化
?セルフパブリッシングのサービス
?電子ブックディストリビューター
?電子ブックのアンビエント化
そのコンテキストが、ソーシャルメディアに流通していく
?多くのマイクロインフルエンサーと無数のフォロワー
?かつて音楽はパッケージ化されて、パッケージの感触こそが音楽の属性
(レコード盤とジャケットの一体化)
?パッケージが剥ぎ取られ、音楽とリスナーがダイレクトに接続
Posted by ブクログ
感想
紙と電子の対立構造という幻想。我々消費者はこの二つを対立させることなく、使い分ければ良い。電信書籍の登場はあくまで選択肢を増やしただけ。
Posted by ブクログ
“電子書籍”が普及して紙の本がなくなるかと言えば、答えはNOでありYESである。。。
人間には手触りが必要である、移ろいやすい電子ではなくまとまったブツと思考が必要である、本屋での逍遙が必要である、あれどっかにあったよなと本棚を、あるいはページを繰って探し回る無駄な時間が必要である…
などと、私ら紙の本体験がある世代は思い、NOと答えるだろう。そして私らの目が黒い間、紙の本がなくなることはない。
だがしかし。
生まれた時からタブレットPCしか触ったことがなく、完全にその世界に最適化された“本”とその読み方しか知らない世代は、当然ながらYESと…いやそうとさえ言わないのではないか。紙の本? なにそれ美味しいの?
「本を検索エンジンだけで探すようになるとたこつぼ化する」とか「本がバラバラにされて消費されるようになってしまう」と“本”の行く末を危惧する向きがあるそうだが、そういう心配はまったく無意味ではないだろうか。ツールが変わり、世界観が変わり、ニーズが変わり、生活体験が変われば、そこには世代間の断絶だけがあり、「幼年期の終わり」があるのみだ。
どっちにしても、いずれ出版文化の衰退とか業界・団体の沈降は(TVや新聞、その他既存の権威と軌を一にして)否応なく襲って来るのであり、ワシらの世代の知ったことではない。
Posted by ブクログ
ケータイ小説は、コンテンツではなくコンテキストだという一行は考えさせられた。村上春樹の『アフターダーク』、『涼宮ハルヒの憂鬱』、『恋空』の一説を比較し、文学とオタクとヤンキーとコンパクトに述べたところも、納得。他にも、なぜ日本の出版界が再販制になったか、その歴史的経緯など、個々には興味深いところは散見された。が、ふだんから著者の言動をtwitter などで読んでいるためか全体としては新味が感じられなかったのが残念。麻野としては、前に読んだ、『マスコミは、もはや政治を語れない』の方が衝撃大きかった。しかし、あまり電子書籍のことに詳しくない人には適書だと思う。""
Posted by ブクログ
概要
電子書籍が紙の本に変わるあるいは、紙の本を補完する社会インフラとして定着するためには
1.デバイスの普及→ipadとキンドルは何を変えるのか
2.本を購入し、読むためのプラットフォームの出現→プラットフォーム戦争
3.本のフラット化(プロとアマの属性がはぎ取られる)→セルフパブリッシングの時代へ
4.電子ブックと読者との新しいマッチングモデルの構築→日本の出版文化はなぜダメになったか
の4つのピースが必要とする。
こうした中で、
出版社はスモールビジネス化されたエージェント的なビジネスへと舵を切っていく。
「良い本であう空間」をきちんと構築できる店舗は、コミュニティの中心地となってみずからをソーシャルメディア化していくような方向へ進化していく。
と言うのが本書の結論である。
Posted by ブクログ
この本が出たのは2010年、2年経過した今でも電子書籍は浸透しているとはいえないと思う。状況はあまり変化していない。私の周りにも電子書籍リーダーで本を読んでいるという人はあまり見たことがない。これからどのように出版業界が変遷していくのかが、この本に書いてあるように重要な鍵であるのは間違いないと思う。
Posted by ブクログ
BookReader を購入したのはよいものの、肝心要のソフト(要するに本そのもの)を買ってみようと Reader's Store を訪ねてみても現段階での出版冊数は少ない(とくに KiKi のアンテナに引っかかってくるものは少ない)うえに、紙もインクも流通も必要ない割には高く感じられる価格設定に疑問を抱かずにはいられない昨今。 電子書籍の登場で今後何が起こり、世の中がどんな風に変わっていくのかを考えてみたくてこの本を手に取ってみました。 でもね、そういう KiKi の知りたい「これから」のことに関してはさして示唆があるとは思えない本でした。
まあ、このての本には賞味期限があるのは致し方ないことだけど、2010年に発刊されたばかり・・・・ではあっても網羅されている情報が今となっては古くなっちゃっているので、どうしても新鮮味には欠けるうえに、著者の経歴がジャーナリストであってアントレプレナーではないためか、将来のビジネスモデルに関する示唆のようなものは皆無(要するに現状分析程度)で終わっちゃっているんですよね~。 この本の副題が「本はいかに崩壊し、いかに復活するか?」となっている割にはその崩壊の過程も、ましてやその後不死鳥のように蘇る可能性に関してもまったく触れていない・・・・・と言っても過言ではないように感じました。
(全文はブログにて)
Posted by ブクログ
フラット化か。フラット化する社会も読みたくなった。とりあえずPDFでもソーシャルリーディングできるデバイスが欲しい。あとカイトランナーが読みたくなった。