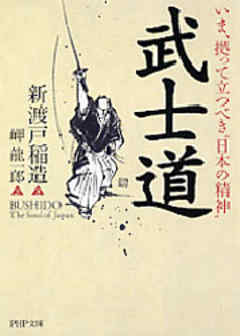感情タグBEST3
Posted by ブクログ
武士道という日本国民に根づく思想を体系化した唯一の思想書。
武士道は日本人の中に深く根付いている考えであるが、教義もないため成文化されていない。権力を持っている者ほど質素に自分を律して生きなければならないという武士の考えが根底にある。
武士道の根幹を成すのは「義」である。これは過去の偉人である西郷隆盛や吉田松陰にも表れており、不合理だとしても正義を通すことである。自分への不都合や時には生命よりも自分に対する信念、正義を優先させる。これは切腹という文化にも表れている。
自分の利益よりも正義を優先する「義」が最も難しく、それを武士は常に守ることを要求されてきた。それにより育まれ、それを見ていた大衆にも伝わったのが武士道である。
富や名声よりも「名誉」を最も重んじる武士道、この信念を資本主義の中でも忘れてはならない。世相も変わってきており、軽視されつつあるがそれこそが日本人の持つ誇らしき思想であると感じる。
Posted by ブクログ
この本は日清・日露戦争中、日本の武士道精神を西洋に紹介することで、日本の国際的地位向上を図ることが狙いで、いわば「広報」的な目的を持って書かれた本。
世界で日本といえば「サムライ」という言葉が出てきますが、この本によるものだったのですね。
なんならこの本によってルーズベルトが日本びいきになり、日露戦争の調停役になったというのだから胸熱。『武士道』の「その功績、三軍の将に匹敵する」と後書き解説にも書いてあります。そんな本をすっかり平和な時代の日本で読んでいる、というのも感慨深い。。。
ちなみに岡倉天心の『茶の本』も同じ時期に日本の文化や精神性を広めるために書かれている本です。日本が近代化を進め世界と対等になるために、自国の文化を発信する。海外の技術や文化をなんでもかんでも取り入れていただけではなかったんですね。
ちなみに『武士道』は「切腹」など海外から見たら独特に見える作法の元となる考え方を、海外で有名な書籍などから同じもの(あるいは対比できるもの)を引用して説明しているので、海外の人からも分かりやすかったと思います。
切腹の様子を描写しているところはぜひ読んでみてください。「はわぁゎぁ〜(T ^ T)」となります。
Posted by ブクログ
日本の自己啓発本の原点
現代の自己啓発本では主に、「周りに影響されないブレない自分を持つ」、「すぐに行動する」「自己肯定感を高める」、「人徳を積む」、「承認欲求について」、「部下と上司の関係」等の内容が主であると感じた。
武士道はこれらの問題について、義、勇、仁、礼、誉、忠の項目で説明しており、この本は日本の道徳の根源は武士道である、と紹介する本かと思いきや立派な自己啓発本であると気づいた。
Posted by ブクログ
和製聖書というべき日本人の心をまとめた本
「道徳教育には宗教教育が基になる、貴国は宗教がないならばなにを柱に道徳教育をしているのか?」という質問に対し著者が答えをまとめた。
打算的な世の中の今こそ読んでもらいたい。
日本人ならば必ず読むべき本です。
Posted by ブクログ
封建制が先か、武士道が先かは分からないけど、封建制が無くなり民主主義が採られる時代になった今では、武士道の形骸化した部分だけが残っている。これを読むことで、今でも存在する、違和感を覚えるような伝統や慣習の解像度が上がった。
Posted by ブクログ
武士道とは何か、日本の武士道精神そのものと、それが日本人の心や動作に浸透してきた背景が理解できる。著者が明治維新後30年くらいで外国人向けに書いたという視点で意識して読むと良いと思った。
時代が違うので当然価値観も違うが、少なくとも今でも日本人の心に受け継がれてきているものもたくさんあり、またそれは武士道の元になっている神道や仏教、儒教から今に受け継がれているものも多い。そういった先人の教えを武士道の視点から学べることはためになる。
学びメモ
・知識というものは、これを学ぶものが心に同化させ、その人の品性に表れて初めて真の知識になる。知識はそれ自体が目的とはならず、あくまで知恵を得るための手段である。陽明学の知行合一。
・文づかいや声音になんの乱れも見せないことは、心の広さであり、余裕である。そうした人は慌てることも混乱することもなく、多くのものを受け入れる余地を持っている。
・礼は寛容にして慈悲深く、人を憎まず、自慢せず、高ぶらず、相手を不愉快にさせないばかりか、自己の利益を求めず、憤らず、恨みを抱かないもの。心がこもっていなければ礼と呼べない。
・負けるが勝ちという格言。これは、真の勝利は乱暴な敵にむやみに対抗しないという意味。
・武士道が浸透していく中で、日本全体の道徳律として提供されていき、大和魂が象徴する言葉になっていった。
・日本に変化をもたらした行動力の源泉は、劣等国として見下されることに耐えられない名誉心からきている。
Posted by ブクログ
今日の会話の中で私たちは、「彼は侍だ」とか”大和魂”という言葉を使うことがある。しかし、それが何を示すのか明確な定義を教わることはなく、経典のようなものも少ない。だから、著者である新渡戸稲造はこれらを日本人に受け継がれる精神”武士道”として、まとめたのである。
孔子の教えである「五常の徳(仁・義・礼・智・信)」または「八つの徳(忠・孝・悌)」が武士道の基盤となっている。義は人の心、礼は礼儀作法・所作を指し、仁や義を型として表すことである。仁は人の良心、慈悲の心のことを言う。伊達政宗は「義に過ぎれば固くなる。仁に過ぎれば弱くなる。」の言葉を遺している。仁義のバランスを取ることが大事であると説いている。
上記の特徴は、よく日本人に言われていることだが、その他にも特筆すべき点があった。これが名誉、忠義である。これらは、心の強さを指すものとして私は考える。名誉は、いかに恥を感じないようにするかと言い換えられる。自分の心に正直に生きることがより強い武士であった。忠義は、主君の義理に対する恩返しである。時には、家族よりも優先させるべき事であった。これらの名誉と忠義の強さが誠となると私は感じた。すなわち、誠とは面子を保つことである。
武士道は、強烈な覚悟と誇りによって成り立っている。その一つに克己心がある。敵前でもけっして怯まず殺される瞬間まで毅然とした態度で平静を保つのが立派な侍であった。また、切腹もこれらを表す姿勢である。切腹は罪状として存在していたそうだが、逃げることもできる状況下であった。それでも、切腹を受け入れるのはそれなりの責任を感じ、自らの腹の中が潔白であることの証明を示す行為だったそうだ。正直、この描写では常軌を逸していると思ってしまった。
本書では、ちょっと表現が強い場面があって、苦手な人もいると思った。それでも、今私たち日本人が持っている礼儀正しさがなぜ世界から称賛されているのか、外国と何が違うのか知ることができるので、一読すべきである。武士道は、一見誠実すぎて損をしてしまう考え方かもしれない。しかし、長期的に見たときに最後に笑うのは精神力、己の気持ちが強い者であると感じた。これからは、多様性の時代がやってくるが、武士道をどのように馴染ませていくのか考えていきたい。
Posted by ブクログ
外国人に向けて日本の武士道を解説する内容なので、海外と日本の比較する場面で分からない例えがあった。
日本人のオリジナリティでもある武士道について、体系的に説明されていた。
Posted by ブクログ
仏教は、運命を受け入れ、危険や災難を目にしてもストイックに落ち着き、生に執着せず、死に親しむ心をもたらした。
サムライ"義“は、自分の身の処し方を、道理に従い、ためらわず決断する心をいう。
死すべき時に死に、討つべきときに討つこと
勇敢な人は優しい人
愛のある人は勇敢な人
礼は、長い苦難にも耐え忍び、親切で妬みの心を持たず、誇らず、おごらず、非礼を行わず、自分の利を求めず、憤らず、慢心しない
人を泥棒呼ばわりすれば、彼は泥棒となる
「つまらないものですが」は、つまらないものをあなたに贈る、という物目線の言葉ではなく、
「あなたはいい人だからどんなものであってもあなたにふさわしいといったら失礼にあたる」という気持ちを表している
Posted by ブクログ
「武士道」には、日本人の国民性の特徴が詰まっているなと感じた。美化しすぎな印象はありつつも、理想を追い求めたものだからこそか。
比較対象として、騎士道、ドイツのゲミュート、英国のジェントルマン、フランスのジャンティオムなどが挙げられているところでフムフムと思った。
武士道を形成する様々な概念について言語化されたものを読む機会はあまり無いので、あらためて文章にされたものを読むと、なるほど納得できるものがあった。
漢字一文字でいうと「義」に集約されるものが特徴的かな。
Posted by ブクログ
知行合一という普遍的道徳を説いた言葉があり、武士道精神の本質的原理と一致するらしい。
その精神は日本が近代化を果たす原動力となり、現代では役目を終えて消える灯心となる。
何事も終えるタイミングを誤らなければ美徳化され残り続けるだろう。
Posted by ブクログ
日本人が日本人観を客観的に学べる。5年に1回くらいで一生そばには置いておきたい。海外でも知られている本なので、知っておくとなぜ日本人は他の国と違うんだ?という問いに答えられる。
Posted by ブクログ
日本人とはナニモノか。西洋思想に半端にかぶれてしまった今、まさに再学習するのに良い。
武士道の根本はノブリス・オブリージュにある。なるほど言われてみるとそうである。昨今嘆かわしい事態が引き起こされている。ネットでのヒトの振る舞いもなかなか酷い。
武士道精神を学び直し、現代の社会様式に合わせて更新する。これが必要だと痛感する。
Posted by ブクログ
この本は、「武士道を体系化した思想書」です。
武士道を西洋文化、キリスト教等と比較しながら、丁寧に考察している本であり「日本人の元!」が、ここにあるように思いました。
ぜひぜひ読んでみて下さい。
Posted by ブクログ
新渡戸稲造さんが日本人の伝統的精神について、外国人向けに書かれた本作。聞きなれない言葉が多く、わたしには少し読みにくい箇所がいくつかありましたが。。。
平成生まれのわたしでも共感できるところがいくつかありましたが、時代劇などを見ていても感じることですが、本当に同じ日本人なの?と思う箇所もたくさんあり。。。
今の資本主義経済やグローバル化が浸透しきった世の中にあって、武士道精神は馴染まない部分が多いですが、日本人の伝統的な精神であるこの武士道について、日本人として決して忘れてはならず、自分の子供たちにも伝えていきたいなと思いました。
Posted by ブクログ
無駄な余談に走ることがなく、武士道という漠然としたものをキーワードに分けて定義付け。そして、ビックリするほど理路整然として客観的な見解!不安げにあたりを見回す読者に対してスマートにエスコートしてくれるジェントルマンに見えてきてしまった。
加えて日本だけでなく、海外の学者や聖書の言葉まで引用しており、武士道への理解を深めて貰おうとする工夫の仕方が素直に凄かった。次々と繰り出されるもんだから注釈を見るのに忙しかったし、相当な読書量やなと脱帽。さすが国連事務局次長!
(天皇を「天上の神の代理人」と表していたのには時代を感じた)
個人的にささったのは「名誉」の章。(英語版では“honour”)`
間違った解釈かもしれないけど、ここでいう名誉は今の汚らしいニュアンスの名誉とは違う気がした。筆者曰く名誉はこの世の中において「最高の善」で「若者が追求しなければならない目標」との事。名を成すまでは帰還せず、そして勝ち取った名誉は年が経つにつれて大きく成長する。
若者の純粋で崇高な志がいずれ彼らの夢、名誉に辿り着くのかと心にストンと落ちた。
一方でこの志に「野心」が混じると今の汚らしいニュアンスになってしまうのかな、とも。
厳めしい章もあったけど最終章の結びも含めて武士道は情緒に溢れ、繊細な部分も併せ持っていた。そろそろチャンバラのようなイメージは切り捨てておきたい。
Posted by ブクログ
新渡戸稲造1899年M32米国発表。日清戦争で眠れる清国に勝利したが未だ西洋から幼稚で野蛮と思われていた日本を武士道を通して正しく理解させようとした本書。武道鍛錬、禅、和歌、茶道、儒教を学び銭勘定を嫌い「仁、義、礼、智、信」義の為なら死ぬことさえも恐れない勇猛果敢なフェアプレー精神で知識と行動を
一致させることを目指す生き方は西洋でブームになり当時の米国大統領は感動し家族や知人に配ったらしい。
Posted by ブクログ
長く色々と書きたいのですが簡潔に。
大河ドラマをきっかけに読みました。
「青天を衝け」を観ていると、その中で理解できない場面が多々あった。自殺行為の計らいに強く志願する青年たち。「大義のために死ぬことは本望だ」、その心が私にはピンと来なかった。その他にも、武士の上下関係や絆、武家の姫の振る舞い等、現代のものとはかけ離れていて、この本を読まなければその時代背景をはらんだ本当の意味はわからなかったと思う。
これまでに、人との考え方の違いや振る舞いの差はどこから来るのだろうと考えた時に、この武士道が関わっているのではないかと未読にも関わらず思っていた。例えば「夜に爪を切ること」や「調子に乗ると痛い目をみる」と言った縁起が悪いことを平気でする人としない人。私は後者であるが、前者はどうしてできるのかと考えた時に、都会育ちか田舎育ちか、という理由に行き着いた(あくまで個人的な見解)。私は田舎育ちであり、幼い頃から祖父母などから教えられていた言い伝えにより、縁起の悪いことは避ける傾向にある。そしてその元は地域の言い伝え、昔の文化、いわゆる日本の武士道のようなものなのか、と。
直接的な関係はさておき、親を大切に思う心や自分を戒める武士的な心持ちは共通しているところがあった。
大河ドラマ好きには強くお勧めする。と言っても、多くの大河ドラマ好きの人は私と違い、そもそもこの武士道的思考や時代背景を理解しているものなのだと思う。笑
それに加え、人はなぜそう考え、そう言い、行動するのか。その由来のひとつに触れることができる。私はそれを知りたくて、この本を読んだのだとも思う。
Posted by ブクログ
義、勇、仁、礼、誠、名誉
日本の武士道たる考え方は、
海外の宗教で学ぶ教育基盤の様です。
ベースとしては、やはり儒教のエッセンスが入っているようです。
日本人の文化としても改めて学べて良かった。
Posted by ブクログ
自分にとって、わかるような、わからないようなものである武士道が、200ページ程度で簡潔に説明されている。
納得できる内容もあれば、そうでない部分もあるが、内容は普遍的で、時代が変わっても学べる項目が多い。
◾️義は人の道なり
◾️義を見てせざるは勇なきなり
勇気の精神的側面は沈着、すなわち落ち着いた心の状態となって表れる
真に果敢な人間は常に穏やかである
決して驚かされず、何事にもその精神の均衡を乱されない
心の広さを余裕と呼び、それはさらに多くのものを受け入れる余地である
◾️義に過ぎれば固くなる、仁に過ぎれば弱くなる
もっとも勇気ある者はもっとも心優しい者であり、愛ある者は勇敢である
◾️礼の根源は、他人の気持ちを尊重することから生まれる謙虚さや丁寧さ
◾️真実と誠実がなければ、礼は茶番であり芝居である
◾️武士道の枠組みを支える柱は「智(知恵)」「仁(仁愛)」「勇(勇気)」
Posted by ブクログ
新渡戸稲造さんの英文を日本語に訳したもの。日本人を西洋の人たちに説明している、興味深い本。現代人のブレブレな生き方に対するアンチテーゼでもあったり、内弁慶的な日本人気質の大元を辿るようなむず痒さもあったり。
Posted by ブクログ
3回目の挑戦にて、初めて読破。
全体通してやっぱり難しくて所々わからない部分があったけど、共感できる部分もあった。
出版当時の日本人の道徳的規律がどこから生まれ、どのように武士および民衆に広がっていったかが記されている。
義、勇、仁などのテーマで、それぞれ当時の日本人の精神的構造が説明されており、現代にも通ずるところが見つけられる。
Posted by ブクログ
「武士道」というと21世紀を生きる自分とは関係のない歴史上の概念と思ってしまいがちだけれど、その内容は特に目新しいものはなく自分が普段から意識しているものばかりで、改めて自分は日本人なのだなと感じた。
Posted by ブクログ
■感想
仏教とか神道とか興味ありますね
絶対と自分を調和させる、いいですね
座禅やってみたいです。体験してみたいですね。
汝自身を知れって真理過ぎるだろ
知識というものは、これを学ぶものが心に同化させその人の品性に表れて初めて真の知識となる、ということ
→その通り過ぎる、知識として手に持ってるんじゃなくて、自分の自然の行動として表れて初めて意味を持つ敵なことだよね。
息をするようにできるってことだよな。
知行合一
高校生の時もこれってマジ大事!って思った気がする
絶対思ってたわ
貴族(力あるもの)を商業から離しておくことはある程度ごうりてきなのかもしれないな
お金持っている人が強い社会になっているもんな
これが当たり前じゃない世界もあるってことだ。
封建制度にも一定の合理性があるんだわ
ちょっとわからないけどさ
侍は本質的には行動の人であるからだ (第10章)
有機を養うのに役経つ場合に限って必要とした 知識は
もし1年で辞めるとするならば、目標とかどうでもいいし、評価とかどうでもいいんだから、
自分がやりたいことベースで考えたほうがいいんじゃん?
やる事やって、やりたいことだけやって、やめちまった方がいいんじゃねえの?
とか思ってたりするわけです。
日本人はほかの民族よりもはるかに多くの朝に何倍ももの度とに感じやすい性質をもっていると
→そんなことあるんかな?繊細な心キビとかは大事にしているんかな、わびさびとか
でももっと欧米とかは素直にすごいと機や楽しいときは喜ぶし、感情を表に出していくよね
こうしないと自分の気持ちにどんどん気づかなくなっていくと思うんだけどそれとはまた違うのかな
って思ったら次に書いてた
自然に発する感情を抑えようとすること自体が苦しみをともっているからである。
感情を顔に出すのは男らしくないとされた
→俺はこれをかっこいいとはもう思わないよ
感情を出していくやつの方が絶対かっこいい。素直に感情出せるやつの方がかっこいいんだから
思想隠す技術
→何でこれがいいんだろうか?
日本人にとっての笑いは、逆境によって乱されたこことの平衡を取り戻そうとする努力を、うまく隠す役目を果たしているからである
つまり笑は悲しみや怒りとのバランスを取るためのものなのだ。
→わからんでもない
逆に出さないから
その心の機微に気が付けるみたいなこともあるかもしれないね
その気持ちを詩にしたりとかして、違う表現方法に頼ってきたって言うのはあるかもしれないね
でもそれは表現方法の違いに過ぎなくて、日本人が感じやすいかって言われたらそうではないだろうっと思うよ。
絶対出していった方が良いもん
ポジショントーク多い
聞きたないねんそんなの
日本人の過度に感じやすく、激しやすい性質についても、私たちの名誉心にその責任がある。そして外国人からもよくして切れるような「日本人は尊大な自負心をもっている」という言葉も、これもまた名誉心の病的な行き過ぎによる結果であると言える
→自負心持ってるか?よくわからん。
人の目を気にして自分の物事言えない人の方が多いと思うんだけど。
それは自負心とは違うのか?
理想は自己を磨く宗教
→これは本当にそう、何か目指すべき像があるからこそ力が湧いてくるのであって、無いと何をすればいいのかわからない
結局、何を信じるか。何をしたいか。どうなりたいか。だ
それは自分の内面から出てくるものであっても、与えられるものであってもいいんだ
後者であればとても楽だ。宗教が無い日本はとても不親切といえるかもしれないな。
何も秀でないことを強制される。何も考えないことを強制される日本は優しくないかもしれないな。
Posted by ブクログ
私は、「礼」の章がとても好きです。
非常におかしいと思えることも、相手を思ってのこと。
贈り物を渡す時の欧米と日本の台詞の違いは、改めて理解できた気がします。
今の日本、そして日本人のどれほどの人達が良きにしろ悪しきにしろ、武士道の心を持っているのでしょう。
私は嫌いではありません。
Posted by ブクログ
岩波版に比べると読みやすい文章になっており、自身の道徳の基礎に「武士道」があることをぼんやりと確認出来た。
ただ、内容が思った以上に深く、かつ、発散していて、一回読んだだけでは理解しきれなかった。
繰り返し読んで、理解を深めたい。
Posted by ブクログ
自分の頭が悪すぎて難しすぎる。笑
すごく心に刺さった言葉。
「じっさい日本人は、人性の弱さが最も酷しき試煉にあいたるとき、常に笑顔を作る傾きがある。-中略-逆境によって擾されしとき心の平衡を恢復せんとする努力を隠す幕である。それは悲しみもしくは怒りの平衡錘である。」
失敗した時、焦った時、逃げたい時、傷付いた時、
誤魔化すようにいつも笑ってしまう。
それを強さと履き違えていたけど、違うのかも。
もっと早く気付きたかったな。
Posted by ブクログ
かつて五千円札の肖像となっていたことで有名な新渡戸稲造。そしてこの『武士道』も国際的に有名な作品ですね。少なくとも名前は結構聞きますよね。
こちら、一言で言えば、日本人論です。もっと詳細に言えば、日本人の道徳論です。
明治の開国以来、それまで明文化されていなかった日本人道徳論を文字に表した初めての作品であろうと思います。
ただこれ、理解するのはなかなか簡単ではないと思います。
まず、日本人が意識せずに持っている中国の儒教的思想を知らないといけません。本書では、義、勇、仁、礼、誠、名誉、忠義、等々が語られます。これらが大まかにどのような意味なのかを知っていないとちょっと分かりづらい。ってか、学校でやりませんよね、こんなの!
さらに、これら日本人道徳観の具体例として多くのエピソードが語られます。市井の武士の話から、太田道灌、源義家、林子平、新井白石、などなど。人選が現代人からすとちょっとビミョーな気もしますが。
で、この後がすごいん。これら具体的エピソードは実は西洋の中にも見られるものだ、ということで、プラトン、シェークスピア、ニーチェ、バルザック、モンテスキュー、ヘーゲル、ソクラテス、ドン・キホーテ、ディケンズ(オリバー・ツイスト)、等々の引用、リファーをしまくるのです。
武士がこれこれするというのは、かつて林子平がなした○○のごとくであるが、西洋ではそれをバルザックが××と唱えたのと一致するものである、的な表現です。
実を言うと、なんだ引用ばかりで結局よくわからないや、この人は自分の知識をひけらかしたいだけにしか見えないや、と感じました。
しかしながら、解説を読んで考えが変わります。
彼が本作を出版したのは1899年、アメリカはカリフォルニアで英語で執筆したものです。当時は明治開国から程ない時期、日清戦争を経て、西洋社会で日本と言う小さい野蛮な国があるとやっと認知されたばかりだったのだと思います。
おそらくは偏見に満ちた物言い、心無い誹りもあったのだと思います。白人でもないし。また、本人にも日本人とは、日本とは何かというアイデンティティ・クライシス的なものも、西洋に赴くなかで持ち始めたのではないかと思います。
そのように考えると、本作は、彼が彼自身のために書いた本ではなかろうかという気がしてきました。自分が書くことで日本人の道徳とは何かをはっきりさせたかった、と。相当の博識の持ち主であったことは疑うべくもありませんが、持てる知識を総動員して日本人の道徳観は西欧にも通じている普遍性を持つと説明したかったように思えてなりませんん。
でも、スーパー凡人の私は通読二回目にして、やっぱり十全に理解したとはいえません。もっと西洋の話も儒教の話も勉強してから再チャレンジをしなければと思いました。
ましてや、解説にあるルーズヴェルト大統領が読後感動して家族や友人に配りまくったというエピソードがありますが、私はこの大統領は内容は殆ど理解していないに賭けますよ笑 そんなに簡単じゃないと思います。
・・・
おわりに、きっかけを。
私は本作は以前読んで本棚に眠っていましたが、先日、戦争の本で某イギリス人作家が日本兵の暴虐を表現して、これが彼らのBushidoなのだ、と批判しており、いやいや違うでしょ、と思い、再読してみたものです。
私自身、今回読み終わった後でも日本人の道徳心を他人に説明できる気がしませんが、ましてや外国人が本作を読んでも決して日本人を理解できないだろうなと感じました。
であるならどうするか。私たち自身が日本人の道徳心・感じ方・考え方を私たちなりに言葉に紡いでいく必要があるのでは?と思いました。海外に住んでいるから特にそう思うかもしれませんが。
本作はまた儒教系の本を勉強したら再読してみたいと思います。