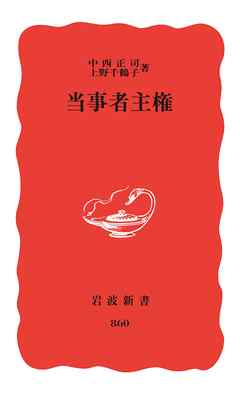感情タグBEST3
Posted by ブクログ
--読書メモ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
当事者は変わる。当事者が変われば、周囲が変わる。家族や地域が変わる。変えられる。地域が変われば、地域と当事者との関係が変わる。当事者運動は、自分たちだけでなく、社会を変える力を持っている。
Posted by ブクログ
この本の内容も題名も時期尚早かもしれない
現在の世界は建前民主主義にたどり着きながら
反作用に犯されて
大きく唯物的競争原理に逆行している最中である
そんな中で膨れ上がった金融マフィアを筆頭とする経済界や
政治や行政である今の権力者達は
この本の内容を最も毛嫌いしているからである
つまり個人がその個性と全体観を持って自律し
お互いの足りない部分を補い合い共生する調和の繋がりを求め
直接民主主義を目指す者を根絶やしたいと
権力機構は躍起になっている最中なのである
この本でも主権という言葉を使っているけれども
本質的に權利とか所有という傲慢で利己的な競争原理社会を
否定しているのである
部分でありながら全体でもあるという意味で
全ての存在が当事者同士でありお互いに
対等で自在な関係であることを
納得し合った関係にあるべきだということなのだと思う
調和というのは一瞬一瞬においてお互いの主張を認め合うことで
中庸な無摩擦の点を目指して限りない相乗効果に乗って
創造の踊りを愉しもうということである
Posted by ブクログ
高齢者の介護及び障碍者の介助についてを中心にして、自己決定能力が欠けていると(社会的には)みなされることの多い「当事者」たちに、「主権」―すなわち「自分の身体と精神に対する誰からも侵されない自己統治権、自己決定権」―を奪還させよう(そのために社会・制度を再設計しよう)という訴えをしている。
高齢者・障碍者を対象にして論じるとわかりやすいし全くそのとおりなのだが、これを、一般的な社会的弱者にまで拡張しようとすると少し問題は複雑になるだろうとは思った。
しかし全体的な主張としては、「基本的に誰でも自己決定はしているし、できる」という考え方(周囲の人の「コミュニケ―ション能力」という認識を含む。)や、第三者としての「専門家」(及びパターナリズム)についての論考など、大いに納得・賛同した。
※蛇足)
例えばまちづくりにまでこれを拡張しようとした場合、「誰が当事者なのか」という問題の他にも、いくつかの論点がうまれると思う。つまり、専門家(あるいは「ケアマネジャー」のような役割)の存在意義として、
①複雑な仕組み(法制度)を使いこなすための補助(著者の一人である上野が「ケアマネジャーの役割として考えているもの)、
②「個人の身体・精神」以外を調整すること(つまり、肉体的・時間的(世代間的)外部性の考慮)、
があると考える。
いずれにしろ、「客観性」のあるべき姿を問われる機会に本書がなったのも事実。より深く広い「主観」の積み重ねこそが客観、ということか。
Posted by ブクログ
「世の中をこんなものさ、と受け入れていれば、自分のニーズにさえ気づかない。そのために、非障害者は当事者にさえ、なれないのだ。障害者の自立の理念に学んで、変えられないと思っている社会を変えてみようではないか」と「おわりに」にはある。2003年に出版された書籍であり、当時の政治状況や医療の状況(たとえば、行政改革や乳がん治療など)は当時と変わったことを感じさせる。一方で、引用した文章で述べられている「当事者にさえ、なれない」という内容は、今なお強く実感させられる人も多いのではないだろうか。
社会は何も変えられないと思わされていれば、自分自身が感じるニーズを考慮しても仕方がない、と捉えても不思議ではない。ではどうするか?
Posted by ブクログ
普遍的な当事者問題について扱っていると思っていたが、内容は8割ほど障害者や介護を通じて考える当事者問題。しかし、そこから、当事者主権への流れはわかりやすく、障害者や介護問題からフェミニズムへと当事者主権という点で繋がるのかぁと思って読んでいた。パターナリズムについても理解を深めることができたと思う。
当事者主権、「自分の事は自分で決める」を通じて、「はたしてどれだけの人が、障害者のように、みずからの人生の主権者として自己選択と自己決定にもとづいて生きているのだろうか。企業組織で働く時、欠陥品を販売していると気づいた時、自分の地位をかけて人生の主権者たりうるだろうか。いま日本社会が一番必要としているのは、一人ひとりの個人が、みずからの人生の責任ある当事者として生きることではなかろうか。」は、刺さったなぁ。
以下読書メモ
>>>
・ニーズを持ったとき、人はだれでも当事者になる。ニーズを満たすのがサービスなら、当事者とはサービスのエンドユーザーのことである。だからニーズに応じて、人はだれでも当事者になる可能性を持っている。当事者とは、「問題をかかえた人々」と同義ではない。問題を生み出す社会に適応してしまっては、ニーズは発生しない。ニーズ(必要)とは、欠乏や不足という意味から来ている。私の現在の状態を、こうあってほしい状態に対する不足ととらえて、そうではない新しい現実をつくりだそうとする構想力を持ったときに、はじめて自分のニーズとは何かがわかり、人は当事者になる。ニーズはあるのではなく、つくられる。ニーズをつくるというのは、もうひとつの社会を構想することである。
・当事者主義では、いろいろある主義主張のひとつ、それも偏った少数派の意見ととられがちだし、また当事者本位という言い方では、またしても「あなたがほんとうに必要なものを私たちが提供してあげましょう」というパターナリズム(温情的庇護主義)にからめとられてしまう危険性があるからだ。
・当事者主権は、何よりも人格の尊厳にもとづいている。主権とは自分の身体と精神に対する誰からも侵されない自己統治権、すなわち自己決定権をさす。私のこの権利は、誰にも譲ることができないし、誰からも侵されない、とする立場が「当事者主権」である。
・当事者主権とは、私が私の主権者である、私以外のだれも――国家も、家族も、 専門家もーー私がだれであるか、私のニーズが何であるかを代わって決めることを許さない、という立場の表明である。
・当事者主権の要求、「私のことは私が決める」というもっとも基本的なことを、社会的な弱者と言われる人々は奪われてきた。それらの人々とは、女性、高齢者、瞳害者、子ども、性的少数者、患者、精神障害者、不登校者、などなどの人々である。この社会のしくみにうまく適応できないために「問題がある」と考えられ、その処遇を自分以外の人々によって決められてきた人々が、声をあげ始めた。
・障害者の自立とは何か。二四時間介助を受けても、自立していると言えるのか?自立生活運動が生んだ「自立」の概念は、それまでの近代個人主義的な「自立」の考え方ーだれにも迷惑をかけずに、ひとりで生きていくことーに、大きなパラダイム転換をもたらした。
・ふつう私たちは「自立」というと、他人の世話にならずに単独で生きていくことを想定する。だがそのような自立は幻想にすぎない。どの人も自分以外の他人によってニーズを満たしてもらわなければ、生きていくことができない。社会は自立した個人の集まりから成り立っているように見えて、その実、相互依存する人々の集まりから成り立っている。人生の最初も、最期にも、人と人が支え合い、お互いに必要を満たしあって生きるのはあたりまえのことであり、だれかから助けを受けたからといって、そのことで自分の主権を侵される理由にはならない。
・高齢者に限らず、だれでもニーズを他人に満たしてもらいながら自立生活を送っている。そう考えれば、高齢の要介護者や障害者の「自立生活」は、ちっともふしぎなものではない。最期まで自立して生きる。そのために他人の手を借りる。それが恥ではなく権利である社会をつくるために、障害者の当事者団体が果たしてきた役割は大きい。
・私たちは当事者を「ニーズを持った人々」と定義し、「問題をかかえた人々」とは呼ばなかった。というのも何が「問題」になるかは、社会のあり方によって変わるからである。誰でもはじめから「当事者である」わけではない。この世の中では、現在の社会のしくみに合わないために「問題をかかえた」人々が、「当事者になる」。社会のしくみやルールが変われば、いま問題であることも問題でなくなる可能性があるから、問題は「ある」のではなく、「つくられる」。そう考えると、「問題をかかえた」人々とは、「問題をかかえさせられた」人々である、と言いかえてもよい。
・それなら「障害者」に「問題」や「障害」を抱えこませた原因は、社会のしくみの側にあるのだから、それを補填する責任が社会の側にあって当然だろう。そのように社会の設計を変えるということは、「障害」を持った(持たされた)人がハンディを感じずにすむだけでなく、障害のない(と見なされる)人々にとっても、住みやすい社会となるはずだ。
・「女性問題」と呼ばれることがらを考えてみてもよい。「職業と家庭の両立」は、いつも女性にとって「問題」だ、と言われつづけてきたが、前近代までは、農家の主婦にとって「職業と家庭の両立」は問題にならなかったのだから、それは「職業と家庭の両立」がむずかしいような社会のしくみを造りあげてしまったことが原因である。しかも、それが「女の問題」であって、「男の問題」にならないのは、男がその「問題」を女にしわよせしてきたからである。女性解放運動は、それに対して、「問題」は女の側にではなく、社会の側にある、とパラダイム転換をおこなった。そのことで、みずからが、社会の「お客様」ではなく、主人公、つまり「当事者」になったのである。
・専門家とはだれか。専門家とは、当事者に代わって、当事者よりも本人の状態や利益について、適切な判断を下すことができると考えられている第三者のことである。専門家には、ふつうの人にはない権威や資格が与えられている。そういう専門家が「あなたのことは、あなた以上に私が知っています。あなたにとって、何がいちばんいいかを、私が代わって判断してあげましょう」という態度をとることを、パターナリズム(温情的庇護主義)と呼んできた。パターナリズムはパーター(父親)という語源から来ており、家父長的温情主義とも訳す。夫が妻に「悪いようにはしないから、黙ってオレについてこい」とか、母親が受験生の息子に「あなたは何も考えなくていいのよ、お母さんが決めてあげるから」というのも、パターナリズムの一種である。
・専門知としてのこれまでの学問と当事者学との、もっとも大きな違いは、非当事者が当事者を「客体」としてあれこれ「客観的」に論じるのではなく、当事者自身がみずからの経験を言語化し、理論化して、社会変革のための「武器」にきたえあげていく、という実践性にある。
・同じような動きをもっと大きな規模で実現したのが、フェミニズムがもたらした女性学であった。「女とはどんな生き物か」をめぐって古来からあれこれ論じてきた男の哲学者や宗教家たちはたくさんいたが、そのどれもが「女とはどんな生き物であってほしいか」「あるべきか」をめぐる、ご都合主義的な論議で、女自身の声は長いあいだ、表にあらわれなかった。女が自分自身の経験を言語化したのが、女性学の成り立ちである。「女とは何者か」を当事者自身が自己定義する試みであると言ってよい。
・専門家が「客観性」の名においてやってきたことに対する批判が、ここにはある。というのも「客観性」や「中立性」の名のもとで、専門家は、現在ある支配的な秩序を維持することに貢献してきたからである。むしろ当事者学は、あなたはどの立場に立つのか、という問いを聞く人につきつけると言ってよい。社会的弱者にとっては、あなたが「何もしないこと」――不作為の罪ーーが、差別の加害者に加担する結果になるように、当事者学は、実のところ、どんな差別問題にも、非当事者はどこにもいない、ということをも明らかにしてきた。なぜなら、差別を受ける者が当事者なら、他方で差別をつくる者も、うらがえしの意味で差別の当事者だからである。
・ 障害を持たないものも、この自立生活運動から学ぶことは多い。はたしてどれだけの人が、障害者のように、みずからの人生の主権者として自己選択と自己決定にもとづいて生きているのだろうか。企業組織で働く時、欠陥品を販売していると気づいた時、自分の地位をかけて人生の主権者たりうるだろうか。いま日本社会が一番必要としているのは、一人ひとりの個人が、みずからの人生の責任ある当事者として生きることではなかろうか。
・ピアは「なかま」、「同輩」という意味であり、ここでは助け、助けられる関係に上下関係が存在しないことが目指されている。
・自立生活運動は、これまで他人の顔色をうかがって生きてきた障害者に自尊心を与えた。ピアカウンセリングによってエンパワメントした障害者は、自分たちの側に「問題」があるのではない、自分たちに「問題」を押しつける社会の側に問題がある、だから自分たちを受け入れるように社会のほうを変えていかなければならないのだと気づいた。
・高齢者のなかには、いまだに介護保険を受けたくない、介護サービス会社のクルマは家の前に停めてもらいたくないという人がいる。
→自助能力を失うことが、意思決定能力を失うことと同じだと考えられてきたからである。
・ホームヘルパーはなぜ低賃金か?理由ははっきりしている。第一に、これまで女が家族のなかでタダで供給してきたから。第二に、女ならだれでもできる非熟練労働と見なされたから。第三に、無業の主婦のように、無尽蔵の労働力の供給源があると考えられたから。
・福祉において、善意や慈善というものはときには危険である。なぜなら、当事者に代わって第三者が、当事者にとって何がいちばんよいかを判断するからだ。
・ベティ・フリーダンの『女らしさの謎』(一九六三年、邦訳『新しい女性の創造』)である。幸せのはずなのに幸せに思えないのは、自分が悪いのではない、女の自己実現をはばむ世の中がまちがっている、と「問題」を一八〇度パラダイム転換したのが、第三波
フェミニズムだった。「女性問題」は、これ以降、女が抱える女だけの問題ではなく、女が問う社会全体の問題へとシフトしたのである。
・アルコール依存症にはしばしば暴力がともなっている。妻はドメスティック・バイオレンスの被害者であることが多いが、自分を被害者と認知することが少ない。配偶者の忍従と献身が、夫のアルコール依存を継続させるという関係が、イネープラー(enabler嗜癖を可能にする人)という概念で明らかにされ、妻も共依存という名の当事者のひとりであることがわかってきた。アルコール依存症の本人だけでなく、アルコール依存症の家族の会のような自助グループも各地に存在している。
やがて臨床家たちは、アルコール依存症の患者の家庭で育つ子どもたちが、成人
・アルコール依存症にはしばしば暴力がともなっている。妻はドメスティック・バイオレンスの被害者であることが多いが、自分を被害者と認知することが少ない。配偶者の忍従と献身が、夫のアルコール依存を継続させるという関係が、イネープラー(enabler嗜癖を可能にする人)という概念で明らかにされ、妻も共依存という名の当事者のひとりであることがわかってきた。アルコール依存症の本人だけでなく、アルコール依存症の家族の会のような自助グループも各地に存在している。
・これがACことアダルトチルドレン(Adult Children of Alcoholics)である。家族のなかのたえまないストレス、家庭が危険な場所であるという緊張状態、母親が暴力の被害を受け続けるのを目撃することからくるトラウマ(心の傷)などにさらされた子どもたちが、強い抑うつ感や自己評価の低さに悩まされることがわかった。その後、ACという用語は、斎藤学さんや信田さよ子さんの紹介で、「現在の自分の生きがたさが、親との関係に起因する」と判断した人々が、自己申告する概念として、ひろく定着した。
・ACに見るように、ひとは自己定義によって、当事者になれる。というよりも、問題を自分で引き受けたとき、人は当事者になる、と言ってよい。当事者とは、周囲から押しつけられるものではない。自己定義によって、自分の問題が何かを見きわめ、自分のニーズをはっきり自覚することによって、人は当事者になる。したがって当事者になる、というのは、エンパワーメントである。たとえ被害者としての当事者性をひきうける場合でさえ、当事者になることとは本人にとっては無力の証ではなく、みずからの主権者になるという能動的な行為なのである。
Posted by ブクログ
「私の現在の状態を、こうあってほしい状態に対する不足ととらえて、そうではない新しい現実をつくりだろうとする構想力を待ったときに、はじめて自分のニーズとは何かがわかり、人は当事者になる」「ニーズはあるのではなく、つくられる。」「ニーズをつくるというのは、もうひとつの社会を構想することである。」
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
障害者、女性、高齢者、子ども、不登校者、患者…。
問題を抱えているとみなされた当事者たちが、「私のことは私が決める」と声をあげた。
自立の意味を転換し、専門性を問い直し、社会を組みかえる、緊急かつ大胆な提言の書。
[ 目次 ]
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
当事者主権はなにかの当事者だからこそ求めるものだったけれど、これからは自分がいつ当事者になるのかわからない否高齢者には長生きすれば必ずなるのだから、そうなる前に考えよう行動しよう住みよくしよう。
Posted by ブクログ
主に障害者の領域を中心とした当事者による運動の書。当事者主権とは何か、当事者運動はそもそもなぜ行われるのか、当事者がサービスを担い、同時に利用者でもあるという形態はどのような意味を持つのか。実に色々なことが網羅されていて、薄い本ながら、内容はギュッと詰まっています。当事者のことを一番よく知っているのは当事者。そのことは、とかく資格を求めがちな専門家志向の現代社会に強く問題提起をしているのではないでしょうか。
ただ、僕はどういう訳だか上野千鶴子先生が執筆しているというだけで、やや引いた感じで読んでしまいます。女性問題は深くてとても単純な思考回路では理解できないのは分かっているけれど、それでも上野先生のラディカルな意見にはいまいちついていけない。
それを念頭に置いていれば、なかなかの良書だと思います。ただ、あくまでも、当事者の当事者による当事者のための書、という意識を持っていた方がいいと思います。でないと、もしかしたら思わぬ落とし穴に入り込んでしまうかもしれません。信用半分・懐疑心半分で読むのがベストだと思います。
Posted by ブクログ
気鋭の実務家と学者のコラボレーションが作った新しいパラダイム。
個人がより主体的に生きることができるように打ち立てた言葉「当事者主権」。
新しい概念が浮かび上がらせてくれるものは何か。
存在しているのに見えないものとして、暗黙のうちに働くものとして、異議を唱えないものとして扱われる人々。障害者、女性、患者、あらゆるマイノリティの人たちがそこにはいる。そして当事者ということばを打ち立てれば、今まで当然のように社会を取り仕切ってきたマジョリティの存在も明らかになる。彼らも当事者なのである。
すべての人にスポットライトを当てるために書かれた本。そのきっかけとして障害をもつ人たちの運動に注目した点は秀逸だと思われる。
Posted by ブクログ
中西正司氏と上野千鶴子氏の共著。中西氏については寡聞ながら初めて知ることとなり、そのエネルギーにただ驚かされた。そして意外に感じられたのは上野千鶴子氏の今までとは違う「筆力」だ。
中西氏は確かに行動的な方だが、失礼ながら単著をお見かけしないところをみると、この本については基本的にコンセプトと主張を提示し、それを上野氏が「脚色」したのではないかと思う(違ってたらお許しを)。
私にとって上野氏の論調は、その視点を常に極端なレベルにおいて、そこから「中庸」の部分に斬り込んで行く姿勢を取っているように感じられ、常に一人称を強調するような印象がある。
しかし、この書において、視点は完全に中西氏のものであるように思えた。上野氏が脚色のみを担当したのであるとしたら、すばらしい黒子ぶりである。
障碍者の介助については詳しくなかったのでいろいろと学ばされることが多かったが、高齢者の福祉については書かれていることを読んで暗うつ、とは言わないまでも救われ難いものを感じた。
この書は10年も前、介護保険にそれなりの期待があった時代のものだ。しかし中の指摘を見ると、当初から「家族」をアテにしたものであったということ。現在もそれは同じであり、いやむしろ「在宅、在宅」と施設収容を前提に置かせないという部分など、もっと家族への負担を課すような政策になっている。
そしてその一つの原因も本書ではみごとに指摘されている。社会が「平均」と「標準」を基準に設計され、政策もそれに応じたものになっているということ。しかし、「平均」と「標準」にぴったり当てはまる人間などいない。人はそれぞれ平均値からの偏差を自分で修正しなければならない。そのためには何らかの力が必要となる。そのための最も簡潔な手段は「金銭」であり、現在満足のいくだけの介護を受けようと思ったら、「財力」が不可欠な要因となっているのだ。
10年前、私は母を看取った。そしてこの10年間、大なり小なり介護に関わる生活をしてきている。その間「制度」としても「現状」としても介護が向上しているとは残念ながら思えない。
行政のつくる「制度」をいただくだけの「クライアント」のままでは今後もこれは変わらないだろう。本書で主張された『一人一人の個人が自らの人生の責任ある当事者として生きること』という言葉がほんとうに清冽に響く。
Posted by ブクログ
「次の仕事を始める前にぜひ読んで欲しい」と、上司に手渡された本。付箋がいっぱい貼られたこの本は、「障害者」や「女性」といった、社会的地位の低い(と呼ばれる)人たちの、問題はどこにあるのか、というのを考える本。きっと、上司が言ってるうち、20%もわかってないんだと思うんだけど、どういった目線で見ていかなければいけないのかは、ちゃんと考えていかなきゃいけないなと改めて思った本。
Posted by ブクログ
◎この世の中では、現在の社会のしくみに合わないために「問題をかかえた」人々が、「当事者になる」。社会のしくみやルールが変われば、いま問題であることも問題でなくなる可能性があるから、問題は「ある」のではなく、「つくられる」。そう考えると、「問題をかかえた」人々とは、「問題をかかえさせられた」人々である、と言いかえてもよい。
Posted by ブクログ
たとえばユニバーサルデザインで社会の設計を行えば、多くの「障害」を「障害」でなくすることは可能であるように、「問題(障害)」は社会によってつくられる。本著では、当事者とは現実の社会に不足や欠乏を感じていて、そこから生じるニーズを満たし得る、もうひとつの社会を構想する人のことであると定義されている。フェミニズム、レズビアン&ゲイ解放運動など、当事者を担い手とした活動が社会に大きな影響を与えつつあるが、その牽引力となったのが自立生活運動である。
自立生活運動とは、保護という名目で施設の中で無為な生活を強いられていた重度障害者が、社会のなかで暮らすことを「危険を冒す権利」として訴え、自己決定、自己選択によって生きていくことを宣言したことを指す。
その流れにある自立生活センターは運動体でありかつ事業体でもある。障害者自身が福祉のサービスの担い手となり、福祉サービスを担う。サービスの供給者であり利用者でもあることは、サービスの「品質管理」を確実なものにし、営利企業に負けないクオリティも確保される。一方で事業体が運動体に対して、つまり採算部門が不採算部門に対して優位に立つ傾向を押さえる努力も興味深い。その方法とは、両方の事務所の代表を当事者自身とし、運営の実権を障害当事者が握るというものである。
当事者運動は第二期を迎えていると著者はいう。要求が制度化されつつも、知らないうちに換骨奪胎されて似て非なる制度が作り上げられる危険を指摘し、交渉能力の維持と監視、実績の蓄積、さらに時代に一歩先んじた政策提言をすることが求められているとする。
障害者運動と女性運動という異なる現場にいる2人の共著であり最後の一文が「全世界の当事者よ、連帯せよ」であることが、当事者主権の運動の展開の可能性をうかがわせる。
Posted by ブクログ
この本は,あるMLを通じて知りました。その後,何度も書店で探しましたが見つからず,結局ネットを通じて購入しました。
社会福祉では,当事者の意向を尊重すると言いますが,いつもその前に「最大限」とか「可能な限り」という言葉がつきます。いつも,これらの言葉について,どのように考えるべきなのかを気にしていたところ,この本に出会いました。「最大限」とか「可能な限り」という専門家ではなく,「当事者」がまさに自分のこととしてどのように行動していけば良いのかについて書かれています。
当事者が生活する上でのニーズを自らが確認し,自分たちのために行動することの重要性を強調しています。また,社会福祉サービスの担い手としての女性の意見を尊重しないという視点でも書かれています。
精神障害をもつ人の福祉を考えるときにも大いに役立つ視点が多く書かれています。