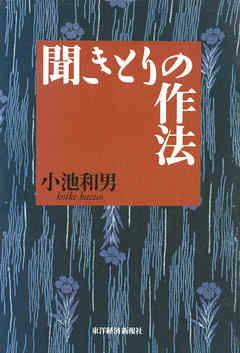感情タグBEST3
Posted by ブクログ
具体的な方法、こつ、一人だけの聞き取り、最大1時間半、録音のこつ、など様々なことを事細かく書いている。フィールドワークで聞き取りをする前には必読書である。
Posted by ブクログ
修士時代、企業インタビューをこなすのに備えて読んだ本。
研究者向けだったと思いますが、いま僕がインタビューをあまり苦手意識なくできるのは、こうした本で得た擬似体験といくつかのインタビュー経験、それに編集者時代の取材やらをこなした日々の賜物。
(2017年7月23日追加)
数量分析だけで説明できる現象はそんなに多くはない。
質的比較分析の本をちょうど読み始めたところ。
外部研究者に比べて、内部観察の壁が高くない、監査という仕事にとっても、文化人類学・社会学的なフィールドワークの基本を実践していければ、もっとよりよいインサイトが得られるはず。
そんな思いを新たにした再読。
3章構成。1、2章のみ読めば、監査人には十分。
・慣れない人は、30分以内の短い聞き取りから。
・調査計画は、予備調査項目みたいなもん。
・半構造化インタビュー
・じっくり考えないとなにもできないという重厚タイプのひとは、わたくしの経験では、聞きとりにはむかない。聞きとりはあるていど「軽佻浮薄」でないと勤まらない。かるがるしく決断する必要がある。
・職場をみる
・相手への敬意、相手に教えてもらうとの気構えが大切である。
・議論をしない。
・つぎの質問のメモも大切なのだ。
Posted by ブクログ
聞き取り調査実施における考え方やTipsをまとめた書籍。修士論文に関わるインタビュー実施の際に読んで参考にした。
■重要ポイントのメモ
1.調査計画(聞きとりの前に)
・当然だが、相手のコスト(時間)への配慮が重要。
・一人の話し手に聞く時間を1回1.5~2時間以内、2回程度にするなど、1人当たり1社当たりの負担を減らして、複数組織を比較した方が了解を得やすい。
・仮説設定時は二段階の手続きを用意する。1つ目は分析概念の設定、2つ目は測定指標の設定である。
・企業選定前に有価証券報告書などで企業について調べるのは大事。
・比較しながら語ることの出来る人をインタビュー相手に選ぶのが良い。比較こそ事実に接近する近道である。
・話し手の人数は一人が最も良い。自分の意見をはっきり言ってもらいやすい。
・依頼する際に、何を、誰に、どれほど話を聞きたいのか、それを具体的に細かく書いた依頼書を企業に送ること。その際に自分の履歴を示す情報を付加して、自己紹介をしておくこと。
・先方の宛先を固有名詞で書くこと。
※学術研究の場合は、書類を書く手間を惜しまず、財団の公募に申し込むこと。各財団の関心分野を知り、自分の問題意識と重なるところを見つけるのが肝要。
2.聞きとり
・個々の質問は前もって決めておかない。聞くべき要点はかなり仮説によって決まっているとしても、実際の質問は相手の答えによって違ってくる。
・具体的に聞くこと。また、最近の例を聞くこと。
・聞きとりは話し手と聞き手の共同作業。聞き手はある程度軽佻浮薄でないと務まらない。軽々しく決断することが必要となる。
・追加質問の重要性。相手の話を踏まえた上で、さらに切り込んだ質問を用意すること。
・メモは重要な点を浮き彫りにする。目に付く情景、各種掲示物など、時間がある限り素早くその一部をスケッチすることも大事。
・毎回聞きとりの”直前に”聞き取り要領を用意すること。
・相手の協力を得るは、「周到な準備」と「的を得た質問」が必要。
・相手の承諾を得られれば録音はしたほうがいい。しかし、それでもメモを真剣に取ること。
・なるべくその日の内に、遅くても次の日までにメモを浄書して、聞き取りノートを作っておくこと。前後矛盾しててもいいので、単語の羅列ではなくとにかく文章にしておく。
・聞き取りノートは門外不出とすること。話し手のプライバシーを最優先。
3.聞き取り調査の説明力
・非数量的な知識を扱うとしたら、個別の例を聞き、なぜ、どのようにしてという点まで理解しやすいように説明することが極めて重要。
・聞き取りの事例をなるべく小さな種の中におさめる。そのうえで、2、3の種にわたって観察事例を拡張する。
・アンケート調査も併用する場合は、聞き取りを先に行う。
・
Posted by ブクログ
企業への聞きとりのための入門書。「聞きとりに手土産はいるの?」というちょっとした疑問から、「計量分析が主流の時代に聞きとりの意味とは何か」という哲学的な命題まで丁寧にふれられてました。人文系で聞きとりする方は読んで損はないはず。