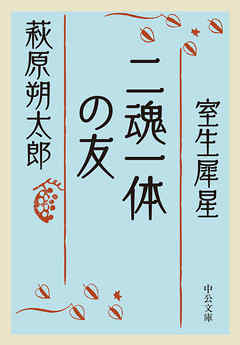感情タグBEST3
Posted by ブクログ
内容が濃い!
萩原朔太郎と室生犀星の共著である本書は、互いへの思いをそれぞれに語った記事を纏めた興味深い1冊で、めちゃくちゃ面白かった!
犀星の幾つかの詩に朔太郎が解釈をつけていたり、互いへ向けた詩を詠んでいたり。
二人が互いに向けた思いをぶちまける。
無花果さん、勧めて下さって有難う御座います♪
本書はまず萩原朔太郎の目線で犀星が語られる。
どうやら彼と犀星は性格も好みも真逆だったよう。
犀星の誘いで移り住んだ田端も朔太郎に言わせれば、「妙にじめじめして、お寺臭く、陰気で、俳人や茶人の住みそうな所」だそうで、「第一始めから印象が嫌いであった。」とバッサリ 笑
芥川龍之介にまで飛び火して、彼が紹介してくれた料亭の茶席も「栄養不良の青っぽい感じ」とまで言ってのける 笑笑
とにかく「田端的風物の一切が嫌い」なのだとか。
う~ん、逆に田端からも嫌われそうだ。
またお互いの性格についても、
「二人の気質や趣味や性情が、全然正反対にできているので、逢えば必ず意見がちがい、それでいてどっちが居なくも寂しくなる友情」
と述べている。
けれど朔太郎は、
「今では同士の関係でなく、肉親の関係に進んでいるのが、ふしぎに直感されるのである。ー愛は、理由なく愛する故に愛である。ー」
とまで言う。
喧嘩別れした後、反対側の駅のホームで佇む犀星の姿に、朔太郎が思わず涙ぐむエピソードまであるから驚き。
こんなにも二人の絆が強かっただなんて、全く知らなかった!
散々に言いながらも犀星を評価し、朔太郎の目線には確かに愛を感じる。
「彼の「作品」にはいつもいみじきユーモアがある。或る馬鹿正直の人間がもつような、真面目すぎて可笑しくなるユーモアである。その笑の底にしおらしい純情の心がすすり泣いている。知れば知るほど、犀星は人の愛情をひきつける徳をもっている。」
犀星自身と犀星作品の、一番の理解者ではないだろうか。
犀星に対して「いじらしい」という言葉を何回使っただろう。
「いじらしい」なんて、相手に対して深い情がなければなかなか使わない。
もはや母性さえ感じてしまう。
朔太郎は彼の心境を「老人心境」「風流心境」、もっと正しくは「冬日返り花的心境」「冬日蜆貝的心境」(笑)などと手厳しく称しているけれど、
それも犀星が我が子を亡くしたことが切っ掛けであったときちんと理解している。
犀星の『忘春詩集』は実にその愛児に捧げたものだとも。(読み直さなきゃ!)
朔太郎は犀星を、
「風流韻事のあらゆる世界が、宿命的の果敢なさと寂しさとに充ちて、世にも悲しく影深いものに見えた。その苔むした庭石や前栽の葉陰を通じて、ずっと人間生活の内部に触れ、宇宙の実在性に通ずる秘密の道を、彼は本能によって直覚した」
とまで言う。
そして、自分は犀星とはあらゆる点において反対に位置するものだが、
「室生君を日本一の詩人と呼ぶにはばからない」
と。
朔太郎は犀星を、ときに敵対し、ときに鼓舞し、才能を認め、共に詩壇で戦っていこうと友情を見せる。
「室生犀星君の作った小曲風の抒情詩だけが、不思議に僕の心を強く惹き付け、………心を溺れさせた。」
また、自身に真理を教えてくれる存在であり、「昔ながらに僕の「善き良心」である」という。
続いては犀星目線の朔太郎。
二人での旅行。
「萩原、ちょいとベルを押せ。」
「おれはお前の家来ではない。お前押せ。」
と早速小競合いの様が書かれていて笑う。
互いに才能豊かであるのに、二人揃うと子供のようだ。
それでも、
「わけてもあたりの静かな高原の湿った光景が、つい絡みついて、黙って向い合うことがあった。」
との詩的な表現がぐっとくる。
また別れ際、先に電車を降りる朔太郎に対して、降りるときは起こしてくれるなという犀星。
朔太郎は言われた通りにするのだけれど、実は犀星は起きている。
「約束どおり黙って出てゆく萩原の靴音を聞き、そっと寝がえりを打ち、心の美しい友だちとこういう風に別れるのを却って寂しく感じた。」
なるほど、朔太郎の言う「いじらしい」ってこういうところかしら。
朔太郎はかなりの熱量をもって犀星を語っていたけれど、犀星の方はいくぶん冷静なのだろうか。
冷静というよりマイペースで、照れ臭いのかな。
犀星は朔太郎を、ドストエフスキーでもニーチェでも自分の一歩先を読んでいたと言うが、
「そのくせ一歩ずつあともどりしている。議論をもった人である。わたしは議論が嫌いなのでわたしの方で控えていると、たまに食ってかかる。妙に哲学者肌である。」
などと言う。
二人の文章には芥川龍之介もよく登場する。
犀星が彼と軽井沢に出掛けた時のこと。
高原の日光は強烈だから帽子を被った方が良いと勧めたにもかかわらず、彼は、「紫外線はからだにいいんだよ」といって聞かない。
が、帰り道、「眼がふらふらする……。」といって木陰に寄ることとなった 笑
だから言ったじゃないかと迫る犀星に、「あやまる、あやまる。」と言う芥川。
そんなエピソードを振り返り、犀星は、
「芥川君くらいぬけたところのある人はないと思った。よくつき合うと味のあるぬけ方をした。」
「俗人にさえ和することのできる人がらを持っていると思った。」
と評し、
「ときとすると文学者らしい垢をも持っていないところを人は知らず私は床しく感じた。」
と結ぶ。
マイペースな犀星だけれど、朔太郎とはまた違った静かな眼差しで、人をよく見ているように感じた。
朔太郎の人柄については意外だった。
容姿からはハイカラな印象を受けていたのだけれど、犀星に言わせれば「ハイカラのような想像を人々に起こさせるが」そうではないらしい。
「彼は物ぐさい男であるということを自分で知っているけれど、その物ぐささから脱けようとする気持のない人間である。」
「外套のボタンが五つあればその中の四つまで外れている男である。」
「彼と一緒に食事をしていても彼は御馳走をそこらじゅうに取り散らかし………」
え~! 笑
「彼のハイカラは彼の精神のなかにのみ蔵われていて、決して実際に生活的に実行されていない。」
それでも「彼は何かハイカラらしいものを感じさせるから不思議である。」
とのこと。
それなら、浅い知識で朔太郎からハイカラな印象を受けていた私も、あながち間違ってはいないのかな。
犀星はこのことを「ハイカラの風格を持っている」「ハイカラ的余韻がそう見せる」と表現して、「田舎者であることに疑いはない」と結んでいる 笑笑
この、くどくどとしつこく言い回すあたり。
これが犀星なんだなぁ 笑
そんな犀星に対し朔太郎は、
俺はお前を根本から理解しているが、お前は俺をどれほど理解しているんだ?俺の作品は読んでいるのか?親友として俺の作品に向き直ったことがないだろ?
と、原稿用紙10枚にも及ぶ手紙をよこしたり…。
犀星は言う。
「僕は彼のこういう意気込みや十枚の原稿紙に力一杯やっつけようとする彼の根気にホトホト参ってしまう、彼は筆をとると一気に書けるひとであり、書いてしまってから打倒れても途中で倒れるような弱い男ではない。」
こう言ってはなんだが、この二人は微笑ましい 笑
滑稽な水と油のようでもありながら、やっぱり互いを意識し、尊敬し、心を許しあっている。
言いたい放題に言いながらも、互いに好いている。
ここまでの仲って、そうそう無いのでは?
ちょっぴり羨ましくもある二人だ。
そしてやってくる朔太郎の死。
「友人には誰一人知らさずに独身者のように彼は死んで行った。おそらく萩原は最後まで友人というものに会いたくなかったのであろう。私はそこに口にいえない萩原の心の深さを知るものである。」
その朔太郎の死後、1954年6月の『新潮』に寄せたという犀星の「詩人・萩原朔太郎」は感慨深かった。
巻末には二人の娘である、萩原葉子さんと室生朝子さんの対談あり。
◎萩原朔太郎
1886年(明治19年)11月1日~1942年(昭和17年)5月11日
◎室生犀星
1889年(明治22年)8月1日~1962年(昭和37年)3月26日
☆笑止(しょうし)
・ばかばかしいこと。おかしいこと。また、そのさま。
・気の毒に思うこと。また、そのさま。
・困っていること。また、そのさま。
・恥ずかしく思うこと。また、そのさま。
☆冬日返り花的心境
返り花というと二度咲きの花のことだと思うのだけど、この場合、
「春の盛りにうまく育たなかった花芽が、冬の小春のあたたかさに乗じて咲くことがある」等の狂い咲きの意味かしら。
☆冬日蜆貝的心境
どういう意味だろうと思ったけれど、「内に蜆のような厭世観を持っている」と後述しているところから、
"蜆のように固く綴じ込もって世の中を悲観している"と解釈した。