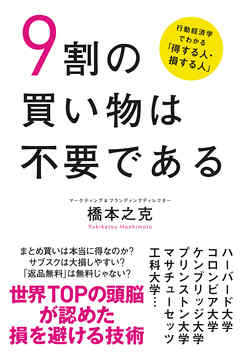感情タグBEST3
Posted by ブクログ
わかりやすい例を多数紹介しながら行動経済学をもとにより良い買い物するためのヒントが書かれています
確率加重関数の解説見て、人が保険や宝くじを買う理由がちょっとわかった気がする。
でもこれらは生まれ持った性質なので、頭で理解して自分をコントロールしないと中々抗うのは難しい…
Posted by ブクログ
マーケティングやブランディングに精通する経済の専門家である著者が普段の買い物から得する人と損する人を行動経済学の観点から書いた一冊。
普段私たちが何気なく行っている買い物について
ネットでの情報収集や転売やサブスクとの賢い付き合い方など近年に生まれた新しい商慣習についての話題や買うものを値段で決めないことやまとめ買いやついで買いなど従来からある買い物についてや買い物における選択のことまで買い物にまつわるさまざまなことを行動経済学の観点から行動心理を学ぶことができました。
また、家、保険といった高額になる買い物についても常識にとらわれず自分にとって最善の選択をするための考え方が書かれており勉強になりました。
またギャンブルにハマる理由も経済学の観点から書かれていて納得できるものでした。
そんな本書の中でも保有効果を狙った返品無料のビジネスの仕組みやポイントカードと割引の損得やサイコロを使った決断の技法などは生きていく上で参考となりました。
また、誰かに見られていると感じるだけで不正は減ることや認知的不協和の不快感にはきちんと反応することなどもモヤモヤとして不思議に思っていたことが鮮明になり本書を読んで良かったと感じました。
本書を読んで自分で欲しいものかをよく考えて買い物をすることや自分だけが利益を得る買い物はやめることなど買い物をする時に気をつけることを学べるとともに保有効果がかなり誤解を与えていることや時間や労力をかけずに情報収集することなど自分の決断に有用な情報も知ることができました。
本書で学んだことを活かして無駄な買い物やお金の使い方をしないよう気を引き締めていこうと感じた一冊でした。
Posted by ブクログ
辛口の意見も多いようだが、本書のように購買心理をまとめてくれているといざ買い物する時に踏みとどまって考えることができてありがたいと思った。
知識の真新しさはないが、賢い買い物をするためのガイドラインのような役割をする本だと思った。
その点を評価したい。
Posted by ブクログ
保険と宝くじの話が自分の感覚に近いので、他も従う気になった。買い物がよかったかどうかは利用した結果で判断されるべき>、使わないけど見ているだけで幸せとか。買ってうれしかったとか、喜んでくれたとか、そういうのは過程のほうに入れるか。衝動買いは家族への暴言や過食よりまし。>ほんとにそう。ある程度重要な買い物については、AIDMAを買い手側から見る。注意を惹かれ関心を持った商品を調べる。買うまでのプロセスを大切にする。時間割引率の影響を勘定に入れろ。>後述の住宅の購入。自分でコントロールできない散財が問題。その点で習慣的なものは要注意。売り手は心理学を学び買い手に無意識に買わせようとするので、買い手も心理学を学び防衛する必要がある。選択肢を減らし選択する回数を減らして疲れない。迷ったら選択を先延ばしするか放棄する。情報収集に時間をかけすぎない。住宅購入。選択肢を増やす。一度の判断で終わらせない。自宅内で住まいを完結させない。耐久消費財は使用期間の間の満足度を維持する。直近数年だけでなく住宅寿命50年を考えるとどうか。住宅の売り手が刹那的な行動習慣を持っていることを意識しておく。
Posted by ブクログ
何かで紹介されていた。
買い物に関する行動経済学を説明しているもの。
そもそもそんなに買い物をしないので、9割無駄な買い物をしているとは思わないが、なるほどと思ったところは
・買う前にサイトで情報収集してもキリがない。時間をかけ過ぎない。
・クーポン券があると使わないと損、と思ってしまう。
・まとめ買いは、使用するまでのタイムラグを精査し、無駄にならないようなら、利用する。
・すでに買い物したものを調べない。
・安いからと言って買わない。
Posted by ブクログ
『予想どおりに不合理』などの行動経済学関連の本を別に読んだ人なら、内容が重複するので本著は不要、あるいは、おさらいに最適。人間の行動心理を用語化し、その用語を淡々と説明していく用語解説、教科書的な内容。確証バイアスだとか、ハロー効果、バンドワゴン効果、経路依存性などなど、所謂、行動経済学用語の再確認用の本。これらの意味がわかる人ならば、読書の価値が低い。初見ならば、これ程分かりやすく解説している本も中々無いだろうから、オススメできる。
ただ、例によって、9割の買い物という、9割については根拠が示されない。光熱費や食費が1割という人はいないだろうから、誇張表現だろう。そう考えると、この本も彼我の認知の差を利用して、低い認知の方から効率よくお金を稼ぎたいという魂胆が透ける。事実ではないがタイトルこうした方が売れそうです!で良いのだろうか。
Posted by ブクログ
行動経済学の本らしいが特段知識を持っていなくても読みやすい。自分自身、過去の買い物で当てはまることがいくつもあって心理学的に説明されるのは面白い感覚だった。
これを読んで買い物を9割減らせるかと言うとこの9割は何の根拠があって書かれてる数字なのかは疑問。内容は9割近くネットショッピングの話で、あとは家やギャンブルに少し触れている程度。現金主義、店舗主義の人にはあまり当てはまらないかもしれない。
Posted by ブクログ
行動経済学に関する本です。
本書の目的として、買い物は自分の幸せにつながるため、真剣に考え、行動経済学の理論を使って、よりよい買い物をしましょうというものです。行動経済学はよく聞きますし、いろいろな理論があることは知っていますが、本書はそれを賢い買い物をするという目的に絞った内容にしていますので、実際の生活に照らし合わせながら読むことができ、入門的に楽しめるのではないでしょうか。
タイトルの「9割の買い物は不要」というのは、若干誇張気味な気もしなくもないですが、売り手側の心理を読み、自分が引っかかってしまいがちな状況を注意するだけでも、十分効果のある内容だと感じます。
▼人は、自分で選んだ物やサービスを使い、それらに囲まれて暮らすことで、自分自身の人生を豊かで充実したものにすることができます。買い物は、自分自身の幸せにつながる前向きな行動であり、真剣に取り組むべきものだと考えています。
▼この本は、こうした買い手の方々のために書かれています。買い物という行動を、買い手はもちろん、関わるすべての人々にとって、よりよいものにすることを目指しています。
▼「よりよい買い物」をおこなうための武器として、本書では「行動経済学」という学問を用意しました。これは人間心理を把握し、よりよい行動につなげるために有効な学問です。
▼行動経済学を通じて得られる重要な知恵の一つは「人の本能に対して、自覚的に対処することが必要だ」ということ
▼買い物において重要なのは、最終的な利用まで含めての満足です。買い方という入り口が衝動的であっても、買った物に間違いがなければ大丈夫です。そこでの間違いを減らすためには、ある程度の時間や手間が必要になります。自分なりにメリハリをつけて、重要な買い物においてはAIDMAのプロセスを使ってみてください。
▼個人的に興味を持った行動経済学の理論
・「ブレークイーブン効果」:含み損の状態にあって、損失をなくすことを強く求める心理のこと(ブレークイーブンは損益分岐点の意味)。損失があきらめきれないときに、これを挽回できると大きな喜びを感じる。
・「社会的選好」:自分自身だけでなく、他社の利益も考慮して選択や行動をおこなう心理のこと。
・「ナッジ」:言葉の訳は「ひじで軽く突く」。禁じることも強制することもせず、またインセンティブを大きく変えることもなく、人の行動をよりよい方向へうながす仕掛けや手法。
・「時間割引率」:将来、手に入る場合の価値が、現在、手に入れる場合の価値に比べて、どのくらい低くなったか(割り引かれたか)を示す率のこと。
・「現在志向バイアス」:目の前にある事柄を実際以上に評価してしまうこと。
・「経路依存性」:慣れ親しんだ状況、過去の経緯や歴史によって決められた仕組みなど、過去に縛られる傾向のこと。
・「イケア効果」:人が自分で手をかけ、時間や労力を費やして完成させたものに対し、特別の愛着を感じ、高く評価するという効果。
・「投影バイアス」:将来における自分の選好を予測するとき、現在の自分の状態に引きずられるバイアスのこと。
・「解釈レベル理論」:対象が心理的に遠い場合は抽象的にとらえ、逆に近い場合には具体的にとらえること。
・「フレーミング効果」:同じ内容であっても、問題の提示の仕方、焦点のあて方により、人の判断や選択が変わるという心理的バイアスのこと。
・「確実性効果」:確率が100%や0%となるような「確実な出来事」に、強く反応する心理のこと。
・「比率バイアス」:数字の多さによって、実際は低い確率を高く見誤る心理的バイアスのこと。
・「コントロール幻想」:自分の力ではコントロールできないものに対しても、自分が影響を与えることができると思い込むこと。
・「ツァイガルニク効果」:中途半端に終わった事柄に関する記憶ほど、残りやすくなる現象のこと。
・「ハウスマネー効果」:運で得られたお金は、苦労して稼いだお金と異なり、ムダづかいされやすいというもの。
<目次>
第1章 ネットの買い物で失敗しないコツとは?-便利そうで意外と不便?リアルより得するおススメの買い方
第2章 「損したくない」という人ほど損しているー「損した」と思うと、その2倍は「得した」気分が必要になる
第3章 買い物での選択で間違えないポイントー「どうしようかな?」と迷ったときに頼れるエビデンス
第4章 絶対に後悔したくない「大きい買い物」-家、保険、ギャンブル…大金が動くときに使える知識