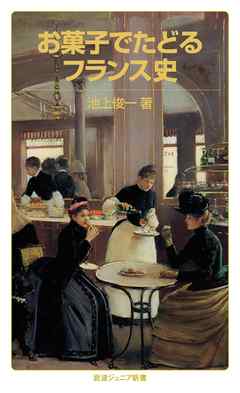感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ジュニア新書だが、高校生でも楽しめる内容で大変面白かった。フランス史は今まで興味を持っていなかったが、この機に自分の興味ある分野の他にもフランス史の本を読み込んでみようと思った。
Posted by ブクログ
いろいろなケーキを目にすることはあっても、その由来は知らずにいたので読んでみた。お酒や絵画と同じく、ケーキもそのストーリーを知ることで楽しめると感じた。
ル・ププランというお店で、サントノーレというケーキを一目惚れして購入し、そのいわれを調べたのが本書を読んだ遠因だが、スイーツにそこまで興味がない私でも興味深く読むことができ、ケーキを好きになったと思うので、とても印象に残った本となった。
本書に限らず、児童文学は大人にとっても面白い本が多いと感じる。
Posted by ブクログ
趣味が高じて本出しちゃった、みたいな本。 フランス史、と書いてあるものの、特に序盤などはフランス以外の部分も多い。簡単にではあるが世界史の流れも書いてくれているので、背景知識がゼロでも常識程度の世界史の知識で何とかなると思う。読んでいてとても楽しい。
Posted by ブクログ
東大大学院教授池上俊一著 岩波ジュニア新書
生きるためには不可欠ではないのに生活に
甘美なうるおいを与え幸せを与える不思議な食べ物。おフランスで発展し国家戦略としてどのように利用したかがよくわかります。ゴーフル、ドラジェ、ビュッシュドノエル、マカロン、クグロフ、シャルロット、マドレーヌ、サヴァン、ブランマンジェ、ルリジュース、タルト・タタン、ミルフィーユなどほとんど食べたことないですがどれも優美な響きでおじさんも憧れます(笑)
Posted by ブクログ
フランス史をザクッと振り返りながらお菓子の歴史も振り返るという本。フランス料理・菓子が現代に至るまで賞賛されたのはイメージ戦略によるものだというのは納得してしまった。中高生の時に読みたかった。
Posted by ブクログ
お菓子のはなしをベースにした簡潔なフランス通史。お菓子の話題以外は重要なところだけポイント絞って概説してくれてわかりやすい。個人的に白眉はカトリーヌどメディシスがくるまえのフランスでは肉を手掴みだったりとか、イタリアの文化が入って洗練されあのだなということ。あと、受け入れるフランス。砂糖大好きフランス。ゾラの胃袋のはなし読んでみたいと思った。パサージュ。
Posted by ブクログ
フランスの歴史を学びながら、国王・皇帝、ブルジョワ、カフェ、科学技術が、フランスのスイーツを進化させたと説得力あふれる歴史を学べる。
偉大な政治家の名前も大切だが、食の文化史も重要だと著者は、読者に問いかける。
これから、パリに旅行する人や職業として職人になる人にも、おすすめしたい良書。
Posted by ブクログ
フランスの大まかな歴史をそれとともに歩み発展してきたお菓子を題材に書かれており飽きずに読むことができる。フランスが与える文化的な影響なども感じることができる。
Posted by ブクログ
へそ曲がりですみません。作者さんが本文中で「やはりフランスが一番素晴らしい」に類することを述べるたび、心の奥底で「いや、和食と中華もすごいでしょ」と反論を呟きながら読むので疲れました……。
全体に楽しく面白く美味しく読めましたが、根っこの部分の「〇〇だからフランス一番」の〇〇の部分に今ひとつ説得力が感じられず残念でした。
一番一番言わないで、普通に「素晴らしい」とだけ言ってくれれば良かったのに……。
Posted by ブクログ
フランスと言えば、グルメ。その中でも甘ちゃん好きが思い浮かべるのはお菓子。ということで今回は、お菓子から見たフランス史の本を取り上げる。
本を読んでいてフムフムと思う点があった。それはイタリアから洗練された料理やマナーを教わらなかったら、今の「料理はフランスが一番」とはならなかったということだ。著者曰く、特にものすごくおいしいと言うわけでもなく、フランス人の食に対する知識や感性が鋭いと言うのは「まったくの嘘」という結果のアンケートがあったと言及している。
では、どうして「幻想」なのに、謝罪会見をしたり、裁判に訴えられることがないのか。それは、絶対王政以降、フランス各地の食材や料理の良い所を取り入れ、中央集権体制の元で、「フランス料理」のイメージが作られて、高級料理としての地位を確立して広く世界に普及したからと著者は指摘している。やはり、イメージ戦略はいつの時代も重要だな。
日本でも、鉄道の発展に伴って地方の名産品が全国に広まって、今では全国的に有名になったお菓子や駅弁は数知れず。フランスでも、鉄道のおかげで、地方でしか手に入らなかった食材や、知られていなかった地方のスイーツが有名になったとある。
お菓子が存在する理由について著者は以下のように述べている。
しかし、甘味料、つまり砂糖は、香辛料とおなじように、生きるために必要というわけではありません。それはむしろよりよく生きるために必要なものなのです。
確かに生活必需品かと言えばそうではない。しかし、甘ちゃんには必要な「人生の栄養源」の1つだ
Posted by ブクログ
フランス菓子の歴史、楽しいです。お菓子がいかに政治・経済・社会・宗教・文化と結びついているかということがよくわかる。侵略の歴史や王家の婚姻とも密接に。
たとえばマカロンやアイスクリームは中世、イタリアからフランスに嫁入りしたカトリーヌ・ド・メディシスによって伝わったし、チョコレートはスペインからやってきた。スペインの王女アンナがブルボン朝のルイ13世に嫁いだことがきっかけ。
序章で「私の信じるところでは、ほんとうに歴史を映す鏡として、社会や文化の重要な要素として、それらを象徴するものとなっているのは、フランス菓子だけだと思うのです。」という著者の主張はちょっとだけ強引な印象。
P82~83
イングランドなどプロテスタントの国では、料理・食べ物とは、飢えを鎮めるためにあるのであり、新たな食欲をかき立てるようなことは好ましくないとされました。そして、市場で高い金で食べ物を買うよりも、自分の菜園から取ってきたもので済ませられればなお良いとされ、健康によい質実剛健な食べ物を奨められました。料理書にも、単純さと節約が大いにほめたたえられています。プロテスタントの国々は、フランスやイタリアがとったような、料理を社交と善き生活術の一部とするだけでなく、芸術の一分野にまでしてしまう路線に反抗しました。
ところがカトリック諸国にとっては、美食と誠実、礼節は相反するものではまったくありませんでした。それは、大食や食いしん坊、酔っ払いとは違うのです。飲み食いして素直に快楽を感じるのが、どうして悪いことでしょうか?
Posted by ブクログ
お菓子を軸に歴史を読み解くのが斬新でおもしろかった。
作者が指摘するようにお菓子は人生に必要不可欠というものでないけど、それを磨いてきたフランスという国の歴史や文化は色々学ぶものがある。
古代では神と人とを結ぶものだったフランスのお菓子が、庶民の間にも広がっていって、そして世界中の人々に愛されるまでになったんだなと思うと今までとは違う美味しさも感じられそう。
Posted by ブクログ
フランス菓子は世界一?
著者はカントリー風のお菓子も良いには良いが、なんだか冴えない印象だと述べている。
少し言い過ぎのような気もするが、確かに映画『マリー・アントワネット』にでてくるようなお菓子にふさわしいのは素朴な茶色いお菓子ではなく、真っ白な生クリームに柔らかなカスタード、うっすらと頬をそめたような桃色......。
デパートの地下にあるお菓子売り場に行けば、人が群がっているのは入り口近くのフランス菓子を扱う店。
人気なのは間違いない。
著者は和菓子については対抗関係にない、全く別の「美」であるとして同じ土俵においていないことを付け加えておく。
フランスの歴史をお菓子とともに歩むのは面白い見方である。
その中で大事なのが「精髄」というもの。
これがフランスの根幹にあるのだそうだ。
精髄は国土と不可分でそこを離れてはあり得ないもの。
終章では、その「精髄」がグローバル化のなかでどう保つのかにまで言及している。
初めは甘くなかったお菓子が大航海時代を経てどんどん甘く、美しくなっていく様子は読んでいて楽しい。
紅茶の世界史のようで、初めはごく小さな地域の物語が、ある時を境に大きく広がっていく様子は歴史の面白さを感じさせる。
女性差別がまだまだ根強かった頃、女性には真の美食能力はなく、グルメにもワイン通にもならないが、甘いものには通じていると考えられていたそうだ。
また、チョコレートは女性を気絶させるほど院微な飲み物で色欲と結びつけられたとも。
全く何の根拠もないが、18世紀になるとその女性性がお菓子界を牽引するようになっていた。
動物の時代から植物の時代へ......。
この力関係が変わっていったのも興味深い点である。
以前紹介した『お菓子の由来物語』を隣において見てもらった方がより具体的にお菓子の姿がわかると思う。
(本書の参考資料でもある)
本書ではかわいらしいイラストが巻頭にカラーで載っているが、お菓子自体の写真はなく、聞き慣れないお菓子だとわかりにくいのではないか。
主に歴史上の人物、場所については写真も使われているが、肝心のお菓子はというと、イラストなので残念な気持ちになる。
とはいえ、一国の歴史をじっくり学べるのでフランス史に興味があれば有意義な読書になると思う。
Posted by ブクログ
フランスの中世から現代までのお菓子の歴史とともに紐解く歴史書。
お菓子が君主の威厳を表すためや、外交上に使用されていたというのは初めて知った。
Posted by ブクログ
お菓子、それはフランスの歴史を彩る武器。
お菓子の歴史ではなく、フランスの歴史とお菓子。なぜフランス料理であったり、フランスのお菓子だったりが、一流の物として世界にフランスのイメージを作ったのか。フランスがフランスたる拠り所とは。
イタリアからやってきた洗練された食文化。それを取り込み、発展する宮廷文化。フランス革命によって、市民のものになる食文化。砂糖を使えることの意味。庭園や建築と共通する飾りへの興味と追求。鉄道建設と地方の名品がパリに集まること。そして、戦争と植民地、技術革新と新しいお菓子。
フランスは、このグローバル社会の中で、フランスであることをどこまで守るのだろう。また、どこまで「フランス」を広げるのだろう。今まで通りにはできない、きっとフランスには難しい時代。憧れの「フランス」はもうイメージの中にしか存在しなくなるかもしれない。フランスのこれからを見守りたい。
Posted by ブクログ
カトリック教会は食事と食卓において社会のエリートたちを文明人にふさわしい礼儀正しい立ち居振る舞いと慎ましやかな社交のできる人間に育てていこうとした。
フランスには甘いものやデザートと女性が結び付けられる傾向があった。女性は甘いものを通じてこの好みを子供と共有するとされていた。
Posted by ブクログ
Flâneur 遊歩者/散策者
デュマの大料理事典読んでみたい!と思って検索したら、通常版はプレミア価格、特装版はその上を行くので手が出ないっ。
岩波さん、そのうち文庫化もお願いします…orz
お菓子分もうちょっと多めだったらな~。
口絵も絵よりは写真が良かったです。ぐぐりながら読んだり。
フランス人のイメージ戦略すごいなぁ。しみじみ。
少し前に「チョコレートの歴史」と言う本を読んだのだけど、チョコレートのところで同じエピソードが取り上げられていてふふっとしてしまいました。
Posted by ブクログ
お菓子を通じてフランス史を俯瞰している本。
ジュニア新書だけあって、平易な文書で書かれており、読みやすい。
お菓子は生きるために不可欠なものではない「余分なもの」であるがゆえに「文化の精華」である、という切り口から、フランス文化史を語る内容になっている。
フランス史>お菓子の歴史という比重になっている印象。全体を俯瞰する、あるいは興味を持つきっかけとしては優れた本だと思う。
ただ、かなり駆け足で語られている印象なので、ある程度の知識があるか、これをきっかけに他の本などで学ばないと、理解しきれないようにも思う。
Posted by ブクログ
昔から世界中の人々を魅了してきたお菓子。教会や修道院で生まれ、やがて王や貴婦人たちへ…魅力的なお菓子を通してフランスの文化・歴史・社会が網羅的に学べる美味しい1冊。
Posted by ブクログ
題名通り、お菓子に関する方向からのフランスの歴史。
食べ物を軸にしているので、それを持ちこんだ人
広めた人の中に歴史上の人がちらほら。
多分テスト何かに出てこないような人もちらほらw
思いこみ、もしくは刷り込み? で
世界一美味しいと言われるフランス料理。
しかしあれは素材の限界までぎちぎちに料理しているので
濃い味が苦手な人にはちょっと…な料理。
日本人にも余り合わないかと。
そもそも体質が違いますし。
語られた中で知っていたのは、マドレーヌの話のみ。
他は、そうだったのか、という程度。
歴史が嫌いな人には、こういう方面からとっかかると
いいかも知れません。
実になるかは謎としてw
Posted by ブクログ
ベルばらとか三銃士とかモンテクリストとかエリザベート(それはオーストリアや)で、若干というか部分的なフランス史は知っているけれども、なかなか一つの歴史の流れ、てか順番が不明瞭(政権の名前順って意味で)、だったのが分かったようなわからないような(どっち!)
お菓子と歴史?!なんて思うけど、お菓子で政治や歴史が動いたわけではないけど、政治=人の流れによって、いろいろなモノや事がフランスに入ってきたことで、の歴史。こういった方面から見ることって滅多にないから、そういう意味では面白いと思う。
し、何よりもお菓子が食べたくなる・・・
Posted by ブクログ
フランスのいろいろなお菓子を歴史にからめて説明しています。中高の冬休み課題用かも知れません。歴史内容は、中高生のレベルに合わせています。
このお菓子がフランスのどの歴史と関わって、作られたかということはとてもおもしろいです。割となじみのあるお菓子が多いのです。口絵にお菓子のイラストがあるので、名前をすぐに思い出せなくても、見たこと、食べたことが多いのが中心です。ああ、口絵を見ただけで食べたくなり、あやうくケーキ屋さんに行くところでした。
宗教起源はクリスマスのこの時期、ぴったりです。クリスマス・ケーキそのものの解説というより、中世のお菓子は神聖なものだったので、修道院で作られたとか、聖体拝領についてとか。今年は歴史をかみしめて、クリスマス・ケーキを頂きます。
著者はイタリア贔屓のよう(抑も『パスタでたどるイタリア史』の続篇)なので、イタリアに軍配をあげ、フランスはそれを「略取」したといいます。文化論でいえば、ちょっとひっかかります。
レシピはないけど、だいたいイメージがわきます。糸砂糖などちょっと食べてみたいです。