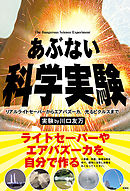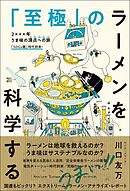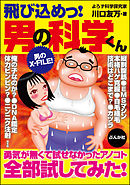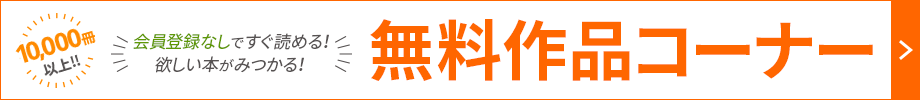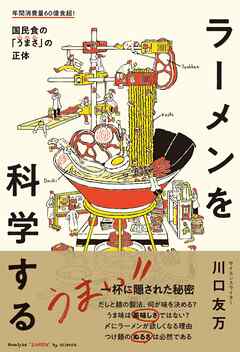
ラーメンを科学する おいしい「麺」「だし」「うまみ」の正体
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
研究者たちの知見を結集した史上初ラーメン科学読本!
年間消費量60億食超!
国民食の「うまさ」を科学の力で解明!
◎世界で5番目の新たな味覚「UMAMI=うま味」とはどんな味なのか?
◎おいしい「だし」「麺」はいかにして生まれるのか?
◎ラーメンの「美味しさ」は何によって決まるのか?
◎実は化学調味料と天然だしは同じだった!?
◎つけ麺が「ぬるい」のには理由があった!
◎〆にラーメンが欲しくなるのはなぜなのか …etc.
病みつきになるラーメンの味を決めるのは、スープのうま味か、麺の食感か? それとも匂いなのか?
いまや国民食となったラーメンは驚くべき速度で日々進化している。
そんなラーメンの魅力を科学の力で解明する初の試み。
これを読めば、いつも食べているあの一杯に魅了される秘密が明らかに!
科学で、ラーメンがもっとおいしくなる。
■本書のおしながき
●第一章 何がラーメンの味を決めるのか?
ラーメン業界にあふれる「○○系」とは?/中毒者を生み出すラーメン店/待ちに待った一杯が「着丼」/うま味の専門家に聞いてみた/ドライマウスを改善? うま味の意外な効用/かけ算で美味くなるうま味のメカニズム/海外にも浸透した新たな味覚「うま味」/ラーメンをより美味しくするために/うま味とはどんな味?…他
●第二章 飲んだ後のラーメン、なぜ美味い?
〆にラーメンが欲しくなる理由/低血糖で欲しくなる炭水化物/酔いと大食いの相関関係/飲むと欲しくなるアミノ酸/背脂チャッチャ系こそ正義?/食べても太らない秘訣/飲みの〆に最適な飲み物/酔った頭を支配するラーメン/食べてしまった翌日の対応策…他
●第三章 おいしい「麺」とは何か?
自家製麺とはなんなのか?/小麦の味と種類を決めるもの/なぜラーメン店は国産小麦を使うのか?/ちぢれと加水率/かん水あっての中華麺/中華麺が黄色いの秘密は?/かん水とは何か?/謎の単位、ボーメ度/小麦が小麦粉に変わるまで/国産小麦を使う理由/麺を水洗いすると締まる理由/おいしい麺とは何か?/麺だけを味わうラーメン…他
●第四章 つけ麺はなぜぬるいのか?
私はつけ麺がわからない/味博士に会いに行く/温度で変わる味のバランス/うま味を足せばおいしくなる?/味の対比効果と抑制効果/コーヒープリンラーメンはおいしいか?/“ぬるい""ラーメンを食べる…他
●第五章 無化調ラーメンとは何か?
ラーメンを嫌う人たちもいる/味覚破壊トリオと無化調ブーム/栄養を見せかけることの問題点/無化調店の裏事情/化調を使ってもちゃんとしているラーメンとは?…他
●第六章 インスタントラーメンの科学
そもそも即席麺は危険なのか?/カップヌードルミュージアムへ行く/50年間、毎日ランチはチキンラーメン/チキンラーメンができるまで/『瞬間油熱乾燥法』という発明/即席麺の業界団体を訪ねる/安全になった即席麺の油/環境ホルモンの間違い…他
●第七章 名店の味を再現しているのは誰か?
どこのスーパーにもある「銘店伝説」とは?/香川県のアイランド食品へ行く/味は信頼関係によって再現される/開発の現場に潜入/エキスメーカーへ行く/充填技術の進歩で保存料が無用に/「酵母エキス」とは?/ひとつじゃない乾燥法/塩分濃度を調べる原理…他
●第八章 人はなぜ「ずるずる」とすするのか?
マンガに見るラーメンの音/クックパドに話を聞く/マーケティングで使われるオノマトペ/検索ワードに見る日本の食卓/意味が変わる食事のオノマトペ/AIで作るオノマトペ/ラーメンに最適なオノマトペとは?…他
●第九章 なぜあの店にばかり行列ができるのか?
詳しい情報を見る
閲覧環境
- 【閲覧できる環境】
- ・ブックライブ for Windows PC(アプリ)
- ・ブックライブ for iOS(アプリ)
- ・ブックライブ for Android(アプリ)
- ・ブックライブ PLUS for Android(アプリ)
- ・ブラウザビューア
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
ラーメンを科学する おいしい「麺」「だし」「うまみ」の正体 のユーザーレビュー
ラーメンを科学する おいしい「麺」「だし」「うまみ」の正体 の詳細情報
閲覧環境
- 【閲覧できる環境】
- ・ブックライブ for Windows PC(アプリ)
- ・ブックライブ for iOS(アプリ)
- ・ブックライブ for Android(アプリ)
- ・ブックライブ PLUS for Android(アプリ)
- ・ブラウザビューア
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。