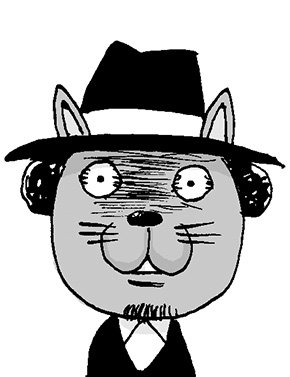田中圭一×『奴隷区』オオイシヒロト先生インタビュー

手塚治虫タッチのパロディーマンガ『神罰』がヒット。著名作家の絵柄を真似た下ネタギャグを得意とする。また、デビュー当時からサラリーマンを兼業する「二足のわらじ漫画家」としても有名。現在は京都精華大学 マンガ学部 マンガ学科 ギャグマンガコースで専任准教授を務めながら、株式会社BookLiveにも勤務。

インタビューインデックス
- 自分の個性を消し、ターゲットを意識した作画に
- ネームは履歴書。1社がダメでも諦めない
- 連載誌休刊で目覚めた「受け入れられる作品」への意識
- マンガ版は小説の「プロモーションビデオ」、それを象徴する“一コマ”
- まだ誰も見たことのない絵を生み出したい
自分の個性を消し、ターゲットを意識した作画に
――まずは、『奴隷区 僕と23人の奴隷』(以下、『奴隷区』)の連載に至るまでの経緯を伺いたいと思います。
もともと連載していた小学館の『週刊ヤングサンデー』が休刊する前くらいから、原作つきの話がちょこちょこ来るようになっていました。小説などがすでにあるものをマンガにする仕事が増えてきて、そこでマンガに対する考え方が変わっていきましたね。
――原作つきの作品をやっていくにあたって、描くうえでのスタンスが変わっていったのですか?
まず思ったのは、「自分の個性をなるべく消したい」ということでした。原作の世界観や雰囲気を、どれだけ再現できるかが勝負だと思ったので。
――なるほど。かつて、個性的な原作者と個性的な漫画家がコラボして失敗してしまうケースをたくさん見てきましたが、「個性を消す」というのは、絵に特化していく漫画家の姿勢として、重要なキーワードかもしれませんね。
原作つきの作品を描くようになって気づいたのは、「自分は演出するのが好きなんだ」ということでした。ストーリーを作るよりも、すでにある話を「どう見せたら面白く表現できるか」を考えるのが好きだと気づけたのは大きかったと思います。
――それは僕も共感できます。最近、取材マンガの仕事も多いのですが、テープ起こししたものからマンガを描く時は、フィクションのようにストーリーやギャグを考える必要がないんですよね。そうすると、見せ方や演出に注力できる。インタビューの場合、いろんなことを聞いて、いろんなことが返ってくるから、結構とっちらかるんですけど、エピソードをポストイットに書き出してページ割りしたものにぺたぺた貼りながら、どれを残して、どれを落として、入れ替えて……読んでいる人にどう感動してもらうかを考えます。作画に徹した時は、こういう余裕ができますよね。
ちなみに、『奴隷区』は双葉社からの依頼だったのでしょうか? これは担当さんに訊いたほうがいいのかな? もともと小説として売れていたということもあるんでしょうけど、コミカライズの作画の方を人選するにあたって、こんな人がいいという条件はあったんですか?
担当編集 石塚さん:もともと、本が出る前からマンガにしたいと思っていた作品でした。作家さん選びに際しては、ストーリーが殺伐としているので、話そのままの路線の絵柄を持ってくると化学反応が起きづらいんじゃないかと思っていたんです。もっとギラギラした絵柄や、劇画調の方でもアリだとは思うんですが、オオイシ先生の作品を読ませてもらって、キャラクターに温かみや愛らしさがあって、憎めない雰囲気に惹かれたのでお願いすることにしました。それまでオオイシ先生が描いていた作品とは、全然違うジャンルだったかもしれないですけど、「まずは原作を読んでみてください」とお願いしました。
――それは、すごく腑に落ちる話ですね。原作の世界観をそのまま持ってこようとすると、頭の中に出てくるビジョンは『漫画ゴラク』とかに描かれるような絵柄なんだけども(笑)、オオイシ先生の絵は、確かにまろやかなんですよ。激辛カレーだけど、リンゴをすり下ろして入れているような感じです。その意図はすごく的確だったんですね。
オオイシ先生は、そのお話をいただいた時、原作は知っていたんですか?
いや、知らなかったですね。
――読んでみてどうでした?
確かに、全く描いたことがないジャンルではあったんですけど、原作に勢いがあったんですよね。どんどん続きが気になる、いい意味で荒々しさがあって、マンガとしてもいろんな表現を見せられるんじゃないかという感覚はありました。
――つまり、演出の余地があったんですね。
そうですね。最初に読んだ時に、面白いシーンのイメージがすぐに湧いてきました。
――いざ始めてみて、想定外の苦労みたいなものはありましたか?
最初の頃は、絵柄を固めるのに苦労しました。『DEATH NOTE』とか、その辺りの絵柄を目指しながら。それまでメインで描いていたのは“描き込む系”の絵柄だったので、「どれだけ綺麗な絵柄に見せるか」という点で試行錯誤しましたね。
ちょうど、この作品からフルデジタルになって、すごく綺麗な線が描けるようになったんです。デジタルのおかげで(笑)。
――これ、液タブ(※1)で線から起こしてます?
そうです。
――だから細いんだ!
そうなんですよ。僕は、つけペンだとブルブル震えちゃったり、何重にも重ねちゃったりするタイプで、それが本来の絵柄なんです(笑)。でも、デジタル化のタイミングが合ったおかげで、綺麗な見やすい絵に変えることができました。
あと、デジタルで良かったのは、ぼんやり光っている場面など「光の表現」をすごくしやすくなったことですね。『奴隷区』は夜が舞台になるシーンが多いので、そういう場面で雰囲気を出せる絵を作りやすくなったのは、デジタルのおかげですね。
「液晶タブレット」の略で、ディスプレイ画面に直接描き込めるタブレットのこと。漫画家、イラストレーターにも愛用者が多い。代表的なメーカーはワコム。似たデバイスとして「板タブ」があり、こちらは従来から存在する「ペンタブレットに書いたものがモニターのカンバスに反映される」タイプのもの。
――セロファンに包まれている「光沢」なんかも、デジタルでないとかなりテクニックが必要なところですよね。

『奴隷区』に関しては、テクスチャをすごく使っています。何でもないコンクリートとかを写真で撮って絵に被せて不思議な質感を出すようなことも、画像処理で簡単にできますから。
――これ、アナログでやると大変ですよ。
できないですね(笑)。
――表現が広がっていくのは、デジタルの良さですよね。あと背景にも、ところどころ写真から起こした絵が使われています。

やっぱり、この手の話はリアリティを持たせないといけないから、写真を使うのは正解なんですよね。SCMが世の中に本当にあって、これらのことが東京都内で実際に行われてるんだと、読者に信じさせる上ではすごく重要で、もちろん効率面もありますが、すごく意識されている感じがしました。
その『奴隷区』の絵づくりで、注意されていることはありますか?
『奴隷区』の前に、『王様ゲーム』(※2)が発売されていて、実績もちゃんと残していました。『奴隷区』は、そこと似た読者層をターゲットにしようということを、最初から見据えていたんですが、それが良かったんだと思います。「どんな読者に向けて何を描くか」を、自分の中でもしっかり意識しながら描けました。その前に青年誌で描いた時は、予想以上に高かった読者の年齢層に苦労したことがあったんですけど、『奴隷区』はピンポイントでターゲットがはっきりしていたので、自分の中に明確なイメージを持ちながら描くことができました。
――やっぱり、読者をちゃんと分かっていて、その反応を見ながらブラッシュアップしていけるというのは大きいですし、作家としてすごく力がつきますよね。ストーリーも絵柄も、読者にウケるもの、読みやすいものを意識するようになった結果、ヒットに結びついたんだというのが分かります。
エブリスタで人気を博したケータイ小説をコミカライズした、原作・金沢伸明、作画・連打一人によるマンガ作品。謎の「王様」からメールで届く命令が次第にエスカレートしていく中、生き残りを懸けて戦う主人公達が描かれている。
ネームは履歴書。1社がダメでも諦めない
――漫画家としてのキャリアはどれくらいになりますか?
連載を持てたのが23歳の時で、わりと早いうちから描かせてもらっていたので、かれこれ10年以上はマンガの仕事をしています。今連載している『奴隷区』で、ようやく日の目を見たというか、多くの人に読んでもらえるようになった感じはしています。
――漫画家を目指すようになったきっかけを伺いたいんですが、本気で進もうと思ったのは、いつ頃からでしょうか?
もともと絵は好きで描いていたんですけど、リアルに漫画家を意識し始めたのは高校時代ですね。大学進学をどうするかという時に、なんとなく「大学には行きたくないな」と思いまして。その時点で漫画家を目指したいと思うようになり、専門学校に進んだという流れです。
――それまでは、コマを割って描いてみたりというのは?
ちゃんと描いたことはなくて、ペンもほとんど使ったことがありませんでした。漫画家を意識し始めた高校3年生の時、まわりの友達が受験勉強を本格的に始めたくらいになって、ようやくペンを持ち始めたという感じですね。
基礎知識が全くなかったので、まずは基本を押さえなくてはと思い、専門学校に行きました。
――専門学校で「へぇ~!マンガってこういうふうに作るんだ!」みたいな驚きはありました?
それはもう、知らないことばかりでしたから新鮮でした。でもその頃から基礎的な作業がすごい苦手だったみたいで……例えば、定規使って線を引いたりとか(笑)。
――パース(※3)って、マンガを描く中で唯一"算数"を使うじゃないですか。しかも時々こんがらがって分かんなくなってね。僕も大学で学生に教えてますけど、パースをどうやって楽しく理解させるかというのは、結構苦労するところです。
まさに、パースの授業だけはすごく嫌いでした(笑)。
周りもそうでしたけど、やっぱり10代の時は「キャラが描きたい!」という思いばかりが強くて、背景までちゃんと描こうという意識はなかなか持てませんでしたね。
――でも、23歳で連載を持てたということは、専門学校を20歳で卒業して、たった3年で連載ですか。専門学校で初めてマンガを勉強したという人がそれほど短期間で連載を持てるものなんですか? つまり、下積み期間があまりなかったってことですよね?
20歳で卒業して、すぐに上京しました。ちょうど『アフタヌーン』の四季賞(※4)をいただいていたので、それがきっかけになったんです。
とはいえ、そこから1~2年はうまくいかず、バイトをしながら描いている状況でした。その矢先、マンガのアシスタントの仕事を紹介されて、1年間アシスタントをやりながら、連載の話にこぎつけることができました。下積みという意味では1年ぐらいなので、確かにスムーズでしたし、幸運だったかもしれません。
パースペクティブ(遠近画法、透視図法)の略。絵の中で、物や建物の立体感、風景の奥行きを表現するのに用いる技法であり、背景を描くためには、一点透視・二点透視・三点透視などの知識が必要である。
講談社の『アフタヌーン』が主催する、完全ジャンルフリーの新人漫画家登竜門。雑誌創刊時の1986年から続いており、年4回開催される。
――アシスタント生活が約1年ということですが、アシスタント時代に急に開眼したというか、力がついたという実感はありましたか?
その1年間がとても濃くて、いろんなものを急激に吸収した時期だったと思います。週刊ペースで連載することの大変さも、身にしみて経験しました。
でも、先生が自分の2歳上くらいで歳が近かったこともあり、「自分も努力すればこんな風になれるかもしれない」という具体的な目標になったのは、ありがたかったですね。
作業も、泊まりこみでずっと一緒にやらせてもらったので、マンガに対する姿勢も感じることができて、どちらかというとメンタル面を鍛えてもらった気がします。どれだけボツを食らってもめげないとか(笑)。
――度胸が据わったんですね。僕が教えている学生も、初めて持ち込みに行って編集者にケチョンケチョンに言われると、がっつり落ちこんじゃうんですよ。教える立場としては、そこをフォローしながら、「いやいや、自信持って大丈夫だよ」と気持ちを上げていかないといけなくて。10代の頃は脆いし、特にマンガを描く人はセンシティブな人も多いから、立ち直りが早い人もいるけど、停滞してしまう人もいる。でも、そういう子はアシスタントに行けばいいと思うんですよね。オオイシ先生のお話の通り、確かに現場を知ることの一番の効果は、メンタル面だなって気がしますね。
今まで、いろんな出版社の方とやってきたんですけど、1社がダメでも「違う人に見てもらって評価してもらえばいいや」とは、ずっと思っています。1つのところで諦めずに持ち込み続けて、なかなか芽が出ない人も多いですけど、とにかくいろんなチャンスを掴みたいので、持ち込める限り持ち込んでやろうという意識は、最初から持っていましたね。
――担当編集さんとの相性も重要ですもんね。前回、『となりの関くん』の森繁拓真先生のインタビューの時にも、編集さんとの話があったんです。編集さんが言うままに直すのか、自分の信念をぶつけて喧嘩するのか、それとも分かってくれる人を探しにいくのかという、いくつかの選択肢がある中で、森繁先生は馬の合う編集さんを見つける旅に出た。それは1つの答えだなと思いました。
そう思います。1人がダメと言ったからって、本当にダメなのかな? って。
自分のスタッフにも言っているんですけど、僕らにとってネームは履歴書みたいなものじゃないですか。それを持って、自分からいろんなところに営業に行かないといけないと思うんです。たまたま合う会社があれば認めてくれるだろうし、ダメなら次に行けばいい。1人の言うことに固執して、自分の履歴書で嘘を描いても仕方ないですからね。
連載誌休刊で目覚めた「受け入れられる作品」への意識
――最初の連載作品というのは?
『ヤングサンデー』で、「日本フーリガン」という作品で連載デビューさせてもらい、そのあとも何本か連載させてもらいました。でもその後、『ヤングサンデー』が休刊になってしまって、それがすごく衝撃的だったんです。
なんかこう、のんびり考えていたというか、自分のマンガが載って「なんとなく生きていけるんじゃないか」とか、「大手の出版社に頼っていれば大丈夫じゃないか」とか思っていた矢先に、突然雑誌がなくなってしまいましたから。担当の方も異動になり、自分の描いていた枠はもちろん、編集長さんも変わってしまって。「これから、どうやってマンガを続ければいいんだろう?」と、放り出されてしまったような形になったんです。それで「そんなんじゃダメだ!」と。生き抜いていくために、いろんな出版社に持っていって、自分に合うチャンスを掴まないといけないと思ったんです。
――なるほど。連載誌が休刊という経験も、先ほどの持ち込みのモチベーションにつながっていくんですね。
そこでマンガを、もっとビジネスというか、生活していくための一つの仕事として捉えるようになりました。それまでは自分の描きたいものを好きなように描かせてもらっている感じでしたが、「受け入れられる作品」がどういうものなのかを、すごく考えるようになりましたね。
――その試行錯誤の中で、答えはありましたか?
いま『奴隷区』の連載をやりながら、リアルに感じていることですが、やはり読んでくれる人が増えて、読者のリアクションが自分でも手に取るように分かるようになってくると、「ここはもっとこうしたほうがいい」「こうしたほうが面白がってもらえる」ということを、すごく考えやすくなりましたね。今までは、描いても反応が分からないことが多かったんです。自分の表現や描き方が良かったのか悪かったのかも判然としない。ただ、「人気がなかったからダメだったんだろうな」という程度の、漠然とした感触しかなくて。
――なるほど。一つの連載がヒットして、その中でどんどん力をつける漫画家が多いのは、そういった読者からの反応によるところも大きいですよね。
さて、少し話が戻りますけど、影響を受けた漫画家に松本大洋さん(※5)を挙げていただいたのですが、作品に出会ったのはいつ頃ですか?
専門学校に入った時くらいですね。それまでは、マンガと言えば『週刊少年ジャンプ』で、他の作品の知識はほとんどありませんでした。でも、専門学校にはいろんなマンガを知っている人がたくさんいて、そこで教えてもらったのが松本大洋先生でした。「こんなマンガがあるのか!」「こんなにおしゃれな世界があるんだ!」という驚きがありましたね。
1987年に『月刊アフタヌーン』増刊号でデビュー。以後、マンガを中心にイラストレーターとしても活躍し、1993年から連載した『鉄コン筋クリート』で一躍有名作家となった。その他の代表作に『ピンポン』『竹光侍』『Sunny』など。大胆かつアーティスティックな作風は、マンガ界に1つの流れを作ったと言っても過言ではない。
――アートですよね。
そうなんです、今まで見たことがない表現でした。自由さというか、どんなものでもアリで、あらゆる可能性が試せるフィールドという気がして、それで青年誌で描きたいと思ったんです。
あとは、松本先生の映画っぽいアングルが好きなんですよね。かっこいい構図が分かりやすく表現されていて、自分の好みにピンポイントでハマった感じでした。
――本来であれば、このタイプの絵柄は『ガロ』とかに閉じこもってるはずなのに、松本大洋さんはこの絵でメジャーシーンに出てきたというのが大きいですよね。『ビッグコミックスピリッツ』で何作もヒットを飛ばして。
でも、小学館で描いていた頃は、そのぶん苦労もあって……編集さんから「松本大洋みたいにやるな」と言われました(笑)。当時、松本先生の影響を受けた新人が多くて、松本先生みたいな絵柄やストーリーで持ってくる人ばかりだったみたいです。
――小学館としては、“松本大洋もどき”は歓迎じゃなかったんですね、きっと。松本大洋さんは、絵柄だけを見るとアートの匂いのするサブカル方向のマンガかなって思いがちですが、読んでみると中身は熱いドラマなんですよね。この絵で熱い話をやるからメジャーに来たんだって。だからヒットしたわけで、編集者さんが真似してくれるなと言うのも分かります。ワン&オンリーな方なんですよね。
そうなんです。新人はこういうのは描くなと言われていました。だから、最初の頃は「松本大洋が好きです」とは言えなかったですね(笑)。カミングアウトしてしまうと、編集者さんに「こいつややこしいヤツだな」って思われるし(笑)。
――絵柄の影響などは受けませんでしたか?
すごく影響を受けました。ですが、「松本大洋禁止令」が出ていたので、やっぱり「真似してたらダメだな」と思い直して、そうじゃない絵柄を追及していきました。
アシスタントで入ったのが『RAINBOW-二舎六房の七人-』の柿崎正澄先生だったんですが、柿崎先生と、その師匠である佐藤秀峰(※6)先生などの影響を一気に受けましたね。
『海猿』みたいに熱く線を描き込むこともあったり、『奴隷区』でキレイめな絵柄になったり。何に影響を受けたか? と訊かれると、自分でも自分の絵柄がよく分からないくらいなんです。
『海猿』や『ブラックジャックによろしく』など、リアルな人間ドラマが人気の漫画家。『ブラックジャックによろしく』は、2012年から全13巻の完全無料ダウンロードがスタートし、現在も多くの電子書籍ストアで無料購読できる。
――何かと直結しているというよりは、いろいろ混ざってる感じ?
そうですね。その時その時で「良いな」と思うものを取り入れ続けているのが、自分のスタイルなのかなと思います。
マンガ版は小説の「プロモーションビデオ」、それを象徴する“一コマ”
――さあ、それでは本題の「一コマ」の話を伺いましょう。『奴隷区』第1巻・第3話の杉並ルシエのコマを選んでいただきました。
-
-
奴隷区 僕と23人の奴隷 1
「“奴隷”欲しいヤツ、いる?」天才的な頭脳も、超人的な肉体もいらない。どんな勝負でも勝ちさえすれば相手を奴隷にできる器具、それがSCM。偶然にもSCMを手にした24人の主人公は... -
奴隷区 僕と23人の奴隷 2
「“奴隷”欲しいヤツ、いる?」天才的な頭脳も、超人的な肉体もいらない。どんな勝負でも勝ちさえすれば相手を奴隷にできる器具、それがSCM。偶然にもSCMを手にした24人の主人公は...
-