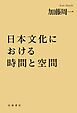配信予定・最新刊
作品一覧
-
-日本の知の礎を築いたのは、飽くなき探求心を持ちつづけた学者たちだった。土居健郎は言う、「まず「わかる」とはどういうことかということをわかる必要があるでしょう」。禅の本質を説く鈴木大拙、インド思想史に人類史的な普遍性を見た中村元、心理療法の目的を自身の物語の発見に見いだした河合隼雄、人間と自然の関係の変化が歴史学に課題をもたらしたと指摘する網野善彦……。日本を代表する「知の巨人」たち、その学問の総決算ともいえる最終講義を精選したアンソロジー。「学究の極み」篇では、日本の知の礎を築いた学者たちが生涯をかけて追究した研究テーマ、その集大成を披露した講義を収録。冒頭に各講義の要約を付し、難解な講義も概要をつかみやすくした。推薦・若松英輔
-
3.9
-
4.21巻2,750円 (税込)日本文化の特徴とは何か.幾度も反復されてきたこの問いに,著者は時間と空間の両面から切り込む.文学・絵画・建築など豊富な作品例,それらを貫く時間と空間の感覚,さらに宗教観や行動規範の分析から,「今=ここ」に生きる日本文化の特徴が鮮明に浮かび上がる.日本文化の本質,その可能性と限界を鋭く問う渾身の書き下ろし.
-
-1巻1,463円 (税込)ここにあるのは若気の過ちではなく、若気の夢、――軍国主義を呪い、詩を愛した日本の青年の知的な客気である。――<「あとがき三十年後」より>。1946年・敗戦翌年、<マチネ・ポエティク>のメンバー 加藤周一・中村真一郎・福永武彦の共同執筆により「世代」に連載された時評は、新しい時代の新しい文学を予告した。時代を超えた評論は日本近代文学史上必読の書となり、なお不動の地位にある。戦後日本文学はここに出発した。
-
5.01巻1,595円 (税込)加藤周一氏が逝ってはや3年。まさに危機に直面している日本と世界の現状を見て「加藤周一だったらなんと言うだろうか……」との思いを抱く向きも多いかもしれません。その一方で「カトウシュウイチってだれ?」という人も確実に増えているでしょう。 本書は、戦後日本を代表する知識人がその晩年、市民グループの求めに応じて談論風発した記録です。 内容は多岐にわたり、戦争と憲法、ファシズム、歴史認識問題、ヒューマニズムと文学・映画、社会主義の功罪など市民からの時に素朴、時に尖鋭な質問に真正面から答え、さらに踏み込んだ答えを示すさまは、さまざまな批判はあるにせよ、「戦後」という時空間の最良の部分がどこにあるかを示してくれます。後続の世代に託された軽やかにして熱い言葉の数々。加藤周一の人物像に迫る入門書としても読める本です。
-
3.01巻660円 (税込)英仏の文化を純粋種の文化と考えるのに対して、日本の文化を、雑種の文化の典型として考え、しかも、善悪の価値観から分離したことに特色をもち、それゆえに希望もあると説く「日本文化の雑種性」のほか、「雑種的日本文化の希望」「日本人の外国観」「日本人の世界像」など10編を収録。当代第一級の国際的文化人・加藤周一が精緻に腑分けした、鋭利な洞察による個性的日本文化論。
-
3.51巻990円 (税込)日本人とは何か。われわれは一体何を望み、何でありたいのか。長い西欧体験にみがきぬかれた知性が、鋭い洞察力を駆使して日本人のありように迫り、将来のあるべき方向を模索した日本人論八編を収録。十数年前に書かれたこれら諸論文は、その歳月を忘れさせる先見の明に貫ぬかれていて、今日の私たちが直面している諸問題をあざやかに浮彫りにしており、日本人と日本文化について思索するすべての人に知的興奮を与えずにはおかない。
-
-1~24巻4,180円 (税込)※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 マチネ・ポエティクのひとりとして『1946 文学的考察』で文壇に登場して以来、文学、芸術を中心にして政治、社会、思想など多方面にわたる評論・創作活動に従事し、戦後日本を代表する知性ともいうべき加藤周一(1919~ )の、旧制高校時代から1979年までの主な活動を集成する。本著作集は、収録著作を精選し、あらたに「追記」「あとがき」による註を加えた、著者自身の編集になる。
-
3.31巻770円 (税込)二〇世紀は日本にとって、実にめまぐるしい百年間でもあった。空前の豊かさと膨大な人的犠牲という強烈なコントラストに彩られたこの世紀は、その時代を体験した人間にどのように映ったのだろうか。優れた文明批評家として知られる著者が、この百年を再考し、新たな混沌が予感される現代を診断する。
ユーザーレビュー
-
Posted by ブクログ
都鄙問答(とひもんどう)
著:石田 梅岩
訳:加藤 周一
中公文庫 968
都鄙とは、都会と田舎ということです
本書は石門心学の祖である、石田梅岩が、問答という形でその教えを広めるために使ったテキストです。
宋学(=朱子学)をベースとしていて、神・儒・仏を日本の古典を読み、まとめ上げた書であるが、その根底には 心を知るという、三教を共に悟る教えが中心になっている
いままで、全集の中ぐらいにしかなく、文庫になってようとはおもってもいませんでした。
2021に中公文庫の古典シリーズの1つとして発行されていました。
丹波の山村で生を受けた梅岩は、隠遁の学者、小栗了雲に出会って、性理の蘊奥を極め -
Posted by ブクログ
時間と空間のとらえかたについて、日本の文化(絵画、和歌、俳句、演劇)からその特徴を捉えようとする本です。まず時間について、世界には(1)はじめと終わりのある時間(ユダヤ教)、(2)円周上を無限に循環する時間、(3)無限の直線上を一定の方向に移動する時間、(4)始めなくおわりのある時間、(5)始めがありおわりのない時間、の5類型がある。そして古事記から始まる様々な例をひもとき、例外はあるものの、日本は(2)(3)の無限の時間の概念が主流だと主張しています。そこでは時間の分節化が難しく「いま」の連続で時間が流れゆくとのこと。
ついで空間についてですが、こちらは(1)開かれた空間、(2)閉じられた -
Posted by ブクログ
20世紀最大の評論家、加藤周一氏の名前が受験国語で頻繁に登場したのは、少し前の時代のこと。『雑種文化』で、文学史の教科書にも名前が載る氏が31歳での執筆のこの書は、1971年に出版された。センター試験では、1991年度の追試験の評論の問題として、この本の最終章である「文学の概念についての仮説」から引用され、出題されている。先日、書店で眺めていた書棚にこの本の背表紙を偶然見つけ、入試問題として授業で何度も扱った一節を含む同書の全体に、あらためてふれてみた。そして、少なからず驚かされた。
それは、氏の文章が、広汎な知識の引用と、鋭い論理展開に特徴づけられながら、実際には、ひどく読み易く平明だという -
Posted by ブクログ
加藤周一は、昭和・平成をまたがり「日本を代表する知性」と呼ばれていた。その加藤が、50年代から数えると約50年以上「時評」を描き続け、08年に自らの死亡によって終わるまで延々と書いていたのだから、時評に並々ならぬ情熱を持っていたのは間違い無いだろう。自らを「非専門の専門家」といい、文学評論家の枠に収まらない批評活動をしていた全体像が、このまとまった「夕陽妄語」全3巻(84年ー08年)の中にあるだろう。これはそのうちの一巻目。
話題は文学はもちろんのこと、文明遺跡、演劇、音楽、映画、国内と国際政治、歴史一般に及ぶ。古今東西の総てのイシューを関連つけて、一つの説得力ある言葉を提示する。実は、私に