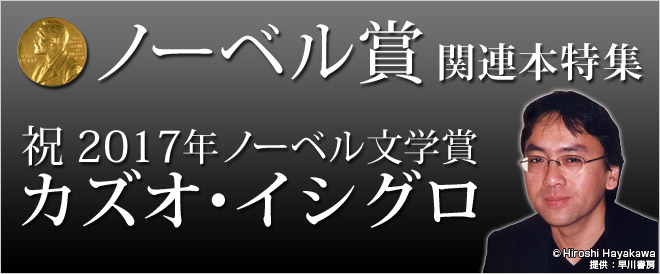作品一覧
-
-1巻1,760円 (税込)千年の昔、一人の女性の手で書かれた五十四帖の壮麗な物語。宮廷ゴシップ、恋愛模様、権力闘争――ほの暗い御簾の陰に潜む人間ドラマと、失意と孤独を抱えた作者・紫式部その人の内奥に、名うての読み巧者が光を当てる。『枕草子』など同時代の傑作も縦横に併せ論じ古典を読む悦びを語り尽くす、知的興奮に満ちた文学案内。
-
-紫式部は平安時代の藤原氏一門の全盛時、京都に生きていた女流作家です。当時の日本は、中国の先進文明と我国の風習とを巧みに調和させた、前後にも類のないような優美繊細な文化を作りあげていました。『源氏物語』の完成に生涯をかけた紫式部はまさに天才で、この物語のなかに、いわば彼女の生きた時代そのものを、全て封じこめてしまおうという野心を抱き、それを実現させてしまったのです。だから、この物語のなかには、数百人の様々な男女が、それぞれの出身階級や家庭やの考え方、感じ方をもって登場します。特に人間生活の永遠の主題というべき愛欲に喜んだり苦しんだりする姿は、私たちにも、ありありと感じられるように見事に描かれています。『源氏物語』は私たち日本人にとって、最大の魂の故郷であり、また己れを写す鏡というべき作品です。しかし、一方で、千年前の貴族の女性の言葉で書かれたこの作品には、言葉の違いという厄介なものがあります。私はまず、この複雑極まりない内容を持つ大ロマンを、近代的な小説として読めるようにしようと思いました。そうして、物語の中心をくっきりと浮き上らせるように試みました。…中村氏はこう述べています。
-
-1巻1,463円 (税込)ここにあるのは若気の過ちではなく、若気の夢、――軍国主義を呪い、詩を愛した日本の青年の知的な客気である。――<「あとがき三十年後」より>。1946年・敗戦翌年、<マチネ・ポエティク>のメンバー 加藤周一・中村真一郎・福永武彦の共同執筆により「世代」に連載された時評は、新しい時代の新しい文学を予告した。時代を超えた評論は日本近代文学史上必読の書となり、なお不動の地位にある。戦後日本文学はここに出発した。
-
-
-
-
-
5.0
-
4.3
-
4.01巻385円 (税込)文章を書くというのはどういうことか。現代における文章とはどのようなものか、また、その望ましい姿とは。――森鴎外・夏目漱石など明治の作家から、安部公房・大江健三郎・井上ひさしら現代作家まで、豊富な文例をあげながら、近代百年の口語文の歴史のあとを辿る。文章を素材にした近代日本文学史であると同時に、文章表現の心構えを分りやすく説いた、万人のための文章講座。
ユーザーレビュー
-
Posted by ブクログ
☆4.5 頼山陽は精神病だった
吉田松陰を知るにあたり、松蔭が影響を受けた頼山陽の伝記を読まうとおもった。
精神病視点で頼山陽を捉へるこころみで、中村自身の鬱病的経験を踏まへてゐる。さう照し合はせてみると、かなり的を射てゐる。そして精神病にもとづく推測が剴切に思はれてくる。
徳川期の遠い時代といふ印象の人物が、いつのまにかわれわれに卑近に迫ってくる感じだ。両親の厳しさと甘やかしは、いまと変らない。
徳川期になかった概念(当時は狂人扱ひしたもの)を、近代の精神病として捉へることで、頼山陽の実像が理解できる。
私としては、頼山陽は発達障害をかかへてゐたのではないかとおもった。 -
Posted by ブクログ
同名のアニメですっかり有名になってしまった『風立ちぬ』でなく、「かげろうの日記」とその続篇「ほととぎす」を採ったのは、大胆な新訳が売りの日本文学全集という編者の意図するところだろう。解説で全集を編む方針を丸谷才一の提唱するモダニズムの原理に負うていることを明かしている。丸谷のいうモダニズム文学とは、
1 伝統を重視しながらも
2 大胆な実験を試み
3 都会的でしゃれている
ということだが、堀辰雄の「かげろうの日記」は、「蜻蛉日記」の現代語訳ではなく歴とした小説である。言葉遣いこそ王朝物語にふさわしい雅やかな雅文体をなぞっているが、主人公の女性心理はまぎれもなく近代人のそれであり、自意識が強く、 -
Posted by ブクログ
堀辰雄の「かげろうの日記」と「ほととぎす」。
ここにはヨーロッパ仕込みの見事な「平安文学の心理小説化」がある。前回配本の森鴎外からもう一歩進んでいる?
平安貴族の生活が生き生きと描写されて、物忌みや、待っていることしか出来ない貴族女性の立場、子供のような道綱(藤原道綱)の振る舞い、揺れ動きながらたまに男を手玉にとる道綱母の行動など、なかなか興味深い。
道綱も成人したころに、夫は他の女に産ませた「撫子」という少女を連れてくる。次第に情が移ってきちんと育て始めたころに、頭の君が撫子を求めてひつこいぐらいに道綱に連絡する。「まだほんの子供ですから」と「いや一目だけでも」何度も何度も同じやりとりを -
Posted by ブクログ
長編というか、いろいろなタイトルがおさまっていて
500P弱を読み終わりました。
堀辰雄氏・福永武彦氏(池澤夏樹氏の父)・中村真一郎氏
3人の作品。
堀辰雄氏の「かげろうの日記」「ほととぎす」は
いまいちわかりませんでした。
福永武彦氏の「深淵」「世界の終り」「廃市」は
3作品ともとてもよかったと思います。
狂気・退廃・情念などがにじみ出ていたと思います。
中村真一郎氏の「雲のゆき来」は漢文や漢詩
古文詩などが多くあって、読みづらい部分が多く
ありましたが、それを差し引いてもとてもよかった
と思いました。
やっぱり自分の知らない作品それも古典的な作品
に出逢える機会は大切だと思います。
この全